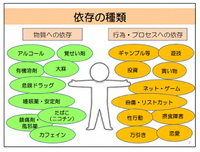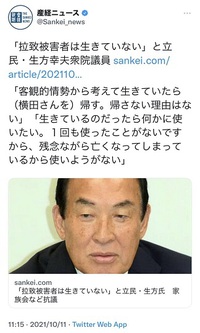江戸のメディア王・蔦屋重三郎
2008年06月28日
前に近代西洋と日本の文化の架け橋と題し林忠正のことを書いたが、
今回は江戸時代の出版界のリーダーとして、
多くの小説家や画家を世に出した功績のある
蔦重こと、蔦屋重三郎について書くことにする。
蔦屋重三郎がいなければ浮世絵版画や洒落本、
読み本、黄表紙などと呼ばれる大衆小説は興隆しなかっただろう。
蔦重は今でいえば、講談社や小学館などの大手出版社を興した人物だ。
蔦屋重三郎は1750年江戸の吉原に生まれた。
吉原は今で言う色町の繁華街で、
新宿歌舞伎町みたいな所である。
彼の父は吉原の遊郭のサラリーマンだった。
蔦重は長じて吉原で書店を営むが、遊郭のガイドブックを作製し大当たりした。
吉原細見という店ごとに遊女の名を記した
案内書が大うけしたのだ。今で言えば「歌舞伎町ホステス名鑑」みたいなものか・・・
蔦重はこれをきっかけに本格的に出版業に進出する。
当時の大衆小説絵本黄表紙に目を着け出版し流行させる。
黄表紙はいまでいう漫画本の走りである。
蔦重は洒落本という色町での遊び方などを描写した風俗小説や、
読み本という純文学的歴史小説などの出版で、
町人文化の興隆に貢献した。

1793年刊 山東京伝『堪忍袋緒〆善玉』の一項。左に山東京伝、右に蔦屋重三郎が描かれている。
寛政の改革で山東京伝の黄表紙が幕府批判しているとされ、
蔦重は罰金と50日の懲役刑を受けた。
その後再起をかけて出版したものが、謎の絵師・東洲斎写楽の役者絵である。
これは今で言うタレントの写真集みたいなものである。
写楽の人物像は諸説あり、一説では蔦重本人だともいわれる。
蔦重に見出され世話になった絵師や文士は相当多い。
またこの時代に有名だった浮世絵師や文士の殆どが、
蔦重と何らかの関係をもっていたといわれる。
喜多川歌麿も蔦重に見出され世に出たし、
十返舎一九や曲亭馬琴も蔦重によって歴史に残った。
蔦重がいたからこそ、江戸の美術や文学が盛んになったともいえるのだ。
蔦重が偉大なのは彼が大衆の好みや嗜好の動きを敏感に察知し、
それを出版につなげていったことである。
今風にいうと市場調査(マーケット・リサーチ)がうまかったのだ。
さらに同時代の西洋との大きな違いは、
一般民衆が書物を購読できる知的レベルの高さと読書習慣の存在、
庶民レベルで絵画を売買する経済市場が出来上がっていたこと。
17~18世紀の江戸は世界でもトップの知的水準と都市機能をもっており、
江戸に匹敵するヨーロッパの都市はなかった。
ちなみにこの時代の江戸の識字率は70~80%もあり、
同時代のロンドンは20%、パリが10%だった。
この知的水準を広めたのが寺子屋と貸し本屋だった。
江戸の寺子屋は19世紀には1000件以上、
貸し本屋は700件もあったといわれる。
換言すると蔦重の出版業が流行ったのはこれらの知的土壌があり、
蔦重の出版がさらに町民の文化的欲求を高めたということでもある。
江戸時代の文化を概観すると、現代との差は殆どないことに気づく。
すでに江戸時代は近世ではなく、近代だったのだ。
ちなみに私は近世の意味を知らない。
今回は江戸時代の出版界のリーダーとして、
多くの小説家や画家を世に出した功績のある
蔦重こと、蔦屋重三郎について書くことにする。
蔦屋重三郎がいなければ浮世絵版画や洒落本、
読み本、黄表紙などと呼ばれる大衆小説は興隆しなかっただろう。
蔦重は今でいえば、講談社や小学館などの大手出版社を興した人物だ。
蔦屋重三郎は1750年江戸の吉原に生まれた。
吉原は今で言う色町の繁華街で、
新宿歌舞伎町みたいな所である。
彼の父は吉原の遊郭のサラリーマンだった。
蔦重は長じて吉原で書店を営むが、遊郭のガイドブックを作製し大当たりした。
吉原細見という店ごとに遊女の名を記した
案内書が大うけしたのだ。今で言えば「歌舞伎町ホステス名鑑」みたいなものか・・・
蔦重はこれをきっかけに本格的に出版業に進出する。
当時の大衆小説絵本黄表紙に目を着け出版し流行させる。
黄表紙はいまでいう漫画本の走りである。
蔦重は洒落本という色町での遊び方などを描写した風俗小説や、
読み本という純文学的歴史小説などの出版で、
町人文化の興隆に貢献した。

1793年刊 山東京伝『堪忍袋緒〆善玉』の一項。左に山東京伝、右に蔦屋重三郎が描かれている。
寛政の改革で山東京伝の黄表紙が幕府批判しているとされ、
蔦重は罰金と50日の懲役刑を受けた。
その後再起をかけて出版したものが、謎の絵師・東洲斎写楽の役者絵である。
これは今で言うタレントの写真集みたいなものである。
写楽の人物像は諸説あり、一説では蔦重本人だともいわれる。
蔦重に見出され世話になった絵師や文士は相当多い。
またこの時代に有名だった浮世絵師や文士の殆どが、
蔦重と何らかの関係をもっていたといわれる。
喜多川歌麿も蔦重に見出され世に出たし、
十返舎一九や曲亭馬琴も蔦重によって歴史に残った。
蔦重がいたからこそ、江戸の美術や文学が盛んになったともいえるのだ。
蔦重が偉大なのは彼が大衆の好みや嗜好の動きを敏感に察知し、
それを出版につなげていったことである。
今風にいうと市場調査(マーケット・リサーチ)がうまかったのだ。
さらに同時代の西洋との大きな違いは、
一般民衆が書物を購読できる知的レベルの高さと読書習慣の存在、
庶民レベルで絵画を売買する経済市場が出来上がっていたこと。
17~18世紀の江戸は世界でもトップの知的水準と都市機能をもっており、
江戸に匹敵するヨーロッパの都市はなかった。
ちなみにこの時代の江戸の識字率は70~80%もあり、
同時代のロンドンは20%、パリが10%だった。
この知的水準を広めたのが寺子屋と貸し本屋だった。
江戸の寺子屋は19世紀には1000件以上、
貸し本屋は700件もあったといわれる。
換言すると蔦重の出版業が流行ったのはこれらの知的土壌があり、
蔦重の出版がさらに町民の文化的欲求を高めたということでもある。
江戸時代の文化を概観すると、現代との差は殆どないことに気づく。
すでに江戸時代は近世ではなく、近代だったのだ。
ちなみに私は近世の意味を知らない。
Posted by トラネコ at 00:00│Comments(1)
│歴史
この記事へのコメント
他の記事は偏ってますねえ
Posted by とある at 2017年10月04日 23:40
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 |