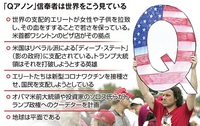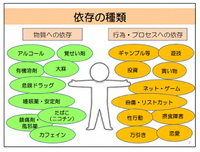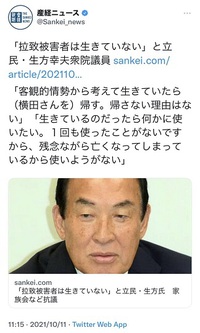神秘の珠「如意宝珠」
2008年12月08日
仏様の手の上の先のとがった珠を見かけることがある。
古い時代の橋の欄干にあるタマネギ型の擬宝珠(ぎぼし)と呼ばれる飾りも同じ。
また龍神がしっかり手に握っている玉もそうだ。
これらの珠を如意宝珠という。
サンスクリット語ではシッタ・マニあるいはチンタ・マニ (चिन्तामणि [cintaamaNi])、
マニ宝珠ともいう。チンタは「思惟、思考、思念」という意味であり、
マニとは「珠」という意味で、総じて「意の如くになる珠」という意味である
 この如意宝珠は古来インドより伝えられた仏教の秘宝である。秘宝といっても現実のものではなく、仏教哲学における象徴的な存在である。
この如意宝珠は古来インドより伝えられた仏教の秘宝である。秘宝といっても現実のものではなく、仏教哲学における象徴的な存在である。
如意宝珠は全ての海水と魚を呑み込んでしまうといわれるインドの伝説の怪魚「マカラ、摩竭魚(まかつぎょ)」の体内から取れる貴重な宝の珠といわれる。或いは龍神の脳から出たものともいわれる。
その無限の価値から仏や仏の教えの象徴とされ、地蔵菩薩や虚空蔵菩薩の持物とされ、仏様のなかで
コスモエナジーさんの如意宝珠
最も如意宝珠の霊験を象徴しているとされる仏様が
如意輪観音菩薩である。この如意輪観音の象徴(三昧耶)が如意宝珠である。
中央の手のひらの上にそれが見える。如意輪観音の働きは、六道の衆生の苦を取り去り、
俗世間の利益を与えることを本意とする。如意輪観音菩薩とはわれわれ衆生の全ての願いを叶える有り難い仏様である。

観心寺国宝「如意輪観音菩薩」
この如意宝珠の形を生涯研究していた市井の研究者がいた。
図形哲学研究者の福原肇氏である。
福原氏とは今から10年以上昔になると思うが、
東京の山手線の田端駅前の喫茶店でお会いした事がある。
今もお元気なのだろうか。
福原氏によると如意宝珠の形は世界中の建築物や、図形に見られる普遍性があるという。
如意宝珠の形は極大と極微、一点と全体など相反する矛盾を統合する形だそうだ。
宝珠を真上から見下ろすと、円の中央に点が来るように見える。
ちょうどコンパスの軸足のとがった針の穴を中心に円を描いたような形だ。
これは点と円が極微と極大(無限)を表し、それを横にしたときのタマネギ形が統合形だという。
水滴や炎の形も長めになるが、宝珠形である。
 考えてみると、自然界の果実や種の形にはこの宝珠形が非情に多いことに気がつく。たとえばドングリや栗の実、アーモンドや柿の種などはみな宝珠形である。中国で吉兆の果物とされる桃も宝珠形だ。おそらく桃は宝珠形だから縁起のよい吉兆を表す果物とされたのではないかと思う。
考えてみると、自然界の果実や種の形にはこの宝珠形が非情に多いことに気がつく。たとえばドングリや栗の実、アーモンドや柿の種などはみな宝珠形である。中国で吉兆の果物とされる桃も宝珠形だ。おそらく桃は宝珠形だから縁起のよい吉兆を表す果物とされたのではないかと思う。
古事記でイザナギの命が黄泉の国に妻のイザナミの命に会いに行き、その帰りに魔物に追いかけられるが、桃を投げて撃退する場面がある。あれも宝珠の霊力を象徴的に表した話ではないだろうか。
ムーンマッドネスさんの如意宝珠
また仏様は蓮の花の上にいる形式(蓮華台)のものが多いが、
蓮の花というのも実は意味があるのだ。
蓮は普通沼地に成長する植物である。
決して川などの流水には繁殖しない。
沼地は水底は泥でが堆積しており、そこにはバクテリアから
虫の仲間やそれを捕食するエビやゲンゴロウなどの肉食昆虫、
さらにそれらを食用とする魚まで、様々な生物が繁殖している。
いわば沼地は人間社会の縮図である。
そのドロドロした泥沼という社会で修行を積んで、
悟りをひらいた方が仏陀すなわち仏様なのだ。
蓮の花はその泥の中で栄養分を吸収して成長し、水面に出て花開くのだ。
これを修行して大悟した仏陀を象徴させて仏様の表現にダブらせているのだ。
そしてその開花前の蓮の花のつぼみも宝珠形である。



能満寺の虚空蔵菩薩
アンジェリックストーンさんの
ローズクォーツ宝珠
如意宝珠は精神的に不安定なときや、瞑想したりするときに、
お香などを焚いて静かに見つめると自然と心が安らいでくる。
実際に願い事が叶うか叶わないかはそれを信じる人の気持次第でどうにでもなるだろう。
この神秘の伝説の珠がただの石ころで終わるか、
素晴らしい無限のパワーを秘めた本物の如意の珠になるかは、
持つ人の心次第であるのは言うまでもない。
古い時代の橋の欄干にあるタマネギ型の擬宝珠(ぎぼし)と呼ばれる飾りも同じ。
また龍神がしっかり手に握っている玉もそうだ。
これらの珠を如意宝珠という。
サンスクリット語ではシッタ・マニあるいはチンタ・マニ (चिन्तामणि [cintaamaNi])、
マニ宝珠ともいう。チンタは「思惟、思考、思念」という意味であり、
マニとは「珠」という意味で、総じて「意の如くになる珠」という意味である
 この如意宝珠は古来インドより伝えられた仏教の秘宝である。秘宝といっても現実のものではなく、仏教哲学における象徴的な存在である。
この如意宝珠は古来インドより伝えられた仏教の秘宝である。秘宝といっても現実のものではなく、仏教哲学における象徴的な存在である。如意宝珠は全ての海水と魚を呑み込んでしまうといわれるインドの伝説の怪魚「マカラ、摩竭魚(まかつぎょ)」の体内から取れる貴重な宝の珠といわれる。或いは龍神の脳から出たものともいわれる。
その無限の価値から仏や仏の教えの象徴とされ、地蔵菩薩や虚空蔵菩薩の持物とされ、仏様のなかで
コスモエナジーさんの如意宝珠
最も如意宝珠の霊験を象徴しているとされる仏様が
如意輪観音菩薩である。この如意輪観音の象徴(三昧耶)が如意宝珠である。
中央の手のひらの上にそれが見える。如意輪観音の働きは、六道の衆生の苦を取り去り、
俗世間の利益を与えることを本意とする。如意輪観音菩薩とはわれわれ衆生の全ての願いを叶える有り難い仏様である。

観心寺国宝「如意輪観音菩薩」
この如意宝珠の形を生涯研究していた市井の研究者がいた。
図形哲学研究者の福原肇氏である。
福原氏とは今から10年以上昔になると思うが、
東京の山手線の田端駅前の喫茶店でお会いした事がある。
今もお元気なのだろうか。
福原氏によると如意宝珠の形は世界中の建築物や、図形に見られる普遍性があるという。
如意宝珠の形は極大と極微、一点と全体など相反する矛盾を統合する形だそうだ。
宝珠を真上から見下ろすと、円の中央に点が来るように見える。
ちょうどコンパスの軸足のとがった針の穴を中心に円を描いたような形だ。
これは点と円が極微と極大(無限)を表し、それを横にしたときのタマネギ形が統合形だという。
水滴や炎の形も長めになるが、宝珠形である。
 考えてみると、自然界の果実や種の形にはこの宝珠形が非情に多いことに気がつく。たとえばドングリや栗の実、アーモンドや柿の種などはみな宝珠形である。中国で吉兆の果物とされる桃も宝珠形だ。おそらく桃は宝珠形だから縁起のよい吉兆を表す果物とされたのではないかと思う。
考えてみると、自然界の果実や種の形にはこの宝珠形が非情に多いことに気がつく。たとえばドングリや栗の実、アーモンドや柿の種などはみな宝珠形である。中国で吉兆の果物とされる桃も宝珠形だ。おそらく桃は宝珠形だから縁起のよい吉兆を表す果物とされたのではないかと思う。古事記でイザナギの命が黄泉の国に妻のイザナミの命に会いに行き、その帰りに魔物に追いかけられるが、桃を投げて撃退する場面がある。あれも宝珠の霊力を象徴的に表した話ではないだろうか。
ムーンマッドネスさんの如意宝珠
また仏様は蓮の花の上にいる形式(蓮華台)のものが多いが、
蓮の花というのも実は意味があるのだ。
蓮は普通沼地に成長する植物である。
決して川などの流水には繁殖しない。
沼地は水底は泥でが堆積しており、そこにはバクテリアから
虫の仲間やそれを捕食するエビやゲンゴロウなどの肉食昆虫、
さらにそれらを食用とする魚まで、様々な生物が繁殖している。
いわば沼地は人間社会の縮図である。
そのドロドロした泥沼という社会で修行を積んで、
悟りをひらいた方が仏陀すなわち仏様なのだ。
蓮の花はその泥の中で栄養分を吸収して成長し、水面に出て花開くのだ。
これを修行して大悟した仏陀を象徴させて仏様の表現にダブらせているのだ。
そしてその開花前の蓮の花のつぼみも宝珠形である。



能満寺の虚空蔵菩薩
アンジェリックストーンさんの
ローズクォーツ宝珠
如意宝珠は精神的に不安定なときや、瞑想したりするときに、
お香などを焚いて静かに見つめると自然と心が安らいでくる。
実際に願い事が叶うか叶わないかはそれを信じる人の気持次第でどうにでもなるだろう。
この神秘の伝説の珠がただの石ころで終わるか、
素晴らしい無限のパワーを秘めた本物の如意の珠になるかは、
持つ人の心次第であるのは言うまでもない。
Posted by トラネコ at 06:00│Comments(2)
│思想・宗教
この記事へのコメント
トラネコ先生、こんにちは。
またお邪魔させてください。
とても興味深いお話でした。
私は京都府宇治市という
ある意味とても恵まれた環境で
育ちながら、その価値を
理解することなく大きくなり
今に至っております。
平等院へむかう途中にある
宇治橋にも
この「如意宝珠」の造型が
あったことを思い出しました。
またお邪魔させてください。
とても興味深いお話でした。
私は京都府宇治市という
ある意味とても恵まれた環境で
育ちながら、その価値を
理解することなく大きくなり
今に至っております。
平等院へむかう途中にある
宇治橋にも
この「如意宝珠」の造型が
あったことを思い出しました。
Posted by 三時の母 at 2008年12月08日 16:03
三時の母様
コメントどうも!
そうですか、京都の宇治のご出身でしたか。
ええとこにお住まいどしたなあ(笑)
実は私は大昔京都で着物の染織職人をしていました。
美術の基礎勉強も京都でおこないました。
また行ってみたいですね。
コメントどうも!
そうですか、京都の宇治のご出身でしたか。
ええとこにお住まいどしたなあ(笑)
実は私は大昔京都で着物の染織職人をしていました。
美術の基礎勉強も京都でおこないました。
また行ってみたいですね。
Posted by トラネコ at 2008年12月08日 20:23
at 2008年12月08日 20:23
 at 2008年12月08日 20:23
at 2008年12月08日 20:23