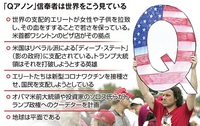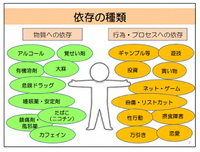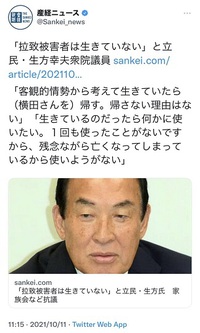宗教雑感・「無神論者は疑われやすい」? その1
2017年08月14日
無神論者は疑われやすい、同じ無神論者ですら偏見 研究
【8月8日 AFP】無神論者は、キリスト教やイスラム教、ヒンズー教、仏教などを信仰する人々よりも悪行に対する嫌疑をかけられやすいとする一風変わった社会調査の結果が7日、発表された。
英科学誌「ネイチャー・ヒューマン・ビヘイビア(Nature Human Behaviour)」に掲載された論文によると、この研究では、世界5大陸13か国の3000人以上を対象に意識調査を実施。
対象国は、中国やオランダなど「非常に世俗的」な国々から、アラブ首長国連邦(UAE)や米国、インドなど信仰を持つ人々が多数を占める国々まで幅広く選択された。
これらの国々では、国民の大部分が仏教、キリスト教、ヒンズー教、イスラム教などの信者であるか、あるいは無神論者だった。
調査では、最初に対象者に対し架空の人物についての描写を行った。
この人物は幼少期に動物を虐待し、成人して教師になった後、ホームレス5人を殺害し、遺体を切断したという設定だった。
その後、対象者の半数に対し、この人物が宗教を信仰していた可能性の有無を尋ね、さらに別の半数に対しては、無神論者であった可能性の有無を尋ねた。
■無神論者も無神論者に偏見
調査の結果、この連続殺人犯を無神論者とみなした人々は、そうでない人々の約2倍に上った。
論文の共同執筆者、米ケンタッキー大学(University of Kentucky)のウィル・ジェルベー(Will Gervais)教授(心理学)はAFPに対し、「無神論者でさえ、直感的に無神論者に対する偏見を持っているらしいというのは印象的だ」と語る。
同氏は、「これが信仰を擁護する昔ながらの規範が根強く残っていることから生じるとみることには懐疑的だ。公然と世俗主義を掲げている地域であっても、人々は今も宗教は倫理的なセーフガードとの信念を直感的に持ち続けているようだ」と説明している。(c)AFP
AFP 2017年08月08日
http://www.afpbb.com/articles/-/3138491?act=all

無神論者と考えられる人々の国別分布
http://livedoor.4.blogimg.jp/karapaia_zaeega/imgs/8/2/827b753a.jpg
>「無神論者でさえ、直感的に無神論者に対する
偏見を持っているらしいというのは印象的だ」
一種の思い込みだな。
宗教や神の存在を信じている人は不道徳な行為や犯罪はしないだろう、
或いは、そんな事するはずがないだろうと、思いたいのだろうと思う。
つまり、希望的かつ願望的な思い込みである。
また一神教文明圏では、宗教が道徳教育の規範になっているから、
無神論者は道徳性のない非常識で犯罪に親和性のある人格だとみられる。
だから読者諸氏も海外に行ったときには無神論者と言わない方がいい。
この辺は、日本人の宗教観や道徳観と大きく異なる。
上に貼った図ではシナと日本が無神論者の国とされている。
実際に日本人でも自分は無神論者だと思っている人は少なくない。
日本人の規定する無神論者は特定の宗教を信じていないとか、
どこかの宗教団体に所属していないから無神論者だと思っていないだろうか。
もちろんシナは共産主義国家で拝金主義だからわかるが、日本は事情が違う。
確かに我々一般の日本人は日常的に、宗教や神様を考えて生活していないし、
毎日聖書や仏典読む人はいないが、他民族に比べ道徳性も高く異教徒にも寛大だ。
それでも日本人は決して無神論者ではないのである。

日本人はこんな事「全能の神」に教えて貰わなくても皆知っているw
よく言われるように、元日には神社参り、お盆には墓参り、クリスマス・・・
まあこれが生活習慣の一部であるが、無神論者はそんなことしない。
熱心な宗教心ではないが、決して無神論者ではないのだ。
日本人は無宗教のようでも信仰心も道徳性もある民族だ。
というか、日本人は宗教から道徳観念を形成されているのではない。
自然崇拝と村落共同体の中から自主的に道徳観が形成されたのだ。
国土の7割が山と森林の、しかも周囲が海で移動できない島国で、
明瞭な四季の変化、自然災害の多さ、多民族の雑居、村落型生活・・・
といった日本列島の自然風土と日本民族の形成過程から、
共同体社会の秩序を否が応でも作らざるを得なかったのだと思う。
さらに自然崇拝は神道に発展し日本人の不文律の道徳概念になり、
共同体、相互扶助、自然保護などの道徳概念になる基本が形成された。
その後、その道徳的抽象概念が体系化されたのは儒教思想である。

日本人の年中行事や習慣は神道・仏教・儒教の混合である。
日本人の道徳の体系化の最初は、神代の応神天皇の頃、
百済から日本の移入されたとされる「論語」に依るとされる。
これから天皇の理想的治世も徳治主義とされ、9世紀の清和天皇以降、
天皇の名前に「仁」の字を当てたのもそれに依ると言われる。
そして平安後期から鎌倉時代に武家政権の時代が江戸時代まで、
約400年間続くことで、武家社会による道徳性の体系化が進み、
その一つが御成敗式目となり、社会規範の基本になっていく。
これがのちの武士道や石門心学に発展していくのである。
明治以降の修身教育も江戸時代に発達した朱子学なども含まれている。
儒教は日本人の道徳としてしっかり根付いている事がわかる。
この点が聖書を座右の書とし、毎週日曜日には教会に通い、或いは、
ハラール食をこだわり、一日5回メッカに向かって祈りを捧げる一神教では、
絶対的な「神」の権威に精神的依存をする「畏れ」による道徳観であると思う。

日本初の武士の法律書「御成敗式目」

武士道も日本人の道徳精神の基層を形成している。
そこで私が前から疑問だったのが・・・
ルース・ベネディクトの「菊と刀」のいう、日本人の「恥」の文化論には異論がある。
日本人の道徳性を他人や社会の目を気にする「恥」の文化だとする点である。
「恥」に対応する社会とは先祖から受け継いだ日本という精神風土を指している、
と私は見る。
これをR.ベネディクトは他律的な「恥の文化」という没主体性の道徳心規定し、
西欧キリスト教文化圏は原罪に基づく自律的な「罪の文化」と規定した。
しかし私は西欧文明の道徳観こそ「神の畏れ」からくる他律的文化ではないかと考える。
誤解を恐れずに言えば・・・
一神教文化圏の人々の精神性は、宗教依存症であると思う。
絶対的権威の「神」依存症と言ってもよいくらい自立していないと思う。
自立しているかのように見えて実は、背後に「神の支え」があるのである。

マルチン・ルターの宗教改革以降、権威的な仲介者である教会を排除し
神と人間の直接的契約関係が成立して以来、絶対的権威の神のしもべとして、
人間は教義=神の教えに忠実にあろうとして、常に「神」を意識しており、
「神=契約者」に背かない行動を心がける事が自律的と言えるだろうか?
さらにルターの信仰義認説にも顕著な絶対的な「神」への信仰があり、
救いは善行を積む事によってではなく、神へのひたすらな信仰心で成就するのだという。
つまり神への絶対的かつ盲目的信仰こそ魂の救済だというのである。
その実践として戒律や教義があり、それに疑問を持つことなしに忠実に信じ、
実践することが信仰の度合いというか、神への忠誠度を測る尺度になっている。
これが異教徒を憎悪し虐殺することに抵抗感を喪失させる「権威」の証で、
キリスト教の歴史、現在のイスラム原理主義者の行動でも推察できるだろう。
これのどこに自律的文化があるのだろうか?

一方神道を宗教と定義するかどうかにもよるが・・・
日本人には絶対的権威を持った唯一神」という存在も概念もない。
悪戯もすれば、怒りもするが、幸福も与え守ってくれる八百万の神々がいるだけだ。
一神教ほどド偉い神様はいないが、暮らしている世界すべてが神が充満した世界だ。
さらに教祖もなく、教義(ドグマ)も教団さえも存在しない。
戒律もないから、神の怒りを恐れることもないから、共同体において、
個々の公的行動規範としての道徳は自律的であらねばならないのだ。
事実、地域の神社の祭礼や維持運営も、氏子と呼ばれる自治組織が担い、
共同体の始まりから自主的に行い、これで共同体の秩序も維持されている。
今風にいえば神社はボランティアによって支えられてきたのである。
我々が自然の一部を構成し、死ねば人もまた神である世界の一員としての、
当然の義務として社会秩序を守ろうとする感覚の方が、近代的な社会性があり、
むしろ日本人の自然の摂理を基本にした道徳観の方が自律的ではないだろうか?
日本人は一神教みたいな絶対的な権威を持った神の教え=教義(ドグマ)に、
盲目的にひれ伏す信仰は嫌いなのだと思う。無論どこにでも盲目的信者はいるが、
日本で一神教が広まらない理由の一つにはこれがあるのではないだろうか?
ま、あくまで私見であるが・・・。

戒律の厳しいドグマティック宗教ほど
他律的で歪んだ解釈になりやすい。
そこで日本人の精神文化の基盤を考えると・・・
日本人精神の基盤は神道・仏教・儒教の混合体である。
しかもこれらは一つの思想とか宗教という、個別的分類やとらえ方をせずに、
時代と共に体系化されつつ無意識に日本人の精神性に根付いているのである。
言い換えれば・・・
これらの宗教・思想は日本人の生活感と一体化し、精神風土と化し
日本人の精神と不可分の存在になっているが故に意識されないのだ。
つまり一神教では「絶対神」と人間は常に対立関係にある事に対し、
日本人の信仰は「神々」と一体化し無意識化しているという事である。

ところで・・・
儒教は2500年前の孔子の教えだが、
本家のシナには欠片すら残っていない(笑)

最近になってシナ共産党は孔子学院とか孔子平和賞とか、
孔子の名前を利用しているが、その精神は皆無であるw
またどこぞの捏造民族が「孔子はウリナラ人ニダ~」と・・・
明日へつづく・・・

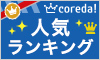

【8月8日 AFP】無神論者は、キリスト教やイスラム教、ヒンズー教、仏教などを信仰する人々よりも悪行に対する嫌疑をかけられやすいとする一風変わった社会調査の結果が7日、発表された。
英科学誌「ネイチャー・ヒューマン・ビヘイビア(Nature Human Behaviour)」に掲載された論文によると、この研究では、世界5大陸13か国の3000人以上を対象に意識調査を実施。
対象国は、中国やオランダなど「非常に世俗的」な国々から、アラブ首長国連邦(UAE)や米国、インドなど信仰を持つ人々が多数を占める国々まで幅広く選択された。
これらの国々では、国民の大部分が仏教、キリスト教、ヒンズー教、イスラム教などの信者であるか、あるいは無神論者だった。
調査では、最初に対象者に対し架空の人物についての描写を行った。
この人物は幼少期に動物を虐待し、成人して教師になった後、ホームレス5人を殺害し、遺体を切断したという設定だった。
その後、対象者の半数に対し、この人物が宗教を信仰していた可能性の有無を尋ね、さらに別の半数に対しては、無神論者であった可能性の有無を尋ねた。
■無神論者も無神論者に偏見
調査の結果、この連続殺人犯を無神論者とみなした人々は、そうでない人々の約2倍に上った。
論文の共同執筆者、米ケンタッキー大学(University of Kentucky)のウィル・ジェルベー(Will Gervais)教授(心理学)はAFPに対し、「無神論者でさえ、直感的に無神論者に対する偏見を持っているらしいというのは印象的だ」と語る。
同氏は、「これが信仰を擁護する昔ながらの規範が根強く残っていることから生じるとみることには懐疑的だ。公然と世俗主義を掲げている地域であっても、人々は今も宗教は倫理的なセーフガードとの信念を直感的に持ち続けているようだ」と説明している。(c)AFP
AFP 2017年08月08日
http://www.afpbb.com/articles/-/3138491?act=all

無神論者と考えられる人々の国別分布
http://livedoor.4.blogimg.jp/karapaia_zaeega/imgs/8/2/827b753a.jpg
>「無神論者でさえ、直感的に無神論者に対する
偏見を持っているらしいというのは印象的だ」
一種の思い込みだな。
宗教や神の存在を信じている人は不道徳な行為や犯罪はしないだろう、
或いは、そんな事するはずがないだろうと、思いたいのだろうと思う。
つまり、希望的かつ願望的な思い込みである。
また一神教文明圏では、宗教が道徳教育の規範になっているから、
無神論者は道徳性のない非常識で犯罪に親和性のある人格だとみられる。
だから読者諸氏も海外に行ったときには無神論者と言わない方がいい。
この辺は、日本人の宗教観や道徳観と大きく異なる。
上に貼った図ではシナと日本が無神論者の国とされている。
実際に日本人でも自分は無神論者だと思っている人は少なくない。
日本人の規定する無神論者は特定の宗教を信じていないとか、
どこかの宗教団体に所属していないから無神論者だと思っていないだろうか。
もちろんシナは共産主義国家で拝金主義だからわかるが、日本は事情が違う。
確かに我々一般の日本人は日常的に、宗教や神様を考えて生活していないし、
毎日聖書や仏典読む人はいないが、他民族に比べ道徳性も高く異教徒にも寛大だ。
それでも日本人は決して無神論者ではないのである。

日本人はこんな事「全能の神」に教えて貰わなくても皆知っているw
よく言われるように、元日には神社参り、お盆には墓参り、クリスマス・・・
まあこれが生活習慣の一部であるが、無神論者はそんなことしない。
熱心な宗教心ではないが、決して無神論者ではないのだ。
日本人は無宗教のようでも信仰心も道徳性もある民族だ。
というか、日本人は宗教から道徳観念を形成されているのではない。
自然崇拝と村落共同体の中から自主的に道徳観が形成されたのだ。
国土の7割が山と森林の、しかも周囲が海で移動できない島国で、
明瞭な四季の変化、自然災害の多さ、多民族の雑居、村落型生活・・・
といった日本列島の自然風土と日本民族の形成過程から、
共同体社会の秩序を否が応でも作らざるを得なかったのだと思う。
さらに自然崇拝は神道に発展し日本人の不文律の道徳概念になり、
共同体、相互扶助、自然保護などの道徳概念になる基本が形成された。
その後、その道徳的抽象概念が体系化されたのは儒教思想である。

日本人の年中行事や習慣は神道・仏教・儒教の混合である。
日本人の道徳の体系化の最初は、神代の応神天皇の頃、
百済から日本の移入されたとされる「論語」に依るとされる。
これから天皇の理想的治世も徳治主義とされ、9世紀の清和天皇以降、
天皇の名前に「仁」の字を当てたのもそれに依ると言われる。
そして平安後期から鎌倉時代に武家政権の時代が江戸時代まで、
約400年間続くことで、武家社会による道徳性の体系化が進み、
その一つが御成敗式目となり、社会規範の基本になっていく。
これがのちの武士道や石門心学に発展していくのである。
明治以降の修身教育も江戸時代に発達した朱子学なども含まれている。
儒教は日本人の道徳としてしっかり根付いている事がわかる。
この点が聖書を座右の書とし、毎週日曜日には教会に通い、或いは、
ハラール食をこだわり、一日5回メッカに向かって祈りを捧げる一神教では、
絶対的な「神」の権威に精神的依存をする「畏れ」による道徳観であると思う。

日本初の武士の法律書「御成敗式目」

武士道も日本人の道徳精神の基層を形成している。
そこで私が前から疑問だったのが・・・
ルース・ベネディクトの「菊と刀」のいう、日本人の「恥」の文化論には異論がある。
日本人の道徳性を他人や社会の目を気にする「恥」の文化だとする点である。
「恥」に対応する社会とは先祖から受け継いだ日本という精神風土を指している、
と私は見る。
これをR.ベネディクトは他律的な「恥の文化」という没主体性の道徳心規定し、
西欧キリスト教文化圏は原罪に基づく自律的な「罪の文化」と規定した。
しかし私は西欧文明の道徳観こそ「神の畏れ」からくる他律的文化ではないかと考える。
誤解を恐れずに言えば・・・
一神教文化圏の人々の精神性は、宗教依存症であると思う。
絶対的権威の「神」依存症と言ってもよいくらい自立していないと思う。
自立しているかのように見えて実は、背後に「神の支え」があるのである。

マルチン・ルターの宗教改革以降、権威的な仲介者である教会を排除し
神と人間の直接的契約関係が成立して以来、絶対的権威の神のしもべとして、
人間は教義=神の教えに忠実にあろうとして、常に「神」を意識しており、
「神=契約者」に背かない行動を心がける事が自律的と言えるだろうか?
さらにルターの信仰義認説にも顕著な絶対的な「神」への信仰があり、
救いは善行を積む事によってではなく、神へのひたすらな信仰心で成就するのだという。
つまり神への絶対的かつ盲目的信仰こそ魂の救済だというのである。
その実践として戒律や教義があり、それに疑問を持つことなしに忠実に信じ、
実践することが信仰の度合いというか、神への忠誠度を測る尺度になっている。
これが異教徒を憎悪し虐殺することに抵抗感を喪失させる「権威」の証で、
キリスト教の歴史、現在のイスラム原理主義者の行動でも推察できるだろう。
これのどこに自律的文化があるのだろうか?

一方神道を宗教と定義するかどうかにもよるが・・・
日本人には絶対的権威を持った唯一神」という存在も概念もない。
悪戯もすれば、怒りもするが、幸福も与え守ってくれる八百万の神々がいるだけだ。
一神教ほどド偉い神様はいないが、暮らしている世界すべてが神が充満した世界だ。
さらに教祖もなく、教義(ドグマ)も教団さえも存在しない。
戒律もないから、神の怒りを恐れることもないから、共同体において、
個々の公的行動規範としての道徳は自律的であらねばならないのだ。
事実、地域の神社の祭礼や維持運営も、氏子と呼ばれる自治組織が担い、
共同体の始まりから自主的に行い、これで共同体の秩序も維持されている。
今風にいえば神社はボランティアによって支えられてきたのである。
我々が自然の一部を構成し、死ねば人もまた神である世界の一員としての、
当然の義務として社会秩序を守ろうとする感覚の方が、近代的な社会性があり、
むしろ日本人の自然の摂理を基本にした道徳観の方が自律的ではないだろうか?
日本人は一神教みたいな絶対的な権威を持った神の教え=教義(ドグマ)に、
盲目的にひれ伏す信仰は嫌いなのだと思う。無論どこにでも盲目的信者はいるが、
日本で一神教が広まらない理由の一つにはこれがあるのではないだろうか?
ま、あくまで私見であるが・・・。

戒律の厳しいドグマティック宗教ほど
他律的で歪んだ解釈になりやすい。
そこで日本人の精神文化の基盤を考えると・・・
日本人精神の基盤は神道・仏教・儒教の混合体である。
しかもこれらは一つの思想とか宗教という、個別的分類やとらえ方をせずに、
時代と共に体系化されつつ無意識に日本人の精神性に根付いているのである。
言い換えれば・・・
これらの宗教・思想は日本人の生活感と一体化し、精神風土と化し
日本人の精神と不可分の存在になっているが故に意識されないのだ。
つまり一神教では「絶対神」と人間は常に対立関係にある事に対し、
日本人の信仰は「神々」と一体化し無意識化しているという事である。

ところで・・・
儒教は2500年前の孔子の教えだが、
本家のシナには欠片すら残っていない(笑)

最近になってシナ共産党は孔子学院とか孔子平和賞とか、
孔子の名前を利用しているが、その精神は皆無であるw
またどこぞの捏造民族が「孔子はウリナラ人ニダ~」と・・・
明日へつづく・・・

Posted by トラネコ at 04:00│Comments(14)
│思想・宗教
この記事へのコメント
トラネコさん、
面白いですね!!!
明日も楽しみにしております。
私のFBグループ『憂国のメキシカンカトリック、パウロ伊藤の独り言』にシェアさせて頂きます。
頑張ってください!
在メキシコ パウロ伊藤
面白いですね!!!
明日も楽しみにしております。
私のFBグループ『憂国のメキシカンカトリック、パウロ伊藤の独り言』にシェアさせて頂きます。
頑張ってください!
在メキシコ パウロ伊藤
Posted by パウロ伊藤 at 2017年08月14日 06:23
パウロ伊藤様
ありがとうございます。
実はこのエントリは先週から書いていたのですが、まとまらずに加除訂正を繰り返すうちに文量が多くなって二回に分けることにしました。まあ雑文ですからお気楽にお読みくださいませ。
ありがとうございます。
実はこのエントリは先週から書いていたのですが、まとまらずに加除訂正を繰り返すうちに文量が多くなって二回に分けることにしました。まあ雑文ですからお気楽にお読みくださいませ。
Posted by トラネコ at 2017年08月14日 08:11
毎度ですが大変勉強になります
過去の関連ブログ 日本でイスラム教的習慣が根付かないこと等 も読んでみましたよ
日本人は圧倒的に無神論者が多いと私自身思っていましたが 実はこんなに奥深い基盤(八百万の神)があるとは・・・
その2も楽しみにしております
過去の関連ブログ 日本でイスラム教的習慣が根付かないこと等 も読んでみましたよ
日本人は圧倒的に無神論者が多いと私自身思っていましたが 実はこんなに奥深い基盤(八百万の神)があるとは・・・
その2も楽しみにしております
Posted by ガトー at 2017年08月14日 10:34
ガトー様
恐縮でございます。
私は日本人の信仰態度というものがこれからの世界的な潮流になればいいと思っています。神道の無教祖・無教義・無組織こそ、信仰を個人的なものにとどめ、政治や経済に利用されない心の平安だけの支柱になれば、戦いもなくなり自然を大切にするのではないかと、まあ甘いですが思っています。
恐縮でございます。
私は日本人の信仰態度というものがこれからの世界的な潮流になればいいと思っています。神道の無教祖・無教義・無組織こそ、信仰を個人的なものにとどめ、政治や経済に利用されない心の平安だけの支柱になれば、戦いもなくなり自然を大切にするのではないかと、まあ甘いですが思っています。
Posted by トラネコ at 2017年08月14日 13:41
シナ朝鮮は上下関係がはっきりしている儒教社会とされていますが、日本人は儒教(孟子孔子老子)を道徳として学校で習ってはいるものの、日本社会は全然儒教社会ではないと思います。 むしろ、和を重視する平等社会です。 それに対して、シナ朝鮮では奴隷制度がまかり通っていました。
歴史的にみても、日本の江戸時代までの身分制度は職業制度とみなすべきです。 実際のところ、一般の武士よりも商人が豊かで、下級武士の家計は米以外の野菜や魚は自給自足でした。 部落も汚れ仕事を行う職業村だったのでしょう。( 部落の身分差別を強調しているのは、在日や外国人。)
歴史的にみても、日本の江戸時代までの身分制度は職業制度とみなすべきです。 実際のところ、一般の武士よりも商人が豊かで、下級武士の家計は米以外の野菜や魚は自給自足でした。 部落も汚れ仕事を行う職業村だったのでしょう。( 部落の身分差別を強調しているのは、在日や外国人。)
Posted by Black Joker at 2017年08月14日 13:41
Black Joker 様
同意です。
日本人の道徳観念の基層をなすのは、神道・儒教・仏教の融合体ではないかと思います。道徳というか宗教心と言うか、文化感覚と言うか、この辺はハッキリ言えませんが、これらの精神風土も日本人や日本語と同じく複数の要素の融合体であると思います。
江戸時代の身分制度は一説よれば、儒学者藤原惺窩が彼の憧れていた儒教国家・朝鮮の身分制度を参考に家康に助言したものだとか・・・
同意です。
日本人の道徳観念の基層をなすのは、神道・儒教・仏教の融合体ではないかと思います。道徳というか宗教心と言うか、文化感覚と言うか、この辺はハッキリ言えませんが、これらの精神風土も日本人や日本語と同じく複数の要素の融合体であると思います。
江戸時代の身分制度は一説よれば、儒学者藤原惺窩が彼の憧れていた儒教国家・朝鮮の身分制度を参考に家康に助言したものだとか・・・
Posted by トラネコ at 2017年08月14日 13:45
>一種の思い込みだな
日本人を無神論者と決めつけるのは一神教に被れているシロケダモノの思い込み、と言うよりは悪意に満ちた偏見でしょう。自分の信じる宗教を信じない連中は野蛮だ、とも言いたげな、実に短絡的な価値観だと思います。そもそも彼らの間でも「無神論って何だ?」みたいに、確固たる概念は確立されてないのでしょう。他文化の価値観からすれば無節操に見えるかもしれませんが、もし日本人が無神論者ならお宮参りや七夕など「自然のお祭り」を年中行事の如く行うはずはありません。結局は価値観の違いなので一神教と多神教は相容れないし、神道=宗教と言う図式が成り立つのかも半永久的に結論は出ないでしょう。
それは無神論の定義も同様なので、やはり海外で迂闊に「私は無神論者です」と公言しない方がいいでしょう。
日本人を無神論者と決めつけるのは一神教に被れているシロケダモノの思い込み、と言うよりは悪意に満ちた偏見でしょう。自分の信じる宗教を信じない連中は野蛮だ、とも言いたげな、実に短絡的な価値観だと思います。そもそも彼らの間でも「無神論って何だ?」みたいに、確固たる概念は確立されてないのでしょう。他文化の価値観からすれば無節操に見えるかもしれませんが、もし日本人が無神論者ならお宮参りや七夕など「自然のお祭り」を年中行事の如く行うはずはありません。結局は価値観の違いなので一神教と多神教は相容れないし、神道=宗教と言う図式が成り立つのかも半永久的に結論は出ないでしょう。
それは無神論の定義も同様なので、やはり海外で迂闊に「私は無神論者です」と公言しない方がいいでしょう。
Posted by KOBA at 2017年08月14日 21:04
KOBA様
同意です。
無神論者とは何か?
いろんな考え方や定義の仕方があるのだと思いますが、ひとつの目安としてですが、例えば神社仏閣内で立ち小便ができるか? 墓石やお地蔵さんに同じことができるか? 日本人に関してですがこれって一つの目安になりませんか?
私はもちろんできません。
例えキリスト教やイスラム教の教会域内や、その他の宗教の聖域と言われる場所でもできませんね。もっとも仏像を平気で破壊する朝鮮人や、一神教の人間はできるかも知れませんが、普通の日本人は抵抗あるんじゃないでしょうか?
同意です。
無神論者とは何か?
いろんな考え方や定義の仕方があるのだと思いますが、ひとつの目安としてですが、例えば神社仏閣内で立ち小便ができるか? 墓石やお地蔵さんに同じことができるか? 日本人に関してですがこれって一つの目安になりませんか?
私はもちろんできません。
例えキリスト教やイスラム教の教会域内や、その他の宗教の聖域と言われる場所でもできませんね。もっとも仏像を平気で破壊する朝鮮人や、一神教の人間はできるかも知れませんが、普通の日本人は抵抗あるんじゃないでしょうか?
Posted by トラネコ at 2017年08月15日 07:01
at 2017年08月15日 07:01
 at 2017年08月15日 07:01
at 2017年08月15日 07:01「一神教では「絶対神」と人間は常に対立関係にある事に対し、日本人の信仰は「神々」と一体化し無意識化しているという事である」なるほど、そうですよねぇ。しかし「絶対神」が全てを支配しているという考え方は、現実がそれにそぐわない場合矛盾が必ず出てきますし、無理に教義に当て嵌めようと現実を歪めてしまう恐れがありますね。
教義などはなくても全てをありのままに受け入れる日本人の信仰はなんと寛大なのでしょう?
教義などはなくても全てをありのままに受け入れる日本人の信仰はなんと寛大なのでしょう?
Posted by kabu at 2017年08月15日 09:30
kabu様
一神教の特徴として挙げていますが教義=ドグマへの忠実な履行(契約)を信者に要求されることが、かなり信仰の負担になるのではないかと思います。しかも神の教えには絶対服従であり、背けば「罰」も用意されている。
反対に多神教である神道は教義も教祖もないから気楽です。
しかしそれだけに自立した言動と規範を身につけないと共同体の生活はできません。つまり教祖も教義もないからこそ、主体的に人間性の進化を行えるのだと私は思いますね。だから安土桃山時代に来日した宣教師が一般民衆の民度の高さに驚き、日本布教のために科学者を本国に要請したと言います。今この辺の宗教論を文章化しスペイン後に翻訳していますが、結構難しいですね・・・
一神教の特徴として挙げていますが教義=ドグマへの忠実な履行(契約)を信者に要求されることが、かなり信仰の負担になるのではないかと思います。しかも神の教えには絶対服従であり、背けば「罰」も用意されている。
反対に多神教である神道は教義も教祖もないから気楽です。
しかしそれだけに自立した言動と規範を身につけないと共同体の生活はできません。つまり教祖も教義もないからこそ、主体的に人間性の進化を行えるのだと私は思いますね。だから安土桃山時代に来日した宣教師が一般民衆の民度の高さに驚き、日本布教のために科学者を本国に要請したと言います。今この辺の宗教論を文章化しスペイン後に翻訳していますが、結構難しいですね・・・
Posted by トラネコ at 2017年08月15日 11:31
at 2017年08月15日 11:31
 at 2017年08月15日 11:31
at 2017年08月15日 11:31外国人の宗教云々って、ユダヤ教みたいに、勉強のために日常から食べ物まで決めるのもあれば、敢えて仏教を「日本教」と言いますが、うまく利用するものまで出てきてるので、色々なんだと思います。
> 日本初の法律書「御成敗式目」
その前に色々出てて、大宝律令とか、養老律令とかあるんすが…これは、一応17条憲法の三倍の51カ条から構成されてて、前から存在する公家法、本所法(荘園関係)があって、それに並ぶ武家の法令ですから、最初ってのは違うと思います。
>一神教文化圏の人々の精神性は、宗教依存症であると思う。
彼奴等の普段の行動がすでに依存してる感じですもんね。oh my god とか連発するやつなんなんだって思うことあります。
ルターがあそこまでできたのて、ザクセン選帝侯フリードリヒ世といい関係だったからでしょうね。誘拐に見せかけてかくまってもらったり、皇帝カール五世からすりゃ恩人だし、ローマ教皇もハプスブルク家と対抗するためには必要だったみたいですから、うまくやったと思ってます。
>儒教は2500年前の孔子の教えだが、本家のシナには欠片すら残っていない(笑)
しっかり残ってますよ。残ってなきゃ共産党に序列なんて存在しませんし、人間を上下でしか見られないなんて、まんま儒教ですよ。
それに儒教が成立した春秋時代の魯なんてのはいつも混乱だらけの、周辺騎馬民族には脅されるわで、ハッキリ言って弱者の慰みでしかありません。あんなものがあるから、いじめは無くならない、嫉妬深くなる、官僚制度も抜擢人事が出来ないっていう弊害もありますし、今の時代だって、企業によっては上司よりいい車に乗ってはいけないっていう下らない規則作ってる会社あるでしょ。あれなんてまんま長幼の序ですよ。
私の勤めてるところが、上司よりいい車に乗ってはいけないなんて規則あったら、ソッコー反乱起こして、力づくで規則作ったやつ追放し、それがワンマン社長が作ったものなら、思いっきり無視するか、腕力で追放しますよ。経済は儒教で命令できるものではありませんからね。
> 日本初の法律書「御成敗式目」
その前に色々出てて、大宝律令とか、養老律令とかあるんすが…これは、一応17条憲法の三倍の51カ条から構成されてて、前から存在する公家法、本所法(荘園関係)があって、それに並ぶ武家の法令ですから、最初ってのは違うと思います。
>一神教文化圏の人々の精神性は、宗教依存症であると思う。
彼奴等の普段の行動がすでに依存してる感じですもんね。oh my god とか連発するやつなんなんだって思うことあります。
ルターがあそこまでできたのて、ザクセン選帝侯フリードリヒ世といい関係だったからでしょうね。誘拐に見せかけてかくまってもらったり、皇帝カール五世からすりゃ恩人だし、ローマ教皇もハプスブルク家と対抗するためには必要だったみたいですから、うまくやったと思ってます。
>儒教は2500年前の孔子の教えだが、本家のシナには欠片すら残っていない(笑)
しっかり残ってますよ。残ってなきゃ共産党に序列なんて存在しませんし、人間を上下でしか見られないなんて、まんま儒教ですよ。
それに儒教が成立した春秋時代の魯なんてのはいつも混乱だらけの、周辺騎馬民族には脅されるわで、ハッキリ言って弱者の慰みでしかありません。あんなものがあるから、いじめは無くならない、嫉妬深くなる、官僚制度も抜擢人事が出来ないっていう弊害もありますし、今の時代だって、企業によっては上司よりいい車に乗ってはいけないっていう下らない規則作ってる会社あるでしょ。あれなんてまんま長幼の序ですよ。
私の勤めてるところが、上司よりいい車に乗ってはいけないなんて規則あったら、ソッコー反乱起こして、力づくで規則作ったやつ追放し、それがワンマン社長が作ったものなら、思いっきり無視するか、腕力で追放しますよ。経済は儒教で命令できるものではありませんからね。
Posted by やま at 2017年08月16日 19:16
やま様
同意です。
御成敗式目は武士政権初の法律書ということでした、お詫びして訂正させていただきます。
儒教に関することですが、私の言いたかったのは道徳性に関してでした。
日本は儒教の教えから道徳が体系化されてそれが武士道や教育勅語などに発展しましたが、その点シナは何も引き継がれなかったという事です。ただ「長幼の序」というのは儒教ですが、「序列」、「上下関係」そのものは古今東西どこでもある社会秩序ではないでしょうか?
同意です。
御成敗式目は武士政権初の法律書ということでした、お詫びして訂正させていただきます。
儒教に関することですが、私の言いたかったのは道徳性に関してでした。
日本は儒教の教えから道徳が体系化されてそれが武士道や教育勅語などに発展しましたが、その点シナは何も引き継がれなかったという事です。ただ「長幼の序」というのは儒教ですが、「序列」、「上下関係」そのものは古今東西どこでもある社会秩序ではないでしょうか?
Posted by トラネコ at 2017年08月17日 00:06
at 2017年08月17日 00:06
 at 2017年08月17日 00:06
at 2017年08月17日 00:06上下関係ってだけで徳目として持ち込まれてるのが、そもそも若い芽を摘んだりする弊害もあるかと思います。
長幼の序とか上下関係も、やっぱり程度にもよりますし、武士道って言っても、中世は内ゲバや内乱、下剋上なんてのが結構ありましたし、江戸時代までの戦い方って、嘘もつき放題、乱取りっていう略奪に加え(これをやらなくしたのが実は織田信長)、和睦と見せかけて宴席で56しまくったりと、893も逃げ出すようなことばかりですし、およそ武士道っていうものをイメージしてる人からすると、ただのカオスでしたからね。
「武士たるもの七度主君を変えねば武士とは言えぬ」と藤堂高虎がいい、自己を高く評価してくれる主君を探して浪人することも是とし、「武者は犬ともいへ、畜生ともいへ、勝つことが本にて候」と朝倉宗滴っていうDQN戦国武将も言ってますから、これが儒教を発露とするものとはちょっと言えない気もしますねwwww逆に気持ち良すぎてアッパレって感じです。
その代わり、戦い方もメチャクチャ合理的で、適度なとこで戦いやめたり、応仁の乱みたいなのを除けば戦の目的がはっきりしてる場合が多かったので、すぐに終わったり、秀吉や長束正家みたいに兵站、物量で凌駕する戦いをやってるので、もし秀吉の戦い方が踏襲されれば明治の軍人勅諭の「質素を旨とすべし」なんてのはあったのかなぁと思いますし、上下関係も陸大卒よりも実力や、適材適所で決まったかもしれません。
明治以降は武士道は新渡戸稲造に宣伝され、日本の軍隊の思想は、誰も真似が出来ないカリスマ性を持った上杉謙信を踏襲したつもりでいたから、「生兵法は怪我の元」を軍隊がやってしまったと思います。しかも長幼の序が足かせになってる部分も大きかったですし。日本陸軍と、共産党は上杉謙信を調べて実践してる感があるのですが、あれは損耗率が異常に高すぎるのと、謙信がカリスマ過ぎて、まだ解明でき切れてないので、毘沙門天の化身っていうザ・宗教どころか、俺が毘沙門天っていう勢いですから、この記事の趣旨を突っ切る勢いでですw
葉隠だって結局平穏な時に書かれたものであり、新渡戸の武士道に関しても、半分はプロパガンダだと思ってます。
長幼の序とか上下関係も、やっぱり程度にもよりますし、武士道って言っても、中世は内ゲバや内乱、下剋上なんてのが結構ありましたし、江戸時代までの戦い方って、嘘もつき放題、乱取りっていう略奪に加え(これをやらなくしたのが実は織田信長)、和睦と見せかけて宴席で56しまくったりと、893も逃げ出すようなことばかりですし、およそ武士道っていうものをイメージしてる人からすると、ただのカオスでしたからね。
「武士たるもの七度主君を変えねば武士とは言えぬ」と藤堂高虎がいい、自己を高く評価してくれる主君を探して浪人することも是とし、「武者は犬ともいへ、畜生ともいへ、勝つことが本にて候」と朝倉宗滴っていうDQN戦国武将も言ってますから、これが儒教を発露とするものとはちょっと言えない気もしますねwwww逆に気持ち良すぎてアッパレって感じです。
その代わり、戦い方もメチャクチャ合理的で、適度なとこで戦いやめたり、応仁の乱みたいなのを除けば戦の目的がはっきりしてる場合が多かったので、すぐに終わったり、秀吉や長束正家みたいに兵站、物量で凌駕する戦いをやってるので、もし秀吉の戦い方が踏襲されれば明治の軍人勅諭の「質素を旨とすべし」なんてのはあったのかなぁと思いますし、上下関係も陸大卒よりも実力や、適材適所で決まったかもしれません。
明治以降は武士道は新渡戸稲造に宣伝され、日本の軍隊の思想は、誰も真似が出来ないカリスマ性を持った上杉謙信を踏襲したつもりでいたから、「生兵法は怪我の元」を軍隊がやってしまったと思います。しかも長幼の序が足かせになってる部分も大きかったですし。日本陸軍と、共産党は上杉謙信を調べて実践してる感があるのですが、あれは損耗率が異常に高すぎるのと、謙信がカリスマ過ぎて、まだ解明でき切れてないので、毘沙門天の化身っていうザ・宗教どころか、俺が毘沙門天っていう勢いですから、この記事の趣旨を突っ切る勢いでですw
葉隠だって結局平穏な時に書かれたものであり、新渡戸の武士道に関しても、半分はプロパガンダだと思ってます。
Posted by やま at 2017年08月17日 02:40
やま様
>長幼の序とか上下関係も、やっぱり程度にもよりますし・・・
そりゃそうです。
何事も程度によります。ただ長幼の序というのは徳川家康が長子相続制を導入したことも大きいと思いますが、ある意味家督相続争いを防止するという知恵であったともいえるでしょう。それはご指摘の下克上時代の戦国時代の名残を太平の世になくす意味もあったと思います。この事がのちの年功序列や卒業年次序列などに繋がっているのかと思います。ただ現代を見れば、年功序列制は崩壊し成果主義が導入されてからは、愛社精神はなくなり、会社は社員を使い捨ての「道具」扱いにし、結果賃金上昇や不況によって会社や工場を海外に移転したりして失業率は上がり産業の空洞化が進みました。まあ何が市場にいのかわかりませんが、価値観も制度もその時代時代に必要性に応じて生まれてくるものだと思います。
>長幼の序とか上下関係も、やっぱり程度にもよりますし・・・
そりゃそうです。
何事も程度によります。ただ長幼の序というのは徳川家康が長子相続制を導入したことも大きいと思いますが、ある意味家督相続争いを防止するという知恵であったともいえるでしょう。それはご指摘の下克上時代の戦国時代の名残を太平の世になくす意味もあったと思います。この事がのちの年功序列や卒業年次序列などに繋がっているのかと思います。ただ現代を見れば、年功序列制は崩壊し成果主義が導入されてからは、愛社精神はなくなり、会社は社員を使い捨ての「道具」扱いにし、結果賃金上昇や不況によって会社や工場を海外に移転したりして失業率は上がり産業の空洞化が進みました。まあ何が市場にいのかわかりませんが、価値観も制度もその時代時代に必要性に応じて生まれてくるものだと思います。
Posted by トラネコ at 2017年08月17日 06:08
at 2017年08月17日 06:08
 at 2017年08月17日 06:08
at 2017年08月17日 06:08