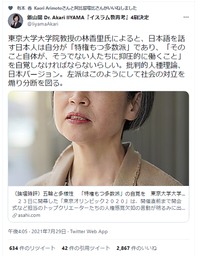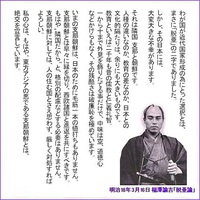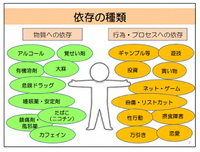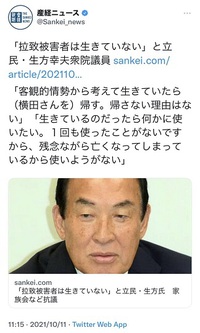雑感・中国人・韓国人の色彩感覚考
2016年05月21日
日本人が好む「地味で上品な色」、中国人が敬遠する理由は何?
中国メディアの今日頭条はこのほど、現代の日本人が好む「地味で上品な色」は中国人にとっては「人間らしさに欠けた色」として敬遠の対象になることを紹介。色というものに対し、日本人と中国人で好む対象が大きく違うというテーマについて論じている。
記事はまず、中国人消費者の体験として、「日系メーカーの地味で上品な色のポロシャツを値段が安いという理由で購入した」ところ、中国人の同僚から「なぜ草食系色の服を着ているのか」と突っ込まれたという体験談を紹介。草食系とは「性」をまったく感じさせないという意味だが、記事によれば同僚の指摘の要点は性のみならず、人間の豊かな感情を感じさせない服という点にある。
バブル時代、服装をはじめとした日本の社会全体の色は「物欲にのぼせた人々の精神の産物」だったと記事は指摘、色には人々の精神が反映されるという見方を示した。そしてバブル崩壊後の日本人は生活を見直そうと、「本来の自然で地味な姿に戻ろうと努力した」と説明した。
しかしその反動は大きく、日本社会には「精神面における潔癖性を美とする極端な見方が形成された」と記事は指摘、これは人間らしい豊かで自然な感情さえ美しくないものとして敬遠し始めたという意味だ。その結果現在の日本社会では友情を築いたり恋人を作るといった人間の豊かな感情に基づく活動に支障が生じていると論じた。
つまり前出の同僚による人間らしい感情を感じさせない服という指摘はポロシャツに対するものであると同時に、現在の日本社会が好む色すなわち精神面の潔癖性を鋭く感じ取ったというのが記事の主張だ。
日系ブランドのポロシャツが表す精神に対し、中国人の同僚は違和感を感じたということだが、中国では伝統的に「赤(紅)」が好まれる色であり、さらに原色を好む傾向にある。日本では原色はけばけばしいとされるケースもあるとおり、派手でメンツを重視する中国人と、謙虚さを美徳とする日本人の精神性が好む色にも表れていると言えそうだ。
(編集担当:村山健二)(イメージ写真提供:123RF)
サーチナ 2016-05-15 11:35
http://news.searchina.net/id/1609736?page=1

天安門広場の壁は赤いし、昔は真っ赤な流血もあったな・・・
>中国では伝統的に「赤(紅)」が好まれる色であり、さらに原色を好む傾向にある。
日本では原色はけばけばしいとされるケースもあるとおり、
派手でメンツを重視する中国人と、謙虚さを美徳とする日本人の精神性が
好む色にも表れていると言えそうだ。
まあ、そういうことだろうな。
>「日本人と中国人で好む対象が大きく違う」のは当たり前じゃないかwww
色彩感覚というのも、その地域の風土や人々の時間的育成度、
伝統というか習慣によって育成される文化的要素の一つである。
これが民族的な気質の一部となっているのである。
シナ人の赤好きの理由は縁起が良い、幸運の色、金銭の色だという。
そういえばシナの国旗も共産党の旗も赤だっけ・・・関係ないか・・・?
赤が好まれ派手な配色が好きなのもシナ人の民族性なのだ。

シナの赤い縁起物
だから結婚式や祝い事などは必ず赤地表示板を用いるし、
商店の宣伝用表示や看板などにも赤が用いられる。また戯曲にも赤は主人公、
白は悪役という決まりもあるらしい。日本人の白感覚とは真逆である。
また赤は縁起の良い色であると同時に魔除けの意味もあるという。
だからか、シナの住宅の入り口ドアには赤が多用されているのだそうだ。
もちろん幸運を呼び込むという二重の意味もあるのかもしれない。
いずれにせよ、シナ人は赤を好むと同時に派手な色使いを好むようだ。
服装センスに関しては、流行に敏感な人は日本や欧米のセンスを取り入れるだろうし、
一概に派手とか地味を服装では判断できないだろう。

京劇の主人公も赤いメイクと衣装で登場する。
ところで偏見覚悟で服装に限定しない一般論としていえば、
シナ人とアメリカ人、ラテン系の好みの色は似ている。
とにかく彼らはケバい原色系の色彩を好むことは間違いない。
中米数か国に暮らした経験、あくまで個人的な経験からいえば、
一般ラティーノの服装センスは日本人よりかなり劣り、服の品質もよくない。
若い人ほど配色も派手なケバいものを好むように思う。
またアメリカ人とは一口にまとめてははいえない。
なぜなら多民族国家だから欧州系、アジア系、アフリカ系・・・
様々な人種のルーツ的な嗜好傾向があるからである。
ただアメリカ人観光客は派手系の民芸品を好む傾向はあると思うし、
一般論的にみればやはり日本人の色彩感覚からは離れた配色も多い。
例えば食品への色付けには毒々しいもの少なくないのもアメリカだ。


さすがにこういう配色のケーキは日本ではお目にかかれないな・・・

最近アメリカで登場したレインボー寿司・・・
逆にヨーロッパ系のフランスやドイツ人などは地味な色彩も、
結構好んでファッションやインテリアにも取り入れている。
派手な配色を使う南欧イタリア人も意外に渋い色のコーディネイトは多い。
中北欧は気候も寒冷で四季の変化も比較的明瞭だからだろうか。
ある面では日本人と共通する色彩感覚もあるように思うのだが。
でもファッションの本場パリっ子は意外にも黒系の服装が多く感じる・・・
一説にはファッションを極めた?パリっ子の色彩感覚は、
色の究極の両端に位置する無彩色の黒と白に行きついたという。
まあ真偽は別にしても、なんとなくありそうな気もするな。

冬ということもあるのか、黒好きなパリっ子
日本人の服飾に関する色彩感覚も派手さがあっても安っぽさがない。
もっとも安っぽさと感じるのも日本人の好みからの判断だが、
民俗的に日本人の好みの色は四季の移り変わりによる自然の色彩ではないか。
これは染色技術が古く元々染料そのものが天然染料で出来ているからだろう。
染色技術は3,4世紀にシナから伝来し6世紀以降発達したと言われる。
ちなみに日本の織物技術は縄文時代草創期(1万2千年前)からある。
染料は近代以前は草木染など天然染料なので自然の色彩そのものであったから、
我々の色彩感覚は明瞭な四季の風土と伝統が育てた色彩感覚ではないかと思う。
あの渋めの侘び寂び系色彩を好む傾向も日本人らしいといえるだろうか。
メキシコ先住民の手工芸では派手な化学染料の糸を使っているのだが、
恐らくこれも近代に入ってのことだろう。昔はすべて天然染料だったはずだが、
スペイン人の征服による文化破壊で伝統の分断があったからだと想像する。
派手な色彩とはいっても個々の色の微妙なニュアンスの違いは大きい。
例えば沖縄の紅型の着物も本土のそれに比べれば派手な印象だが、
現代朝鮮のチマチョゴリの色合いとは大きく印象が異なることがわかるだろうか?

派手さを排した純和風の部屋

日本の着物の色彩は派手・地味問わず品格が感じられる。

沖縄の紅型(びんがた)染めの着物
本土の色彩に比べれば南国風の派手さが感じられるが、
染色技術の巧緻さや意匠性が感じられるのが特徴だ。
もちろん伝統的染料はすべて植物系天然染料である。
朝鮮は歴史的に日韓併合時代以前には染色技術がなく、
シナから買い入れていた王族以外の被支配階級においては、
すべて庶民の服は綿の生地の白(生成り)のままだったのは周知の通りだ。
元々染色技術がないから色彩の調整や配合、配色の感性も育たない。
こういう文化の国には洗練された色彩感覚など育つはずがない。
だからチマチョゴリの配色やデザインが安っぽいのである。
天然染料は派手とはいっても化学染料にくらべ彩度が抑え気味である。
この微妙な色合いや彩度の差異を感じられるセンスは天然染料の染色技術である。
誤解を恐れずにいえば、日本人と現代南朝鮮人の色彩感覚の違いは・・・
天然染料と化学染料の色彩感覚の違いとも言えないだろうか?

李氏朝鮮時代末期の庶民
すべて白い民族衣装に身を包んでいる。


原色の化学染料で染めた安っぽい現代のチマチョゴリ。
これには何らの創意工夫も服飾センスすら感じられない。
しかし魔法瓶を使う朝鮮式茶道ってwwwwwww(爆)
>バブル時代、服装をはじめとした日本の社会全体の色は
「物欲にのぼせた人々の精神の産物」だったと記事は指摘、
色には人々の精神が反映されるという見方を示した。
そしてバブル崩壊後の日本人は生活を見直そうと、
「本来の自然で地味な姿に戻ろうと努力した」と説明した。
一部同意。
バブル期にどういう色彩の服が流行ったか覚えていないが、
そういえば、あの頃は国中が「物欲にのぼせた時代」ではあったと思う。
それを言うならシナ・バブル関係なく、伝統的シナ人だって同じではないか。
確かに服装を始め、商業的な色彩はその時代を反映したものはあると思うが、
バブル時代の流行した服装の色彩は国民全体に影響したものではなく、
一部の若者の遊び着として派手さを強調したものだったと記憶している。
ジュリアナ東京で踊る女の子の服装もボディコン系の派手なものが多かったっけ。
但しその色彩は今見ても、決して安っぽい印象は私にはない。
着物と同じく派手さの中にも洗練された微妙な粋さがあったと思う。
私の記憶に間違いがなければだが・・・
バブル崩壊後は黒系の服装が多かったという印象もある。
やはり好調に興隆していた経済が一挙に崩壊し低迷すれば、
人々の気持ちも重く沈みがちになり、それが服装にも反映するのだろうか。

>日本社会には「精神面における潔癖性を美とする極端な見方が形成された」
>これは人間らしい豊かで自然な感情さえ美しくないものとして敬遠し始めたという意味だ
まったく的外れwww
やはり日本文化を理解できないシナ人の皮相で浅薄な分析である。
ここで述べている「精神面における潔癖性を美とする極端な見方」とか、
「人間らしい豊かで自然な感情さえ美しくないものとして敬遠し始めた」って何よ???
まずこの言葉の意味するところが分からないから何ともいえないが、
伝統文化を継承せず、分断歴史のシナ人に日本の伝統美がわかるはずがない。
日本人は潔癖性を意識することは事実だが、それは昔からの伝統である。
それに、シナ人にとっての「人間らしい豊かで自然な感情」とは、
エゴイストで打算的で感情むき出しのことを指しているのではないか?
少なくとも日本人の感性にはないシナ人或は朝鮮人のものであろう。
そういう前提で述べている分析だから、殆ど的を得ていないのだが、
文化摩擦というものには、こういう根深い文化の違いがあるのだろう。
シナ朝鮮人には永遠に日本人や日本文化は理解できないと思う。
ちなみに私の好きな色、特に服装に関していえば・・・
自然の色であるアースカラー(ベージュ、ブラウン、オリーブ・・・)と
無彩色(白黒灰)それに藍系の青である。
原色系の服は持っていないが、赤系なら臙脂は好きな色である。
服は持ってはいないが藤色も好きである。いつかこの色の服を着てみたい。
・・・ということで、今日もとりとめのない雑談で失礼する。

近隣国だからと言っても、別に無理してまで、
仲良くしたり、理解し合う必要もないんじゃない・・・
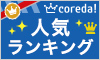

中国メディアの今日頭条はこのほど、現代の日本人が好む「地味で上品な色」は中国人にとっては「人間らしさに欠けた色」として敬遠の対象になることを紹介。色というものに対し、日本人と中国人で好む対象が大きく違うというテーマについて論じている。
記事はまず、中国人消費者の体験として、「日系メーカーの地味で上品な色のポロシャツを値段が安いという理由で購入した」ところ、中国人の同僚から「なぜ草食系色の服を着ているのか」と突っ込まれたという体験談を紹介。草食系とは「性」をまったく感じさせないという意味だが、記事によれば同僚の指摘の要点は性のみならず、人間の豊かな感情を感じさせない服という点にある。
バブル時代、服装をはじめとした日本の社会全体の色は「物欲にのぼせた人々の精神の産物」だったと記事は指摘、色には人々の精神が反映されるという見方を示した。そしてバブル崩壊後の日本人は生活を見直そうと、「本来の自然で地味な姿に戻ろうと努力した」と説明した。
しかしその反動は大きく、日本社会には「精神面における潔癖性を美とする極端な見方が形成された」と記事は指摘、これは人間らしい豊かで自然な感情さえ美しくないものとして敬遠し始めたという意味だ。その結果現在の日本社会では友情を築いたり恋人を作るといった人間の豊かな感情に基づく活動に支障が生じていると論じた。
つまり前出の同僚による人間らしい感情を感じさせない服という指摘はポロシャツに対するものであると同時に、現在の日本社会が好む色すなわち精神面の潔癖性を鋭く感じ取ったというのが記事の主張だ。
日系ブランドのポロシャツが表す精神に対し、中国人の同僚は違和感を感じたということだが、中国では伝統的に「赤(紅)」が好まれる色であり、さらに原色を好む傾向にある。日本では原色はけばけばしいとされるケースもあるとおり、派手でメンツを重視する中国人と、謙虚さを美徳とする日本人の精神性が好む色にも表れていると言えそうだ。
(編集担当:村山健二)(イメージ写真提供:123RF)
サーチナ 2016-05-15 11:35
http://news.searchina.net/id/1609736?page=1
天安門広場の壁は赤いし、昔は真っ赤な流血もあったな・・・
>中国では伝統的に「赤(紅)」が好まれる色であり、さらに原色を好む傾向にある。
日本では原色はけばけばしいとされるケースもあるとおり、
派手でメンツを重視する中国人と、謙虚さを美徳とする日本人の精神性が
好む色にも表れていると言えそうだ。
まあ、そういうことだろうな。
>「日本人と中国人で好む対象が大きく違う」のは当たり前じゃないかwww
色彩感覚というのも、その地域の風土や人々の時間的育成度、
伝統というか習慣によって育成される文化的要素の一つである。
これが民族的な気質の一部となっているのである。
シナ人の赤好きの理由は縁起が良い、幸運の色、金銭の色だという。
そういえばシナの国旗も共産党の旗も赤だっけ・・・関係ないか・・・?
赤が好まれ派手な配色が好きなのもシナ人の民族性なのだ。

シナの赤い縁起物
だから結婚式や祝い事などは必ず赤地表示板を用いるし、
商店の宣伝用表示や看板などにも赤が用いられる。また戯曲にも赤は主人公、
白は悪役という決まりもあるらしい。日本人の白感覚とは真逆である。
また赤は縁起の良い色であると同時に魔除けの意味もあるという。
だからか、シナの住宅の入り口ドアには赤が多用されているのだそうだ。
もちろん幸運を呼び込むという二重の意味もあるのかもしれない。
いずれにせよ、シナ人は赤を好むと同時に派手な色使いを好むようだ。
服装センスに関しては、流行に敏感な人は日本や欧米のセンスを取り入れるだろうし、
一概に派手とか地味を服装では判断できないだろう。

京劇の主人公も赤いメイクと衣装で登場する。
ところで偏見覚悟で服装に限定しない一般論としていえば、
シナ人とアメリカ人、ラテン系の好みの色は似ている。
とにかく彼らはケバい原色系の色彩を好むことは間違いない。
中米数か国に暮らした経験、あくまで個人的な経験からいえば、
一般ラティーノの服装センスは日本人よりかなり劣り、服の品質もよくない。
若い人ほど配色も派手なケバいものを好むように思う。
またアメリカ人とは一口にまとめてははいえない。
なぜなら多民族国家だから欧州系、アジア系、アフリカ系・・・
様々な人種のルーツ的な嗜好傾向があるからである。
ただアメリカ人観光客は派手系の民芸品を好む傾向はあると思うし、
一般論的にみればやはり日本人の色彩感覚からは離れた配色も多い。
例えば食品への色付けには毒々しいもの少なくないのもアメリカだ。


さすがにこういう配色のケーキは日本ではお目にかかれないな・・・

最近アメリカで登場したレインボー寿司・・・
逆にヨーロッパ系のフランスやドイツ人などは地味な色彩も、
結構好んでファッションやインテリアにも取り入れている。
派手な配色を使う南欧イタリア人も意外に渋い色のコーディネイトは多い。
中北欧は気候も寒冷で四季の変化も比較的明瞭だからだろうか。
ある面では日本人と共通する色彩感覚もあるように思うのだが。
でもファッションの本場パリっ子は意外にも黒系の服装が多く感じる・・・
一説にはファッションを極めた?パリっ子の色彩感覚は、
色の究極の両端に位置する無彩色の黒と白に行きついたという。
まあ真偽は別にしても、なんとなくありそうな気もするな。

冬ということもあるのか、黒好きなパリっ子
日本人の服飾に関する色彩感覚も派手さがあっても安っぽさがない。
もっとも安っぽさと感じるのも日本人の好みからの判断だが、
民俗的に日本人の好みの色は四季の移り変わりによる自然の色彩ではないか。
これは染色技術が古く元々染料そのものが天然染料で出来ているからだろう。
染色技術は3,4世紀にシナから伝来し6世紀以降発達したと言われる。
ちなみに日本の織物技術は縄文時代草創期(1万2千年前)からある。
染料は近代以前は草木染など天然染料なので自然の色彩そのものであったから、
我々の色彩感覚は明瞭な四季の風土と伝統が育てた色彩感覚ではないかと思う。
あの渋めの侘び寂び系色彩を好む傾向も日本人らしいといえるだろうか。
メキシコ先住民の手工芸では派手な化学染料の糸を使っているのだが、
恐らくこれも近代に入ってのことだろう。昔はすべて天然染料だったはずだが、
スペイン人の征服による文化破壊で伝統の分断があったからだと想像する。
派手な色彩とはいっても個々の色の微妙なニュアンスの違いは大きい。
例えば沖縄の紅型の着物も本土のそれに比べれば派手な印象だが、
現代朝鮮のチマチョゴリの色合いとは大きく印象が異なることがわかるだろうか?

派手さを排した純和風の部屋

日本の着物の色彩は派手・地味問わず品格が感じられる。

沖縄の紅型(びんがた)染めの着物
本土の色彩に比べれば南国風の派手さが感じられるが、
染色技術の巧緻さや意匠性が感じられるのが特徴だ。
もちろん伝統的染料はすべて植物系天然染料である。
朝鮮は歴史的に日韓併合時代以前には染色技術がなく、
シナから買い入れていた王族以外の被支配階級においては、
すべて庶民の服は綿の生地の白(生成り)のままだったのは周知の通りだ。
元々染色技術がないから色彩の調整や配合、配色の感性も育たない。
こういう文化の国には洗練された色彩感覚など育つはずがない。
だからチマチョゴリの配色やデザインが安っぽいのである。
天然染料は派手とはいっても化学染料にくらべ彩度が抑え気味である。
この微妙な色合いや彩度の差異を感じられるセンスは天然染料の染色技術である。
誤解を恐れずにいえば、日本人と現代南朝鮮人の色彩感覚の違いは・・・
天然染料と化学染料の色彩感覚の違いとも言えないだろうか?

李氏朝鮮時代末期の庶民
すべて白い民族衣装に身を包んでいる。


原色の化学染料で染めた安っぽい現代のチマチョゴリ。
これには何らの創意工夫も服飾センスすら感じられない。
しかし魔法瓶を使う朝鮮式茶道ってwwwwwww(爆)
>バブル時代、服装をはじめとした日本の社会全体の色は
「物欲にのぼせた人々の精神の産物」だったと記事は指摘、
色には人々の精神が反映されるという見方を示した。
そしてバブル崩壊後の日本人は生活を見直そうと、
「本来の自然で地味な姿に戻ろうと努力した」と説明した。
一部同意。
バブル期にどういう色彩の服が流行ったか覚えていないが、
そういえば、あの頃は国中が「物欲にのぼせた時代」ではあったと思う。
それを言うならシナ・バブル関係なく、伝統的シナ人だって同じではないか。
確かに服装を始め、商業的な色彩はその時代を反映したものはあると思うが、
バブル時代の流行した服装の色彩は国民全体に影響したものではなく、
一部の若者の遊び着として派手さを強調したものだったと記憶している。
ジュリアナ東京で踊る女の子の服装もボディコン系の派手なものが多かったっけ。
但しその色彩は今見ても、決して安っぽい印象は私にはない。
着物と同じく派手さの中にも洗練された微妙な粋さがあったと思う。
私の記憶に間違いがなければだが・・・
バブル崩壊後は黒系の服装が多かったという印象もある。
やはり好調に興隆していた経済が一挙に崩壊し低迷すれば、
人々の気持ちも重く沈みがちになり、それが服装にも反映するのだろうか。

>日本社会には「精神面における潔癖性を美とする極端な見方が形成された」
>これは人間らしい豊かで自然な感情さえ美しくないものとして敬遠し始めたという意味だ
まったく的外れwww
やはり日本文化を理解できないシナ人の皮相で浅薄な分析である。
ここで述べている「精神面における潔癖性を美とする極端な見方」とか、
「人間らしい豊かで自然な感情さえ美しくないものとして敬遠し始めた」って何よ???
まずこの言葉の意味するところが分からないから何ともいえないが、
伝統文化を継承せず、分断歴史のシナ人に日本の伝統美がわかるはずがない。
日本人は潔癖性を意識することは事実だが、それは昔からの伝統である。
それに、シナ人にとっての「人間らしい豊かで自然な感情」とは、
エゴイストで打算的で感情むき出しのことを指しているのではないか?
少なくとも日本人の感性にはないシナ人或は朝鮮人のものであろう。
そういう前提で述べている分析だから、殆ど的を得ていないのだが、
文化摩擦というものには、こういう根深い文化の違いがあるのだろう。
シナ朝鮮人には永遠に日本人や日本文化は理解できないと思う。
ちなみに私の好きな色、特に服装に関していえば・・・
自然の色であるアースカラー(ベージュ、ブラウン、オリーブ・・・)と
無彩色(白黒灰)それに藍系の青である。
原色系の服は持っていないが、赤系なら臙脂は好きな色である。
服は持ってはいないが藤色も好きである。いつかこの色の服を着てみたい。
・・・ということで、今日もとりとめのない雑談で失礼する。

近隣国だからと言っても、別に無理してまで、
仲良くしたり、理解し合う必要もないんじゃない・・・
Posted by トラネコ at 00:00│Comments(29)
│文化
この記事へのコメント
トラネコ様
色に罪はない。
私はあまり赤い色好きじゃないです。
それも時と場合です。
伝統として日本には朱色を華やかな場で使ってたのではないでしょうか。
丁度、今日記念日にオレンジ色のバラの花を一輪買って来てくれました。
夫は長年、深紅のバラを買ってくれるのですが、やっと私が深紅のバラに興味ないの理解してくれたみたいですww
いつも、有難うって言うのですが。。
今年は、心底嬉そうって顔してくれたねって。
キャッ!心と裏腹は相手に分るんですね。
夫はいつも真っ赤な薔薇の花束を贈る事が私を喜ばす事。
いつも、私が色々不満があっても薔薇を送ったらチャラみたいな態度があったからww
昔、夫の顔目掛けて薔薇の花束押し付けて、なめんなよ~って言った事有ります。
多分、男と女は同じ人間ですが別な生き物ですね。
美的感覚も同じ民族でも違いあるのでしょうか?
音楽も若い頃は楽しめた激しい曲も今ではまるで駄目です。
騒音としてしか認識できません。
人は老いと共に変わるのでしょか?
でも、クラッシク音楽は今でも好きです。
色に罪はない。
私はあまり赤い色好きじゃないです。
それも時と場合です。
伝統として日本には朱色を華やかな場で使ってたのではないでしょうか。
丁度、今日記念日にオレンジ色のバラの花を一輪買って来てくれました。
夫は長年、深紅のバラを買ってくれるのですが、やっと私が深紅のバラに興味ないの理解してくれたみたいですww
いつも、有難うって言うのですが。。
今年は、心底嬉そうって顔してくれたねって。
キャッ!心と裏腹は相手に分るんですね。
夫はいつも真っ赤な薔薇の花束を贈る事が私を喜ばす事。
いつも、私が色々不満があっても薔薇を送ったらチャラみたいな態度があったからww
昔、夫の顔目掛けて薔薇の花束押し付けて、なめんなよ~って言った事有ります。
多分、男と女は同じ人間ですが別な生き物ですね。
美的感覚も同じ民族でも違いあるのでしょうか?
音楽も若い頃は楽しめた激しい曲も今ではまるで駄目です。
騒音としてしか認識できません。
人は老いと共に変わるのでしょか?
でも、クラッシク音楽は今でも好きです。
Posted by うさこ at 2016年05月21日 01:09
おそらく以前にもどこかで私は似たようなことをコメントしたと思いますが、さらに付け加えれば、支那人が派手な色を好むのは周りが汚いからっていうのもあるみたいですね。しかも最近じゃ大気汚染がひどいからというのも付け加わったのかわかりませんが、アカの前は黄色が皇帝の色で清の国旗は黄色で、その後の軍閥の旗も張作霖の奉天閥は黄色が主体です。
あそこまでアカを際立たすとイライラするというか精神的におかしくなる気がします。私の両親も冬場とかジャケットは真っ赤なやつを着てて目が痛くなります。実際両親は支那人みたく自己中の塊みたいな人で、すぐイライラするんですよね。
私はそれこそ、赤系統はあまり好きではないのでワインレッドのブレザーが一着あるくらいで、カラフルよりも、自然に溶け込む感じが好きですが、自分の私物を見ると、靴は水色で、今はコンバースオールスターのヘリテージでコバルト系のやつを探してて、食器は私が瑠璃色の美しさと、レトロ感に一目ぼれして3年くらいかけて探し求めて今年の五月の美濃焼祭りでようやく手に入れた、美濃焼の瑠璃色フタ付どんぶりで、手に入れてからは、それで食事をしてます。しかも店の人曰く、そんな古いものをワザワザ探し求めてきてくれた心意気だと言ってものすごくマケてくれてました。
http://item.rakuten.co.jp/honjo/a359-31-10/
因みに、これとは別に、るり色水玉フタ付き丼を一つだけでいいから探してて、レトロブームか何かの影響か有田で一か所だけ作っているところがあるそうですが、有田焼は以前「大粛清」をしたので、地元に近い美濃焼き、もしくは瀬戸焼で探してます。
http://denkyu.ocnk.net/product/2284
あとは昭和のカレー皿のネイビーラインが入っているやつも、美濃焼きか欧州のやつを探してまして。
http://calamel.jp/go/item/42354941
カレー皿は似たようなのや、写真に載ってるのは結構あるんですが、理想としてるのがなかなか…
今年の10月あたりにどんぶり祭りがあるのでその時にGETしようかなぁと。
これも誰かが言っていたのですが我が国の場合、風景がものすごく美しいので、自然に溶け込むというのもどこかで考慮していると思います。確かに、自然の風景が十分カラフルなのに、自分たちも原色系のど派手な色を着てしまうとアンバランスになるような気がします。
観光客を見ればわかりますが、イスラムも含むコーカソイド系は、やっぱりその辺は考えてますけれど、アジアの観光客はそうはなりません。原色系の服で、しかも汚れがついてるので、目立つんですよねぇ。
あそこまでアカを際立たすとイライラするというか精神的におかしくなる気がします。私の両親も冬場とかジャケットは真っ赤なやつを着てて目が痛くなります。実際両親は支那人みたく自己中の塊みたいな人で、すぐイライラするんですよね。
私はそれこそ、赤系統はあまり好きではないのでワインレッドのブレザーが一着あるくらいで、カラフルよりも、自然に溶け込む感じが好きですが、自分の私物を見ると、靴は水色で、今はコンバースオールスターのヘリテージでコバルト系のやつを探してて、食器は私が瑠璃色の美しさと、レトロ感に一目ぼれして3年くらいかけて探し求めて今年の五月の美濃焼祭りでようやく手に入れた、美濃焼の瑠璃色フタ付どんぶりで、手に入れてからは、それで食事をしてます。しかも店の人曰く、そんな古いものをワザワザ探し求めてきてくれた心意気だと言ってものすごくマケてくれてました。
http://item.rakuten.co.jp/honjo/a359-31-10/
因みに、これとは別に、るり色水玉フタ付き丼を一つだけでいいから探してて、レトロブームか何かの影響か有田で一か所だけ作っているところがあるそうですが、有田焼は以前「大粛清」をしたので、地元に近い美濃焼き、もしくは瀬戸焼で探してます。
http://denkyu.ocnk.net/product/2284
あとは昭和のカレー皿のネイビーラインが入っているやつも、美濃焼きか欧州のやつを探してまして。
http://calamel.jp/go/item/42354941
カレー皿は似たようなのや、写真に載ってるのは結構あるんですが、理想としてるのがなかなか…
今年の10月あたりにどんぶり祭りがあるのでその時にGETしようかなぁと。
これも誰かが言っていたのですが我が国の場合、風景がものすごく美しいので、自然に溶け込むというのもどこかで考慮していると思います。確かに、自然の風景が十分カラフルなのに、自分たちも原色系のど派手な色を着てしまうとアンバランスになるような気がします。
観光客を見ればわかりますが、イスラムも含むコーカソイド系は、やっぱりその辺は考えてますけれど、アジアの観光客はそうはなりません。原色系の服で、しかも汚れがついてるので、目立つんですよねぇ。
Posted by やま at 2016年05月21日 03:05
自然界で赤色の原色は毒か血の印象ですからあんまり使いたくない色です。目もチカチカしますし。そういえばお隣の国は良く血なまぐさいお話が長い歴史で多いそうですけど、もしかして、色彩も関係あったりするんでしょうかねえ。お互いに色彩1つとっても異なるのですから無理に付き合う必要もないと思います。
草木染でも自然界の違いがあるんです。トラネコ様の住まわれているメキシコにたぶん多く生息していると思うんですが、サボテンも草木染が出来るんですけど、これが錫(スズ)の金属イオンを使うと原色の赤に近い色になるんです。もしかすると、自然そのものでも海外特に赤道付近の植物は原色傾向、そこから少し離れると色彩が落ち着いてくるかもしれませんね。そういえば魚も熱帯地域は鮮やか、日本はそこまで鮮やかじゃなかったですね。
草木染でも自然界の違いがあるんです。トラネコ様の住まわれているメキシコにたぶん多く生息していると思うんですが、サボテンも草木染が出来るんですけど、これが錫(スズ)の金属イオンを使うと原色の赤に近い色になるんです。もしかすると、自然そのものでも海外特に赤道付近の植物は原色傾向、そこから少し離れると色彩が落ち着いてくるかもしれませんね。そういえば魚も熱帯地域は鮮やか、日本はそこまで鮮やかじゃなかったですね。
Posted by おしょう at 2016年05月21日 07:22
色彩感覚は確かに国によって色々ですね。そんなに多くの国に行ってはいないのですが暑い国は何故か原色を好んで使っているイメージがあります。かえって暑苦しいのに不思議です。日本人だからか私も皆さん同様やはり原色は好みませんねぇ。持っている服も白や黒が多いですね。目立つのが嫌いだし女性と歩く際は相手を立てる事が出来て便利です。しかし朝鮮茶道…友人がウリナラ起源説を論破してました。曰く北朝鮮には無いじゃ無いかと…。
Posted by 今はスマホがPC代わり。 at 2016年05月21日 08:44
トラネコせんせー
色についての考察、すごく興味深いです。
最近、障害児支援で実際に活かされている色彩心理学のことを思い出しました。言葉でのコミュニケーションの苦手な発達障害児の理解を助けるツールとしても注目されはじめているそうです。
赤というのは、「物質」「現実」「欲」を表すようです。ポジティブな意味では「活動的」「情熱的」、ネガティブな意味だと「怒り」「葛藤」とか。
一方、土や木の色である茶色は、ポジティブ⇒「安定」「堅実」「伝統」、ネガティブ⇒「地味」「頑固」など。
たとえば、ドラマ「積み木くずし」で不良少女が部屋中を黒く塗りつぶした上からピンクのスプレーで文字を書きなぐっているシーンがありました。
「孤独」を表す黒に、「甘え」を表すピンク。その少女の心の内をよく表現したものだと感心したものです。
なんかこう、好きな色(その時の気分で選ぶ色)で、その人や国民の心理も分析できそうで面白いなーと思いました。
色についての考察、すごく興味深いです。
最近、障害児支援で実際に活かされている色彩心理学のことを思い出しました。言葉でのコミュニケーションの苦手な発達障害児の理解を助けるツールとしても注目されはじめているそうです。
赤というのは、「物質」「現実」「欲」を表すようです。ポジティブな意味では「活動的」「情熱的」、ネガティブな意味だと「怒り」「葛藤」とか。
一方、土や木の色である茶色は、ポジティブ⇒「安定」「堅実」「伝統」、ネガティブ⇒「地味」「頑固」など。
たとえば、ドラマ「積み木くずし」で不良少女が部屋中を黒く塗りつぶした上からピンクのスプレーで文字を書きなぐっているシーンがありました。
「孤独」を表す黒に、「甘え」を表すピンク。その少女の心の内をよく表現したものだと感心したものです。
なんかこう、好きな色(その時の気分で選ぶ色)で、その人や国民の心理も分析できそうで面白いなーと思いました。
Posted by 自称29歳 at 2016年05月21日 09:19
見るからに安っぽいチマチョゴリを纏い、「魔法瓶」を用いて「朝鮮式茶道」なるものを披露するところに、南恨国の文化的後進性や、独創性の欠落ぶりが窺え、笑ってしまいます。「布地」といえば、「恐竜戦隊ジュウレンジャー」で、今は亡き曽我町子氏が熱演し、好評を博した「魔女バンドーラ」のドレスの布地は、「小紋」でした。「子供番組」だからといって手を抜かず、アップに堪える布地を選ぶとはと、ファンは感心したものです。悪意に満ちた「パクリ」しかできない民族に、どんな未来があるのやら・・・。
Posted by NTRC特撮軍団長・ヤラセロウ大元帥 at 2016年05月21日 09:19
お疲れ様です(^-^)/
>シナ人にとっての「人間らしい豊かで自然な感情」とは、
エゴイストで打算的で感情むき出しのことを指しているのではないか?
超納得w
確かにそれを色で表現すると「赤」にしかならんでしょうね。
日本の場合は、四季折々の自然の風景の色を取り入れているという段階で、表現方法が異なるシナ人には理解出来ないと思います。
古来からの色があり、かさねの色目という伝統の配色もあります。
ちなみに私は「杜若」の配色の薄手ストールを愛用しており、今の時期は大変重宝します。
あー、日本人で良かった(o^^o)
そういった意味合いや法則等が皆無、しかも生地もどう見てもペラペラ化繊なチマチョゴリなどは論外です。
>シナ人にとっての「人間らしい豊かで自然な感情」とは、
エゴイストで打算的で感情むき出しのことを指しているのではないか?
超納得w
確かにそれを色で表現すると「赤」にしかならんでしょうね。
日本の場合は、四季折々の自然の風景の色を取り入れているという段階で、表現方法が異なるシナ人には理解出来ないと思います。
古来からの色があり、かさねの色目という伝統の配色もあります。
ちなみに私は「杜若」の配色の薄手ストールを愛用しており、今の時期は大変重宝します。
あー、日本人で良かった(o^^o)
そういった意味合いや法則等が皆無、しかも生地もどう見てもペラペラ化繊なチマチョゴリなどは論外です。
Posted by きいろ香 at 2016年05月21日 15:08
派手な色の組み合わせはえてして安っぽくなりがちなので難しいのです。その点ではシックなほうが無難なのです。シナ朝鮮に限らず、私は同じ派手でもアジアのゴテゴテ文化の派手っぽさは好みません。明らかにデザインとして失敗しているように思います。一方で、ある種のアフリカ文化の派手さはかなりハイセンスな感じがします。ヨーロッパでもラテン系、特にイタリア系は派手ではないでしょうか。染料は知りませんが、顔料も天然物のほうが上品だと思います。合成は工事現場のライトのような、けばけばしい派手さでしょう。
このアジア彩色に通じるケバケバシさは、一種の貧しさからくるような気がします。貧しい人は、高密度なもので全てを満たさなければ気が済まないのです。なぜなら、彼等の心や人生が虚ろだから、それを埋めたいのです。逆に心の豊かな人は、高密度なものばかりでなく、空虚なものをも必要とするのです。
このアジア彩色に通じるケバケバシさは、一種の貧しさからくるような気がします。貧しい人は、高密度なもので全てを満たさなければ気が済まないのです。なぜなら、彼等の心や人生が虚ろだから、それを埋めたいのです。逆に心の豊かな人は、高密度なものばかりでなく、空虚なものをも必要とするのです。
Posted by 牛虎の金さん at 2016年05月21日 21:42
トラネコ様、皆様。
いつものトラネコさんのブログの常連の方は、色彩感覚も同じ匂いを感じてしまいましたww
やま様が仰る様に自然が美しい国土の日本であるが故、普段使いの服装は地味って言うか自己主張しなくても心が安定してられるのかもですね。
欧米人ともシナ朝鮮人ともアフリカや東南アジアとかの人達とも違う特殊な感性を持ってるのが日本人なのかなぁって思います。
勿論、上下ってレベルの次元の話ではなく。
大昔、冬に山陰に旅行に行った時、水墨画の世界ってこれなんだって思った事あります。
ホントに白と黒だけの景色でした。生まれて初めて見た世界でした。
雪が半端無く降っててモノクロの世界でしたが、綺麗って思いました。
一緒に行ったw友達が、陰気だぁ~嫌や~帰りたい~w
大阪に帰って来てやっぱり大阪はええなぁ~冬でも快適やしなぁ~
友達にとって大阪の良さを認識する旅になりました~w
日本に住んでおれば色んな景色見る事できますね。
日本人は四季折々を経験する事で独特の感性が培われるのかな?
いつものトラネコさんのブログの常連の方は、色彩感覚も同じ匂いを感じてしまいましたww
やま様が仰る様に自然が美しい国土の日本であるが故、普段使いの服装は地味って言うか自己主張しなくても心が安定してられるのかもですね。
欧米人ともシナ朝鮮人ともアフリカや東南アジアとかの人達とも違う特殊な感性を持ってるのが日本人なのかなぁって思います。
勿論、上下ってレベルの次元の話ではなく。
大昔、冬に山陰に旅行に行った時、水墨画の世界ってこれなんだって思った事あります。
ホントに白と黒だけの景色でした。生まれて初めて見た世界でした。
雪が半端無く降っててモノクロの世界でしたが、綺麗って思いました。
一緒に行ったw友達が、陰気だぁ~嫌や~帰りたい~w
大阪に帰って来てやっぱり大阪はええなぁ~冬でも快適やしなぁ~
友達にとって大阪の良さを認識する旅になりました~w
日本に住んでおれば色んな景色見る事できますね。
日本人は四季折々を経験する事で独特の感性が培われるのかな?
Posted by うさこ at 2016年05月21日 22:17
トラネコ様
レス違いで申し訳ありませんが、今、日本で沖縄在住の元アメリカ海兵隊員で今は退役(民間企業の社員としてアメリカの基地でIT関係の事務職の国籍アメリカ人)が日本人女性殺害の事件。
沖縄に米軍基地があるからこんな事件があるって事で米兵出て行け!てなってます。
私は、この女性が殺害された事とこんな悲惨な目にあった事、そして家族の悲痛な思いを聞くと他人事として聞くことは出来ません。
絶対あってはならない事です。
ですが、それと、米軍基地が沖縄にあるからこんな事が起きるから米軍出て行けは違うと思います。
異常な人間はどこの都市にも存在します。
逆に、日本人に迷惑かけるのが日本人殺すのが反日万歳叫んでる民族が日本にお出入り自由ってのがおかしくないですか?
レス違いで申し訳ありませんが、今、日本で沖縄在住の元アメリカ海兵隊員で今は退役(民間企業の社員としてアメリカの基地でIT関係の事務職の国籍アメリカ人)が日本人女性殺害の事件。
沖縄に米軍基地があるからこんな事件があるって事で米兵出て行け!てなってます。
私は、この女性が殺害された事とこんな悲惨な目にあった事、そして家族の悲痛な思いを聞くと他人事として聞くことは出来ません。
絶対あってはならない事です。
ですが、それと、米軍基地が沖縄にあるからこんな事が起きるから米軍出て行けは違うと思います。
異常な人間はどこの都市にも存在します。
逆に、日本人に迷惑かけるのが日本人殺すのが反日万歳叫んでる民族が日本にお出入り自由ってのがおかしくないですか?
Posted by うさこ at 2016年05月21日 23:05
うさこ様
>夫は長年、深紅のバラを買ってくれるのですが・・・
いいですねえ!
仰りたいことはわかりますが、色の好みなんかこの際どーでもいいじゃないですか、要は気持ちですから。それにしても、うさこ様の夫婦関係は理想的なんじゃないかな。結婚生活に失敗した私には憧れる夫婦像であります。
やま様
同意です。
>支那人が派手な色を好むのは周りが汚いからっていうのもあるみたいですね。
なるほど、そういう観方も面白いですね。
ただ疑問なのは、そんなに汚い環境をキレイにしようと思わないのですかね?まあ思わないんでしょうね、なんせシナ人ですから(笑)
>あそこまでアカを際立たすとイライラするというか精神的におかしくなる気がします
そうですね、私も同じです。
ただ赤とはいってもいろいろありますが、シナ人好みの赤は一般にカーマインという黄色味がかった赤です。やま様のジャケットのワインレッドは臙脂系だと思います。臙脂になればまた印象はシックになりますね。私も好きです。
>るり色水玉フタ付き丼
写真を見ましたが、これは瑠璃というより藍ですね。
瑠璃は古代からの青でラピスラズリーの粉砕した岩絵の具に近い色で、藍よりも明るめの青ですね。ターコイズブルーよりかは暗めになりますが、上品な色です。
>我が国の場合、風景がものすごく美しいので、自然に溶け込むというのもどこかで考慮していると思います
これは大いに同意。
やはり日本の風土の影響は否定できません。
おしょう様
同意です。
>自然界で赤色の原色は毒か血の印象ですから・・・
恐らくこれは警告だと思います。
毒キノコや毒カエルなどが自分を守るために、外敵から身を守る手段に派手なめだつ赤の皮膚をもって毒があるんだぞ、と警告しているのかも知れませんね。毒々しいなんて表現が赤にはあるのでしょう。
>サボテンも草木染が出来るんですけど、これが錫(スズ)の金属イオンを使うと原色の赤に近い色になるんです。
これってサボテンに着く虫のことじゃないですかね?
サボテンの草木染め色は緑だったと思います。錫イオンを使うというのは私は不勉強で知りません。メキシコの赤い染料は、伝統的にはコチニールというカイガラムシの一種をつかっていました。この赤も天然顔料だけあって、派手とはいえ臙脂に近い渋い色です。
熱帯系の生き物には派手な色彩が多いですね。これも太陽光の強い光の反映なんでしょうか。
今はスマホがPC代わり。様
そうですね、色彩感覚も風土が大きいですね。
>目立つのが嫌いだし女性と歩く際は相手を立てる事が出来て便利です
おお、デートのときにそこまで女性に気を使ってますか。
そういう気遣い感覚も日本人なんですかね。いいことです。
自称29歳様
同意です。
>赤というのは、「物質」「現実」「欲」を表すようです。
へえ、そうなんですか。
赤というのはまさにシナ人の感性というか、民族性そのものを表わした色ですね。日本人の自然色愛好も風土に由来しているのもわかりますね。
NTRC特撮軍団長・ヤラセロウ大元帥様
同意です。
半島系の民族はとにかく歴史的に独創性という精神気質は育たなかったのですね。だから何でもパクり、それに留まらすそれをウリジナルにしてしまいたい心理がまさにあの半島民族の気質そのものでしょう。ところで彼らはどんな色を好むのでしょうね・・・
きいろ香様
同意です。
>かさねの色目という伝統の配色
十二単などはまさにそれですね。
平安時代にすでに日本人には配色、コーディネートという感性があったんですね。同時代の諸外国文化に比べ、季節による配色の違いも工夫されていたのですから大したものです。さすが四季の変化の明瞭な日本の風土ですね。
牛虎の金さん様
>私は同じ派手でもアジアのゴテゴテ文化の派手っぽさは好みません。
そうですか・・・
ではインドの民族衣装のサリーの派手さは如何ですか?インドネシアのバティック染めもよいセンスのものがあると思いますし、タイ・シルク織物もよい配色だと思いますけどね・・・。私はこれらアジアの色彩センスは中々品性があるセンスだと思います。まあ色も配色も個々人の好み、国民性、民族性ですから良し悪しというのも難しいですけどね。
うさこ様
>大昔、冬に山陰に旅行に行った時、水墨画の世界って・・・
>一緒に行ったw友達が、陰気だぁ~嫌や~帰りたい~w
水墨画のセンスがわからんか・・・
そういえば大阪もある意味、派手な感じはありますね。
ヒョウ柄のプリント生地を好む大阪のオバちゃんとか、ケバい感じがありますね。これもまた地域の風土でしょうか。
>夫は長年、深紅のバラを買ってくれるのですが・・・
いいですねえ!
仰りたいことはわかりますが、色の好みなんかこの際どーでもいいじゃないですか、要は気持ちですから。それにしても、うさこ様の夫婦関係は理想的なんじゃないかな。結婚生活に失敗した私には憧れる夫婦像であります。
やま様
同意です。
>支那人が派手な色を好むのは周りが汚いからっていうのもあるみたいですね。
なるほど、そういう観方も面白いですね。
ただ疑問なのは、そんなに汚い環境をキレイにしようと思わないのですかね?まあ思わないんでしょうね、なんせシナ人ですから(笑)
>あそこまでアカを際立たすとイライラするというか精神的におかしくなる気がします
そうですね、私も同じです。
ただ赤とはいってもいろいろありますが、シナ人好みの赤は一般にカーマインという黄色味がかった赤です。やま様のジャケットのワインレッドは臙脂系だと思います。臙脂になればまた印象はシックになりますね。私も好きです。
>るり色水玉フタ付き丼
写真を見ましたが、これは瑠璃というより藍ですね。
瑠璃は古代からの青でラピスラズリーの粉砕した岩絵の具に近い色で、藍よりも明るめの青ですね。ターコイズブルーよりかは暗めになりますが、上品な色です。
>我が国の場合、風景がものすごく美しいので、自然に溶け込むというのもどこかで考慮していると思います
これは大いに同意。
やはり日本の風土の影響は否定できません。
おしょう様
同意です。
>自然界で赤色の原色は毒か血の印象ですから・・・
恐らくこれは警告だと思います。
毒キノコや毒カエルなどが自分を守るために、外敵から身を守る手段に派手なめだつ赤の皮膚をもって毒があるんだぞ、と警告しているのかも知れませんね。毒々しいなんて表現が赤にはあるのでしょう。
>サボテンも草木染が出来るんですけど、これが錫(スズ)の金属イオンを使うと原色の赤に近い色になるんです。
これってサボテンに着く虫のことじゃないですかね?
サボテンの草木染め色は緑だったと思います。錫イオンを使うというのは私は不勉強で知りません。メキシコの赤い染料は、伝統的にはコチニールというカイガラムシの一種をつかっていました。この赤も天然顔料だけあって、派手とはいえ臙脂に近い渋い色です。
熱帯系の生き物には派手な色彩が多いですね。これも太陽光の強い光の反映なんでしょうか。
今はスマホがPC代わり。様
そうですね、色彩感覚も風土が大きいですね。
>目立つのが嫌いだし女性と歩く際は相手を立てる事が出来て便利です
おお、デートのときにそこまで女性に気を使ってますか。
そういう気遣い感覚も日本人なんですかね。いいことです。
自称29歳様
同意です。
>赤というのは、「物質」「現実」「欲」を表すようです。
へえ、そうなんですか。
赤というのはまさにシナ人の感性というか、民族性そのものを表わした色ですね。日本人の自然色愛好も風土に由来しているのもわかりますね。
NTRC特撮軍団長・ヤラセロウ大元帥様
同意です。
半島系の民族はとにかく歴史的に独創性という精神気質は育たなかったのですね。だから何でもパクり、それに留まらすそれをウリジナルにしてしまいたい心理がまさにあの半島民族の気質そのものでしょう。ところで彼らはどんな色を好むのでしょうね・・・
きいろ香様
同意です。
>かさねの色目という伝統の配色
十二単などはまさにそれですね。
平安時代にすでに日本人には配色、コーディネートという感性があったんですね。同時代の諸外国文化に比べ、季節による配色の違いも工夫されていたのですから大したものです。さすが四季の変化の明瞭な日本の風土ですね。
牛虎の金さん様
>私は同じ派手でもアジアのゴテゴテ文化の派手っぽさは好みません。
そうですか・・・
ではインドの民族衣装のサリーの派手さは如何ですか?インドネシアのバティック染めもよいセンスのものがあると思いますし、タイ・シルク織物もよい配色だと思いますけどね・・・。私はこれらアジアの色彩センスは中々品性があるセンスだと思います。まあ色も配色も個々人の好み、国民性、民族性ですから良し悪しというのも難しいですけどね。
うさこ様
>大昔、冬に山陰に旅行に行った時、水墨画の世界って・・・
>一緒に行ったw友達が、陰気だぁ~嫌や~帰りたい~w
水墨画のセンスがわからんか・・・
そういえば大阪もある意味、派手な感じはありますね。
ヒョウ柄のプリント生地を好む大阪のオバちゃんとか、ケバい感じがありますね。これもまた地域の風土でしょうか。
Posted by トラネコ at 2016年05月22日 09:14
at 2016年05月22日 09:14
 at 2016年05月22日 09:14
at 2016年05月22日 09:14トラネコ様
>これってサボテンに着く虫のことじゃないですかね
恥ずかしい、その通りです。間違えてしまいました。本当に申し訳ありません。
熱帯系に原色の生物が多いのはどうやら多種多様な生態系が影響を与えているのもあるかもしれませんね。種が多いと敵も多いですから警告色の黄色や赤色といったものになったり、反面、繁殖目的にメスもしくはオスが原色を入れてアピールするようです。日本の場合は山々で区切られているのでそこまで種の生存競争が激しくなく繁殖目的でも藍色や朱色ぐらいになるのかもしれません。
そう思うと日本の櫻はまさしく日本人向けの質素でありながらの鮮やかさなのかもと感じます。
>これってサボテンに着く虫のことじゃないですかね
恥ずかしい、その通りです。間違えてしまいました。本当に申し訳ありません。
熱帯系に原色の生物が多いのはどうやら多種多様な生態系が影響を与えているのもあるかもしれませんね。種が多いと敵も多いですから警告色の黄色や赤色といったものになったり、反面、繁殖目的にメスもしくはオスが原色を入れてアピールするようです。日本の場合は山々で区切られているのでそこまで種の生存競争が激しくなく繁殖目的でも藍色や朱色ぐらいになるのかもしれません。
そう思うと日本の櫻はまさしく日本人向けの質素でありながらの鮮やかさなのかもと感じます。
Posted by おしょう at 2016年05月22日 10:47
トラネコ様
うさこ様
ヨコから失礼します。
おっしゃる通り、大阪には独特なケバさが有ります。
原色やアニマル柄が好きなオバちゃんが多いんです。
が、これはアッチ方面の影響が強いのではないか、と個人的には思ってます。
一昔前の大店のダンさんやごりょんさんなどは、おっとりとしたなにわ言葉を話し、服装のセンスもシックで落ち着いたものだったと聞いてます。
戦後、こういった人たちは北の山手方面に移り住み、現在では原色派手好きな人たちに、すっかり入れ替わってしまったのだと推測します。
コチニールと言えば、カンパリの色がそうですね、確か。
うさこ様
ヨコから失礼します。
おっしゃる通り、大阪には独特なケバさが有ります。
原色やアニマル柄が好きなオバちゃんが多いんです。
が、これはアッチ方面の影響が強いのではないか、と個人的には思ってます。
一昔前の大店のダンさんやごりょんさんなどは、おっとりとしたなにわ言葉を話し、服装のセンスもシックで落ち着いたものだったと聞いてます。
戦後、こういった人たちは北の山手方面に移り住み、現在では原色派手好きな人たちに、すっかり入れ替わってしまったのだと推測します。
コチニールと言えば、カンパリの色がそうですね、確か。
Posted by きいろ香 at 2016年05月22日 12:45
確か、河添恵子先生も仰っていたのですが欧米人や日本人と違って、自然が豊かなところよか、カジノ街とか、とにかくギンギラギンのヤカマシイ所が大好きみたいで、ホントその通りですし、外で支那人を見分けるのはもの結局服装が原色ばかり、そうでないにしろトータルコーディネートが不自然なので見分けつきやすいです。なんといっても、山にペンキ塗ろうとかほざいている連中ですからね。 京劇の画像見ててホント納得します。赤か黄色をケバくした衣装にど派手の衣装ですからね。それで鳴り物をジャンジャン鳴らしまくって、色覚異常の雑音で、甲高い二胡と、あいつらの喚くような喋りが入ったりするわけですよね。あんなもんを芸術扱いとか気が狂ってるとしか思えません。支那と朝鮮はやっぱり似たり寄ったりです。
日本の派手さといえば、せいぜいバサラ大名の佐々木判官とか、徳川宗春ですもんね。しかも宗春は景気対策でやってましたし。(信長公と太閤殿下は触れないでおきますねww)歌舞伎だって、派手とはいっても、偏った色を使った演出ではないですし、話の流れに合った情景を流してて、緩急がしっかりしてると思います。
私の買ったどんぶりは、岐阜県では技術者が90歳で引退した?らしく後継いないそうで…。
日本の赤の使い方は、クジラ幕なんか見たく、赤の重ね塗りとかして重み出してますもんね、あくまで自然と調和した形で、神社では厄災を防ぐためとかですもんね。
同じ赤の使い方もここまで変わるのかと思い知らされます。
日本の派手さといえば、せいぜいバサラ大名の佐々木判官とか、徳川宗春ですもんね。しかも宗春は景気対策でやってましたし。(信長公と太閤殿下は触れないでおきますねww)歌舞伎だって、派手とはいっても、偏った色を使った演出ではないですし、話の流れに合った情景を流してて、緩急がしっかりしてると思います。
私の買ったどんぶりは、岐阜県では技術者が90歳で引退した?らしく後継いないそうで…。
日本の赤の使い方は、クジラ幕なんか見たく、赤の重ね塗りとかして重み出してますもんね、あくまで自然と調和した形で、神社では厄災を防ぐためとかですもんね。
同じ赤の使い方もここまで変わるのかと思い知らされます。
Posted by やま at 2016年05月22日 15:03
おしょう様
いえいえ、間違いは誰にもあります。
>熱帯系に原色の生物が多いのはどうやら多種多様な生態系が影響を与えている・・・
多分仰る通りでしょう。
種類が多いと生存競争が激しいですから、サバイバルも繁殖も目立たなくてはなりませんしね。シナ人の赤や派手好みもあの人口のせいかな・・・
きいろ香様
なんで大阪のオバちゃんはヒョウ柄の服が好きなんですかね?
アッチ方面もヒョウ柄好きなんですかね、いったい何が影響してるんでしょうか、これ長年の疑問なんですが・・・
やま様
歌舞伎も結構派手な衣装ですが、京劇のメイクや衣装ほど下卑た感じがしませんよね。なんででしょうか・・・やはり歌舞伎は安土桃山時代が発祥ですから500年くらいの歴史があります。京劇は清朝の乾隆帝時代が起源ですから、まあ200年くらいか、シナという風土に加えそういう歴史の洗練されかたってのもあるでしょうね。
いえいえ、間違いは誰にもあります。
>熱帯系に原色の生物が多いのはどうやら多種多様な生態系が影響を与えている・・・
多分仰る通りでしょう。
種類が多いと生存競争が激しいですから、サバイバルも繁殖も目立たなくてはなりませんしね。シナ人の赤や派手好みもあの人口のせいかな・・・
きいろ香様
なんで大阪のオバちゃんはヒョウ柄の服が好きなんですかね?
アッチ方面もヒョウ柄好きなんですかね、いったい何が影響してるんでしょうか、これ長年の疑問なんですが・・・
やま様
歌舞伎も結構派手な衣装ですが、京劇のメイクや衣装ほど下卑た感じがしませんよね。なんででしょうか・・・やはり歌舞伎は安土桃山時代が発祥ですから500年くらいの歴史があります。京劇は清朝の乾隆帝時代が起源ですから、まあ200年くらいか、シナという風土に加えそういう歴史の洗練されかたってのもあるでしょうね。
Posted by トラネコ at 2016年05月22日 15:49
at 2016年05月22日 15:49
 at 2016年05月22日 15:49
at 2016年05月22日 15:49歌舞伎は、色の使い方とか、相当理解していると思います、幕引きの色が黒赤緑ですし、寺社の柱が赤くても、中の枠みたいなのが緑だったりして、色相環とか理解してたんじゃありませんかね・・・補色っていう概念が発達してたりとか・・・
奢侈禁止令が出されても、それをかいくぐって、江戸小紋とか、裏地を赤にしたりして粋なものが流行ったりしているので、その辺のセンスとか根本から違うんでしょう。
気質というか文化というか古代でも、律令官人とかは、位によって衣服が違っていたり、甲冑・武具だって凝り始めたものが出てきたりしているんので、古代からの連綿とした積み重ねが歌舞伎に反映されたっていうのもあると思います。
奢侈禁止令が出されても、それをかいくぐって、江戸小紋とか、裏地を赤にしたりして粋なものが流行ったりしているので、その辺のセンスとか根本から違うんでしょう。
気質というか文化というか古代でも、律令官人とかは、位によって衣服が違っていたり、甲冑・武具だって凝り始めたものが出てきたりしているんので、古代からの連綿とした積み重ねが歌舞伎に反映されたっていうのもあると思います。
Posted by やま at 2016年05月22日 16:19
トラネコ様
なんでヒョウ柄が好まれるのかはナゾですねw
より目立ちたいからでしょうか。
皆が着てたら目立たなくなってますけど。
以前、インタビューに答えていた大阪のオバちゃんは
「似合うから来てるんやん」
と言ってましたがw
なんでヒョウ柄が好まれるのかはナゾですねw
より目立ちたいからでしょうか。
皆が着てたら目立たなくなってますけど。
以前、インタビューに答えていた大阪のオバちゃんは
「似合うから来てるんやん」
と言ってましたがw
Posted by きいろ香 at 2016年05月22日 18:26
トラネコ様
うさこ様
きいろ香様
横からすいません、大阪のオバチャンがヒョウ柄好きな件なのですが、ちょっと調べてみるといくつかの説が成り立つかと。
1. テレビの印象操作
そもそも、大阪のオバチャンはそこまでヒョウ柄を着ないという大阪の人もおられるそうです。印象操作といっても悪い意味ではなく、これは阪神タイガースの影響ではないかと、阪神タイガースの本境地は兵庫県なのですが、戦前や戦後には大阪タイガースというチーム名だったことがありますから、そこから、大阪=タイガース=虎=ヒョウ柄のようになったのかも? カーネルサンダースの呪いとかもありましたし。
2. きいろ香様の仰られるアッチ系の方
ヒョウ柄を心理学的にみると、自分自身の弱さを隠して空威張りをする傾向があるそうです。昔で言うとヤンキーとか今ではDQNですかね。そう考えると、アッチ系の方が戦後に入ってきて周りの日本人に空威張りするためにヒョウ柄を着たというのもありうるのかなあと。
3. 大阪の風土
大阪は昔、天下の台所と言われていたので商売として互いに競争が激しかったのではないかと、そのため「目立ちやすい」事が注目を集め商売が盛り上がる。という地が昔からあり、それが今のヒョウ柄に繋がったのかも?
偉そうに述べましたが、本当、どうしてなんでしょう。
後、大阪のオバチャンって白髪を紫とかに染める印象もあるんですが、これも大阪が多いのでしょうか? 私の周りはあまりいないのですが。
うさこ様
きいろ香様
横からすいません、大阪のオバチャンがヒョウ柄好きな件なのですが、ちょっと調べてみるといくつかの説が成り立つかと。
1. テレビの印象操作
そもそも、大阪のオバチャンはそこまでヒョウ柄を着ないという大阪の人もおられるそうです。印象操作といっても悪い意味ではなく、これは阪神タイガースの影響ではないかと、阪神タイガースの本境地は兵庫県なのですが、戦前や戦後には大阪タイガースというチーム名だったことがありますから、そこから、大阪=タイガース=虎=ヒョウ柄のようになったのかも? カーネルサンダースの呪いとかもありましたし。
2. きいろ香様の仰られるアッチ系の方
ヒョウ柄を心理学的にみると、自分自身の弱さを隠して空威張りをする傾向があるそうです。昔で言うとヤンキーとか今ではDQNですかね。そう考えると、アッチ系の方が戦後に入ってきて周りの日本人に空威張りするためにヒョウ柄を着たというのもありうるのかなあと。
3. 大阪の風土
大阪は昔、天下の台所と言われていたので商売として互いに競争が激しかったのではないかと、そのため「目立ちやすい」事が注目を集め商売が盛り上がる。という地が昔からあり、それが今のヒョウ柄に繋がったのかも?
偉そうに述べましたが、本当、どうしてなんでしょう。
後、大阪のオバチャンって白髪を紫とかに染める印象もあるんですが、これも大阪が多いのでしょうか? 私の周りはあまりいないのですが。
Posted by おしょう at 2016年05月22日 18:54
トラネコ様
インドは太古の文化超大国であり、数理的な素養を育む優れた土壌や建築文化があると思いますが、やはり熱い所で、激しい色や儀式や味を好む傾向があるように見受けられます。一度旅行に行ったときにも、かなり残酷な生贄の儀式を見せられて辟易いたしました。色に関しては、まあ好みと言われてしまえばそれまでですが、アジアの極彩色に何か五月蠅さを感じるのが私の感覚でしたのでお許し下さい。
しかし私の作品は、現実には、辰砂(≒ヴァーミリオン)を最も多く用いる絵が多いので、人肌の色とは血の色を反映していて当然と思っております。しかし、東洋画、あるいは東洋思想の上では、禅のようなぎりぎりまで彩色を抑えた趣味と、曼荼羅のような極彩色(阿頼耶識という深層領域)の趣味に大別できるのではないでしょうか。日本も両者が併存しますが、密教文化すらもアジアのそれに比べると極端な彩色やど派手な表現を抑えているように思います。
これは、西洋にも見られることであり、聖書の最後に出てくる黙示録やグノーシスといったものは、密教に通じる派手な象徴性があって、これが造形美術に具体化されれば、かなり派手なものになるでしょう。でも、その逆方向とのバランスで丁度よく成り立っているのが西洋文化のように思うのです。西洋の派手さには(私が感じるような)アジアの香辛料多使用でかえって一様化してしまう料理のような過剰さが少ないように思えるのですが・・・
インドは太古の文化超大国であり、数理的な素養を育む優れた土壌や建築文化があると思いますが、やはり熱い所で、激しい色や儀式や味を好む傾向があるように見受けられます。一度旅行に行ったときにも、かなり残酷な生贄の儀式を見せられて辟易いたしました。色に関しては、まあ好みと言われてしまえばそれまでですが、アジアの極彩色に何か五月蠅さを感じるのが私の感覚でしたのでお許し下さい。
しかし私の作品は、現実には、辰砂(≒ヴァーミリオン)を最も多く用いる絵が多いので、人肌の色とは血の色を反映していて当然と思っております。しかし、東洋画、あるいは東洋思想の上では、禅のようなぎりぎりまで彩色を抑えた趣味と、曼荼羅のような極彩色(阿頼耶識という深層領域)の趣味に大別できるのではないでしょうか。日本も両者が併存しますが、密教文化すらもアジアのそれに比べると極端な彩色やど派手な表現を抑えているように思います。
これは、西洋にも見られることであり、聖書の最後に出てくる黙示録やグノーシスといったものは、密教に通じる派手な象徴性があって、これが造形美術に具体化されれば、かなり派手なものになるでしょう。でも、その逆方向とのバランスで丁度よく成り立っているのが西洋文化のように思うのです。西洋の派手さには(私が感じるような)アジアの香辛料多使用でかえって一様化してしまう料理のような過剰さが少ないように思えるのですが・・・
Posted by 牛虎の金さん at 2016年05月22日 20:20
トラネコ様、皆様。
私は大阪生まれの大阪育ち。
こんなにマスコミ絡みで大阪イコール猥雑、大阪のシニア世代のおばさん叔父さんが言葉使いもどぎつく、服装も品がないケバイなんてなかったですよ。
おしょうさんが仰るマスコミの印象操作でしょうね。
きいろ香さんが仰るように、アッチ系の難民さんが大量に大阪目指して住み付いた事もあるのでしょうね。
調べた訳でもないですから。。断定できませんが。。
でも、私的にそうと思いますw
大阪(今で言う市内ですが)言葉は郊外の言葉は明らかに違います。
商売人は、はっきりした物言いをしなくてはビジネスが成り立ちません。
祖母は読み書きはひらがなオンリーでしたが、暗算めちゃくちや速かったです。
夫が大学生の時、シャープの電卓を家庭教師のバイトで買って来た時¥4000だったんですよ。
今や100均アイテムですよねww
私が思ったのは、ばあちゃんの頭は凄いでしたww
そんな大阪商人はどぎつい言葉使いしません。
吉本と、かの国の難民が大阪を汚したって思ってます。
口の悪い趣ミとしてどうなのかは、人の生き方として他人がとやかく言うべきとは思いませんが、あれが大阪の姿と思うのはどうでしょうかねw
私は大阪生まれの大阪育ち。
こんなにマスコミ絡みで大阪イコール猥雑、大阪のシニア世代のおばさん叔父さんが言葉使いもどぎつく、服装も品がないケバイなんてなかったですよ。
おしょうさんが仰るマスコミの印象操作でしょうね。
きいろ香さんが仰るように、アッチ系の難民さんが大量に大阪目指して住み付いた事もあるのでしょうね。
調べた訳でもないですから。。断定できませんが。。
でも、私的にそうと思いますw
大阪(今で言う市内ですが)言葉は郊外の言葉は明らかに違います。
商売人は、はっきりした物言いをしなくてはビジネスが成り立ちません。
祖母は読み書きはひらがなオンリーでしたが、暗算めちゃくちや速かったです。
夫が大学生の時、シャープの電卓を家庭教師のバイトで買って来た時¥4000だったんですよ。
今や100均アイテムですよねww
私が思ったのは、ばあちゃんの頭は凄いでしたww
そんな大阪商人はどぎつい言葉使いしません。
吉本と、かの国の難民が大阪を汚したって思ってます。
口の悪い趣ミとしてどうなのかは、人の生き方として他人がとやかく言うべきとは思いませんが、あれが大阪の姿と思うのはどうでしょうかねw
Posted by うさこ at 2016年05月22日 22:07
トラネコ様の政治と関係ないスレ、最近少ないですがわたしは結構気に入っています。
アメリカのあの色とりどりのカップケーキの写真、よくぞ出してくださいました。食べ物にああいう色を使う、という感覚は全くわかりません。つくづく思うのですがケーキのような西洋の食べ物さえ、見た目が非常に美しく繊細な日本のケーキが素晴らしいですね。誰の本か忘れましたが、「日本とフランスは美を物事の判断の基準にしている国だ」と書いてありました。私たちの主張しすぎない服装や言動も、それが他者と調和されて美しいと思うからかもしれないですね。
アメリカのあの色とりどりのカップケーキの写真、よくぞ出してくださいました。食べ物にああいう色を使う、という感覚は全くわかりません。つくづく思うのですがケーキのような西洋の食べ物さえ、見た目が非常に美しく繊細な日本のケーキが素晴らしいですね。誰の本か忘れましたが、「日本とフランスは美を物事の判断の基準にしている国だ」と書いてありました。私たちの主張しすぎない服装や言動も、それが他者と調和されて美しいと思うからかもしれないですね。
Posted by kabu at 2016年05月22日 22:39
おしょう様
うさこ様
テレビの影響は大きいかも知れませんね〜。
私も大阪ですが、実際周りでそうそうヒョウ柄のオバちゃんは見かけません。
どうやらあれは、某商店街界隈の、狭い範囲での状況らしいです。
その商店街にアニマル柄を多数扱っている婦人服店があるらしく、近所のオバちゃんたちが愛用しているようです。
そして、テレビがよく取材に行く商店街でもあるそうです。
そこのオバちゃんが着るヒョウ柄は、いわゆるヒョウ柄ではなく、ヒョウの絵が描いてあるヒョウ柄なんですけどねw
紫頭のオバちゃんも、たまに見る程度です。
「たまに見かける」というのが、全国的に見たら多いのかもしれませんがw
昔、学生の頃、ヤンキーと呼ばれるアホたちがよく「パチキ入れんぞ、ゴルァ〜!」と凄んでて、パチキって何?と思ってたんです。
後に友人から「頭突き」のことだと聞いて、なんでパチキっていうのか不思議だったんですけど、だいぶ後になってから、井筒和幸監督の映画「パッチギ」が公開されて謎が解けました。
チョン語じゃねーかと。
今思えば、ヤンキーの在コ率、高かったのかもしれません。
うさこ様
テレビの影響は大きいかも知れませんね〜。
私も大阪ですが、実際周りでそうそうヒョウ柄のオバちゃんは見かけません。
どうやらあれは、某商店街界隈の、狭い範囲での状況らしいです。
その商店街にアニマル柄を多数扱っている婦人服店があるらしく、近所のオバちゃんたちが愛用しているようです。
そして、テレビがよく取材に行く商店街でもあるそうです。
そこのオバちゃんが着るヒョウ柄は、いわゆるヒョウ柄ではなく、ヒョウの絵が描いてあるヒョウ柄なんですけどねw
紫頭のオバちゃんも、たまに見る程度です。
「たまに見かける」というのが、全国的に見たら多いのかもしれませんがw
昔、学生の頃、ヤンキーと呼ばれるアホたちがよく「パチキ入れんぞ、ゴルァ〜!」と凄んでて、パチキって何?と思ってたんです。
後に友人から「頭突き」のことだと聞いて、なんでパチキっていうのか不思議だったんですけど、だいぶ後になってから、井筒和幸監督の映画「パッチギ」が公開されて謎が解けました。
チョン語じゃねーかと。
今思えば、ヤンキーの在コ率、高かったのかもしれません。
Posted by きいろ香 at 2016年05月23日 08:33
うさこ様
きいろ香様
やはり、そうですか。
アッチ系の方とテレビの印象操作みたいですねえ。
私は大阪や東京だろうと良い所、悪い所があると思うのですが、大阪に入った外の人間がNo1を威張りたくて、テレビ局の在日が空威張りの為に大阪のオバチャン=ヒョウ柄なんて印象操作しようとか?
日本にヒョウ柄の動物ってイリオモテヤマネコとか小型の動物しかいないので、入ってくるとしたら大陸系ですよね。日本人が持ち込んだのではなくあちらの方が持ち込みだしたのかもしれませんね。
大阪=口が悪いの印象は吉本の影響は大きいでしょうね。誰とは言えませんが聞いているとちょっとなあ、と思う人もいますね。
ヒョウ柄模様ではなくヒョウの絵なんですね・・・それはインパクトがありそうww
きいろ香様
やはり、そうですか。
アッチ系の方とテレビの印象操作みたいですねえ。
私は大阪や東京だろうと良い所、悪い所があると思うのですが、大阪に入った外の人間がNo1を威張りたくて、テレビ局の在日が空威張りの為に大阪のオバチャン=ヒョウ柄なんて印象操作しようとか?
日本にヒョウ柄の動物ってイリオモテヤマネコとか小型の動物しかいないので、入ってくるとしたら大陸系ですよね。日本人が持ち込んだのではなくあちらの方が持ち込みだしたのかもしれませんね。
大阪=口が悪いの印象は吉本の影響は大きいでしょうね。誰とは言えませんが聞いているとちょっとなあ、と思う人もいますね。
ヒョウ柄模様ではなくヒョウの絵なんですね・・・それはインパクトがありそうww
Posted by おしょう at 2016年05月23日 13:18
トラ猫様
いやはや色彩感覚のお話仰る通り!以前モレシャンさんが仰ってました
3色以上の色使いはエレガントじゃないと。別におフランス好きではありませんが
フランス人のシックなセンスは脱帽ものです。そのフランス人がジャポネスクと言ってこぞって日本の浮世絵などからヒントを得て描いた絵画等は有名ですよね。
アールヌーボーも日本の美術様式なくしては成り立たなかったのでは。
中韓の色使いの品のなさは論外です。最もシノワズリーも流行したわけですから中国の文化も素晴らしいものがありますが色使いにかけては日本の右に出るものはないと思いますが?黒猫様と一緒で私も黒やグレーや藤色などのシックなカラーが基本です。それにアメリカのお菓子なんぞも食べられた代物ではありません。日本のわびさびに代表される茶道で使われる和菓子は繊細かつ抑えた色彩、正に和敬清寂の心意気です。それと黒猫様がのせられていた韓国の茶道?の写真、またまた思いだして笑っちゃいました。何しろ彼らが言うところの茶道は韓国起源らしいです。この写真がその韓国茶道の写真ですがお作法もへったくれもありません。魔法瓶でジャージャーとお湯を注ぐのですから、おまけに使っているのは日本の象印魔法瓶だそうです。
いやはや色彩感覚のお話仰る通り!以前モレシャンさんが仰ってました
3色以上の色使いはエレガントじゃないと。別におフランス好きではありませんが
フランス人のシックなセンスは脱帽ものです。そのフランス人がジャポネスクと言ってこぞって日本の浮世絵などからヒントを得て描いた絵画等は有名ですよね。
アールヌーボーも日本の美術様式なくしては成り立たなかったのでは。
中韓の色使いの品のなさは論外です。最もシノワズリーも流行したわけですから中国の文化も素晴らしいものがありますが色使いにかけては日本の右に出るものはないと思いますが?黒猫様と一緒で私も黒やグレーや藤色などのシックなカラーが基本です。それにアメリカのお菓子なんぞも食べられた代物ではありません。日本のわびさびに代表される茶道で使われる和菓子は繊細かつ抑えた色彩、正に和敬清寂の心意気です。それと黒猫様がのせられていた韓国の茶道?の写真、またまた思いだして笑っちゃいました。何しろ彼らが言うところの茶道は韓国起源らしいです。この写真がその韓国茶道の写真ですがお作法もへったくれもありません。魔法瓶でジャージャーとお湯を注ぐのですから、おまけに使っているのは日本の象印魔法瓶だそうです。
Posted by マルガリータ at 2016年05月23日 14:16
うさこ様
そうですね、大阪人と言ってもいろんな人がいるわけで、みんなが皆下卑た方言をまくしたてるドラマのような会話はしませんもんね。ただ大阪人というか関西系は他地域に移住しても方言は変えない傾向がありますから、他県民には強烈な印象があるのでしょうね。 まあマスゴミが作る印象操作の影響はあるとは思います。
kabu様
どうも有難うございます。
私も政治よりも文科系の雑談がすきなんですよね(笑)
アメリカの文化的特徴の背景に、大量生産・大量消費型社会というのがあります。つまり生活に関するすべてが人工物の世界という奴です。あのケーキのケバい色なども自然を遙かに無視した人工物系の色です。こういう感性がアメリカ人の安っぽい趣味に繋がるのかなと思います。
ご指摘のフランス的美意識は日本美術を受け入れたジャポニズムも始め、相撲好きや歌舞伎好きの文化的マニアもいるようですね。まあ一般に西欧人は日本人の美意識と通じるものはあるようです。
マルガリータ様
同意です。
印象派もアールヌーボーも象徴主義も・・・みんな日本の江戸美術がなければ、生まれてこなかったものばかりです。それを認め受け入れる感性がフランス人にはあったということですね。そういえば、フランス料理も日本の懐石料理のコンセプトを取り入れているといわれます。まあ美意識が共通している面もあるんでしょうね。そういえばスェーデン料理?なんてのも懐石そのもので器に凝ったりしていましたっけ・・・。
そうですね、大阪人と言ってもいろんな人がいるわけで、みんなが皆下卑た方言をまくしたてるドラマのような会話はしませんもんね。ただ大阪人というか関西系は他地域に移住しても方言は変えない傾向がありますから、他県民には強烈な印象があるのでしょうね。 まあマスゴミが作る印象操作の影響はあるとは思います。
kabu様
どうも有難うございます。
私も政治よりも文科系の雑談がすきなんですよね(笑)
アメリカの文化的特徴の背景に、大量生産・大量消費型社会というのがあります。つまり生活に関するすべてが人工物の世界という奴です。あのケーキのケバい色なども自然を遙かに無視した人工物系の色です。こういう感性がアメリカ人の安っぽい趣味に繋がるのかなと思います。
ご指摘のフランス的美意識は日本美術を受け入れたジャポニズムも始め、相撲好きや歌舞伎好きの文化的マニアもいるようですね。まあ一般に西欧人は日本人の美意識と通じるものはあるようです。
マルガリータ様
同意です。
印象派もアールヌーボーも象徴主義も・・・みんな日本の江戸美術がなければ、生まれてこなかったものばかりです。それを認め受け入れる感性がフランス人にはあったということですね。そういえば、フランス料理も日本の懐石料理のコンセプトを取り入れているといわれます。まあ美意識が共通している面もあるんでしょうね。そういえばスェーデン料理?なんてのも懐石そのもので器に凝ったりしていましたっけ・・・。
Posted by トラネコ at 2016年05月23日 19:50
at 2016年05月23日 19:50
 at 2016年05月23日 19:50
at 2016年05月23日 19:50トラ猫様
大変申し訳ありませんでした。コメント中2回もトラ猫様を黒猫様と書いてしまいました。軽い認知症かもしれません。お許しを!
大変申し訳ありませんでした。コメント中2回もトラ猫様を黒猫様と書いてしまいました。軽い認知症かもしれません。お許しを!
Posted by マルガリータ at 2016年05月24日 20:53
マルガリータ様
了解!
了解!
Posted by トラネコ at 2016年05月24日 21:06
at 2016年05月24日 21:06
 at 2016年05月24日 21:06
at 2016年05月24日 21:06トラネコ様
22歳頃、東京に旅行に行って、山手線乗ってた時、普通に関西弁で喋ってたんですが、向こうのサラリーマン風な人が、物珍しそうに私達の事見てて、
あの子ら関西人なのね。
一人のサラリーマンが惜しいよね、喋り方が~って。
私は、そうでっか!みたいな喋り方しません。
ですが、大阪イントネーションは愛してますから、何処に行っても関西弁は使うつもりです。
自分の生まれ育ったあらゆる物は言葉であろうが大切にしたいです。
私は方言は好きです。
でも今の大阪言葉が日本人から嫌われてるのは、日本人から離れてる言葉でしょうね。
女性が大口開けてうまいうまいって言うのも嫌です。
テレビを見なければそんな低俗な人みなくても言い訳ですからね。
でも、トラネコさんが仰る様に関西人が自分の方言を使い続ける事に非難して欲しくないです。
私は方言に対していいなぁ~って思います。
もっと聞きたいって思います。
なのに、なぜ?大阪弁は聞きたくない方言なん?
多分、攻撃的な物言いが他県の人には。。
でも大阪弁は他県の人が関わりたくないって言葉使いではないです。
22歳頃、東京に旅行に行って、山手線乗ってた時、普通に関西弁で喋ってたんですが、向こうのサラリーマン風な人が、物珍しそうに私達の事見てて、
あの子ら関西人なのね。
一人のサラリーマンが惜しいよね、喋り方が~って。
私は、そうでっか!みたいな喋り方しません。
ですが、大阪イントネーションは愛してますから、何処に行っても関西弁は使うつもりです。
自分の生まれ育ったあらゆる物は言葉であろうが大切にしたいです。
私は方言は好きです。
でも今の大阪言葉が日本人から嫌われてるのは、日本人から離れてる言葉でしょうね。
女性が大口開けてうまいうまいって言うのも嫌です。
テレビを見なければそんな低俗な人みなくても言い訳ですからね。
でも、トラネコさんが仰る様に関西人が自分の方言を使い続ける事に非難して欲しくないです。
私は方言に対していいなぁ~って思います。
もっと聞きたいって思います。
なのに、なぜ?大阪弁は聞きたくない方言なん?
多分、攻撃的な物言いが他県の人には。。
でも大阪弁は他県の人が関わりたくないって言葉使いではないです。
Posted by うさこ at 2016年05月24日 23:01
うさこ様
同意です。
方言はそれこそ地方文化の代表です。
近年の情報通信の発達により方言が廃れて行っているのも事実です。これは全国的な傾向ですが、関西方言はいっこうに廃れることはなさそうです。また芸能界でもわかりますが、関西人の多くは地元を離れても方言を直しません。これは関西人の文化的矜持というか自信の現れじゃないかと思います。ただ方言というよりも強引さの背景のある言葉遣いは、あまりよい印象は持たれないでしょうね。ここは方言とは関係なく気質の問題だと思います。
同意です。
方言はそれこそ地方文化の代表です。
近年の情報通信の発達により方言が廃れて行っているのも事実です。これは全国的な傾向ですが、関西方言はいっこうに廃れることはなさそうです。また芸能界でもわかりますが、関西人の多くは地元を離れても方言を直しません。これは関西人の文化的矜持というか自信の現れじゃないかと思います。ただ方言というよりも強引さの背景のある言葉遣いは、あまりよい印象は持たれないでしょうね。ここは方言とは関係なく気質の問題だと思います。
Posted by トラネコ at 2016年05月27日 10:11
at 2016年05月27日 10:11
 at 2016年05月27日 10:11
at 2016年05月27日 10:11