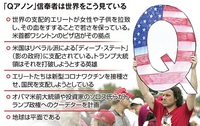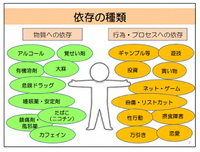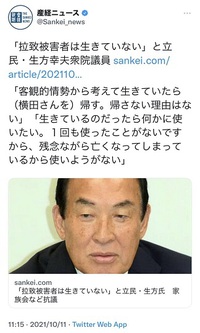21世紀における宗教の役割 後編
2019年05月09日
最初に私の宗教的立場を述べておく。念のため。
私は以前から述べてきたように、ごく一般の日本人と同じく、
特定の宗派、教団に帰依した者ではないが無神論者ではない。
神かどうかわからないが目に見えない精神的な存在を畏れる者だ。
一応このことを念頭にお読みいただきたい。

>宗教が社会でより大きな役割を果たすのが望ましいと考える人の割合が
最も高かったのはインドネシア(85%)で、ケニア(74%)、
ナイジェリア(74%)、チュニジア(69%)が続いた。
>宗教が社会でより大きな役割を果たすのが望ましいと
考える人の割合が最も低かったのは日本(15%)で、次いでスウェーデン(20%)、
スペイン(23%)、フランス(24%)が低かった。
とても興味深い数字である。
この数字の違いは、先進国と途上国という生活レベルの差異
多神教と一神教との差異、キリスト教とイスラム教の差異とも見られるが、
どの観点で分析するかで、その結果は異なってくるだろう。
私は一神教と多神教の違いに注目する。
さらに言うと、教条主義宗教か、教義のない宗教かである。
キリスト教は完全なドグマ宗教であり、神道は教義がない。
もっとも・・・
教祖も教義も布教団体もない神道が宗教か否かという議論さえあるが、
一応便宜上、ここでは宗教を論じる上で神道も日本人の宗教という立場をとる。
宗教が社会で大きな役割を果たすべきだと考える国民で、
その割合が低いのが日本、スェーデン、スペイン・・・など欧州なのは、
日本では無意識の神道「信仰」が定着しており、欧州では前回述べた、
宗教の弊害を痛いほど歴史的に経験した地域という理由があろう。

宗教の社会的役割といえば・・・
西欧の一神教は社会及び人間の道徳を説く役割もあったが、
日本では儒教がその役目を持ち、神道は自然と先祖を尊ぶ習俗であった。
そういう意味からも日本でキリスト教など一神教は国民性に合わない。
キリスト教禁止令が解禁(1899)され、各地に教会が建ち宣教師も多く来日し、
ミッションスクールもたくさん出来てきても、未だ100万人の信者は増えない。
あれから120年たっても、キリスト教徒は人口の1%しかいないのはなぜか?
日本には既に八百万の神々が生活すべてに定着しすぎている証拠である。
神道は祖霊崇拝と御霊崇拝が基本でその先に皇室崇拝があるのだが、
これは意識しようがしまいが、空気みたいに当たり前になりすぎているのである。
上述のように日本では、キリスト教の道徳性は古くから儒教が担っていたし、
儒教から支配者層の道徳律が後の武士道へと発展していったわけだ。
人生観や死生観については仏教が鎌倉時代以降その役を担ってきたので、
わざわざ日本人は西欧の「神との契約」など結ぶ必要性はないのである。

日本人の宗教観には「神との契約」という概念がない
だから・・・
お盆には帰省ラッシュがあり、正月には何百万人も初詣に行くし、
初日の出を拝んだり、地域の神社が代々氏子に引き継がれるし、
天皇の代替わり、新元号にも多くの人々がそれを祝うのである。
こんなことを無神論者がするわけがないのである。
日本人は無宗教だというが無神論者では決してない。
一神教というドグマ宗教観でみるから無神論に見えるだけである。
日本人はわざわざ神を意識しなくても自然に感じる感性もあると思う。
それが私がよく引用する西行法師の歌に現れていると思う。
<参考エントリ>
一神教圏の人には日本は多神教と答えればよい。
https://ryotaroneko.ti-da.net/e9017436.html

神=目に見えない畏敬の存在は
何となく感じるだけでいいのだ。
個人的には宗教心は重要だと考えるが、在来・新興宗教問わず、
21世紀の社会には宗教心は必要だが宗教団体は不要になり、
というより、宗教団体は有害な存在なので無くすべきではないかと考えている。
仏教僧侶が生臭坊主といわれて久しいが、坊主を聖人などと思う人は皆無だ。
また同性愛者や小児性愛者の多いカトリック神父も既に俗人の集まりであるし、
プロテスタント系でも西早稲田に巣食うようないかがわしい牧師や教会は少なくない。
イスラム教はあまりにも前近代的な黴臭さと教条主義的な危険性があり、
日本人の精神風土にはキリスト教以上になじめない異質な宗教である。
さらにユダヤ教などはまったく日本には縁がない。

一方・・・
神道は基本的に祖霊崇拝、御霊崇拝、自然崇拝で成り立つ。
そこには教祖も一切の教義(ドグマ)も布教活動も存在しない。
恐らくユングのいう集合的無意識が日本人の神道観であろう。
つまり民族の共通の巨大な意識に神道があるのである。
それは外来の仏教をも飲み込み神仏習合してしまったのだ。
もっとも神道は教義がないから仏教と融合しやすかったとも言えるが。
神道には教義がない上に、英雄的指導者=カリスマもいない。
宗教(団体)にカリスマ的教祖がいないことは実は大きな意味がある。
一神教のように宗教が権力化や戦争・テロに発展することがないのである。
だから日本には仏教系宗派は乱立して論争もあったが、
一度として宗教戦争に発展したことはなかったのである。
これは宗教戦争を繰り返してきた欧州とは注目すべき点である。

神道は排他的一神教徒さえも受け入れる。
カリスマを必要とする人は依存心が強く自立心がないのである。
カリスマに傾倒することで導かれたいという他者依存の精神は、
排他的で攻撃的なカルトへと盲目的に傾倒しやすくする危険性がある。
これが宗教戦争やオウム事件のようなテロ組織化する原因にもなっている。
神道はカリスマ教祖も教義もないから、何かの目的に向かう組織体になりえない。
また八百万の神々は生活すべての事象に宿っておられるので信仰の場所を選ばない。
つまり・・・
多神教はあらゆる神々が日常の物象すべてに存在するという概念だから、
一神教のように特定の神を優遇したり、異教の神を排斥することもないし、
さらにすべての神々に平等に敬意と畏れを抱くから自然や社会を破壊しない。

日本はいたるところに遍く神々がおわします国である。
そろそろ結論だが・・・
21世紀の宗教の在り方として私はこう思う。
宗教の弊害を歴史的に経験し熟知してきた欧州人のキリスト教離れは、
ある意味、自然保護、人権運動、男女平等・・・などキリスト教に反発する、
或いは、キリスト教の反省から発生した近代の啓蒙運動と捉えることができる。
キリスト教はその歴史的役割の終焉にきている。
私は宗教とは、誤解を恐れずにいえば一種の人生哲学だと思う。
人の生き方や死生観を説き、生きるべき指針を示す人生ガイドである。
だからいろいろな教えや考え方があってもかまわないのだ。
このことはちょうど江戸時代の石田梅岩の石門心学と同じだ。
心学は商売人の心構えを説いたものだが、これも一種の哲学書で、
どんな宗教でもかまわないから一途に心を磨くことが大事だと説く。
宗教など専門家以外の個人はその程度の捉え方で十分である。
これが教団を作り出すと、ロクな事がないのが歴史の教訓である。
それに宗教教団など神や仏とはまったく関係ない俗人の集まりに過ぎないのだから。

石門心学を説いた石田梅岩
人の生き方は現実を見据え合理的に生きるべきと考えるが、
その精神的支えを宗教が行うことには何ら反対しないし、むしろ、
目に見えない何かを畏れる心がないと人間は傲慢になると思う
しかし宗教が団体化すると本来の教えとは真逆な、
金銭欲、権力欲、名声欲、排他性、独善性・・・など、
ドロドロの俗人の世界にまみれることは歴史の事実だ。
宗教によって心が解放され自由になるというのは、
個々人が切磋琢磨して心を磨いた結果そうなるのであって、
宗教団体に入って活動すれば逆に心は拘束されるのである。

日本はいろんな神々のおわします国である。
だから仲良く共存する思想が根底にあるのだ。
宗教団体に所属すれば、献金や不況活動など強制的義務を負わされる。
それも宗教的脅迫(実践しないと罰が下るとか天国に行けないとか)と、
打算(自分は神に選ばれし者、天国の切符貰える♪)で活動するのである。
宗教=信仰とは個人的なものに過ぎない
自分が謙虚に信じ生活すればいいだけである。
他人に勧めるのはいいが強制はいけない。
如何に偉大な宗教でも個々人の心の問題に過ぎないと喝破したのは、
ドイツ観念論のインマニュエル・カントであるが、まさにこれだ。
宗教心は生きるための心の糧になるが、宗教団体は弊害しかない。
宗教団体は崩壊し宗教心だけが残る。

「いかなる偉大な宗教でも私事である。」
・・・by インマヌエル・カント
水瓶座の時代というのをご存じだろうか?
この時代は宗教団体や教会など世俗的権威主義から人間が解放され、
個々人の価値観や自主性を尊重し合うと同時に、自立した個の確立を目指し、
平和共存と人間尊重の時代になるといわれている。
つまり21世紀からは宗教は必要ない時代になるのである。
具体的には宗教的権威や団体の消滅が進むのではないだろうか?
しかし個々人の心の中には超越的真理(神といってもよいが)は存在し続ける。
すべての人々の心は神につながっているのである。
神とは大宇宙の意識というか、目に見えない崇高、荘厳な存在であるが、
それをGodと呼ぶか、ブラーフマン、梵天と呼ぶか、大日如来と呼ぶか、
エホバ、ヤーヴェ、アッラー・・・なんでもいいのだ。
個々人が心の内に「神」を持つという事は自立した人間になるという事である。
外に神を求めるからおかしな宗教に騙され利用され自縄自縛になるのである。
各人が心に神を持つ時代が水瓶座の時代なのである。

アクエリアス【訳詞付】- The Fifth Dimension



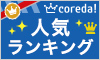

私は以前から述べてきたように、ごく一般の日本人と同じく、
特定の宗派、教団に帰依した者ではないが無神論者ではない。
神かどうかわからないが目に見えない精神的な存在を畏れる者だ。
一応このことを念頭にお読みいただきたい。

>宗教が社会でより大きな役割を果たすのが望ましいと考える人の割合が
最も高かったのはインドネシア(85%)で、ケニア(74%)、
ナイジェリア(74%)、チュニジア(69%)が続いた。
>宗教が社会でより大きな役割を果たすのが望ましいと
考える人の割合が最も低かったのは日本(15%)で、次いでスウェーデン(20%)、
スペイン(23%)、フランス(24%)が低かった。
とても興味深い数字である。
この数字の違いは、先進国と途上国という生活レベルの差異
多神教と一神教との差異、キリスト教とイスラム教の差異とも見られるが、
どの観点で分析するかで、その結果は異なってくるだろう。
私は一神教と多神教の違いに注目する。
さらに言うと、教条主義宗教か、教義のない宗教かである。
キリスト教は完全なドグマ宗教であり、神道は教義がない。
もっとも・・・
教祖も教義も布教団体もない神道が宗教か否かという議論さえあるが、
一応便宜上、ここでは宗教を論じる上で神道も日本人の宗教という立場をとる。
宗教が社会で大きな役割を果たすべきだと考える国民で、
その割合が低いのが日本、スェーデン、スペイン・・・など欧州なのは、
日本では無意識の神道「信仰」が定着しており、欧州では前回述べた、
宗教の弊害を痛いほど歴史的に経験した地域という理由があろう。

宗教の社会的役割といえば・・・
西欧の一神教は社会及び人間の道徳を説く役割もあったが、
日本では儒教がその役目を持ち、神道は自然と先祖を尊ぶ習俗であった。
そういう意味からも日本でキリスト教など一神教は国民性に合わない。
キリスト教禁止令が解禁(1899)され、各地に教会が建ち宣教師も多く来日し、
ミッションスクールもたくさん出来てきても、未だ100万人の信者は増えない。
あれから120年たっても、キリスト教徒は人口の1%しかいないのはなぜか?
日本には既に八百万の神々が生活すべてに定着しすぎている証拠である。
神道は祖霊崇拝と御霊崇拝が基本でその先に皇室崇拝があるのだが、
これは意識しようがしまいが、空気みたいに当たり前になりすぎているのである。
上述のように日本では、キリスト教の道徳性は古くから儒教が担っていたし、
儒教から支配者層の道徳律が後の武士道へと発展していったわけだ。
人生観や死生観については仏教が鎌倉時代以降その役を担ってきたので、
わざわざ日本人は西欧の「神との契約」など結ぶ必要性はないのである。

日本人の宗教観には「神との契約」という概念がない
だから・・・
お盆には帰省ラッシュがあり、正月には何百万人も初詣に行くし、
初日の出を拝んだり、地域の神社が代々氏子に引き継がれるし、
天皇の代替わり、新元号にも多くの人々がそれを祝うのである。
こんなことを無神論者がするわけがないのである。
日本人は無宗教だというが無神論者では決してない。
一神教というドグマ宗教観でみるから無神論に見えるだけである。
日本人はわざわざ神を意識しなくても自然に感じる感性もあると思う。
それが私がよく引用する西行法師の歌に現れていると思う。
<参考エントリ>
一神教圏の人には日本は多神教と答えればよい。
https://ryotaroneko.ti-da.net/e9017436.html

神=目に見えない畏敬の存在は
何となく感じるだけでいいのだ。
個人的には宗教心は重要だと考えるが、在来・新興宗教問わず、
21世紀の社会には宗教心は必要だが宗教団体は不要になり、
というより、宗教団体は有害な存在なので無くすべきではないかと考えている。
仏教僧侶が生臭坊主といわれて久しいが、坊主を聖人などと思う人は皆無だ。
また同性愛者や小児性愛者の多いカトリック神父も既に俗人の集まりであるし、
プロテスタント系でも西早稲田に巣食うようないかがわしい牧師や教会は少なくない。
イスラム教はあまりにも前近代的な黴臭さと教条主義的な危険性があり、
日本人の精神風土にはキリスト教以上になじめない異質な宗教である。
さらにユダヤ教などはまったく日本には縁がない。

一方・・・
神道は基本的に祖霊崇拝、御霊崇拝、自然崇拝で成り立つ。
そこには教祖も一切の教義(ドグマ)も布教活動も存在しない。
恐らくユングのいう集合的無意識が日本人の神道観であろう。
つまり民族の共通の巨大な意識に神道があるのである。
それは外来の仏教をも飲み込み神仏習合してしまったのだ。
もっとも神道は教義がないから仏教と融合しやすかったとも言えるが。
神道には教義がない上に、英雄的指導者=カリスマもいない。
宗教(団体)にカリスマ的教祖がいないことは実は大きな意味がある。
一神教のように宗教が権力化や戦争・テロに発展することがないのである。
だから日本には仏教系宗派は乱立して論争もあったが、
一度として宗教戦争に発展したことはなかったのである。
これは宗教戦争を繰り返してきた欧州とは注目すべき点である。

神道は排他的一神教徒さえも受け入れる。
カリスマを必要とする人は依存心が強く自立心がないのである。
カリスマに傾倒することで導かれたいという他者依存の精神は、
排他的で攻撃的なカルトへと盲目的に傾倒しやすくする危険性がある。
これが宗教戦争やオウム事件のようなテロ組織化する原因にもなっている。
神道はカリスマ教祖も教義もないから、何かの目的に向かう組織体になりえない。
また八百万の神々は生活すべての事象に宿っておられるので信仰の場所を選ばない。
つまり・・・
多神教はあらゆる神々が日常の物象すべてに存在するという概念だから、
一神教のように特定の神を優遇したり、異教の神を排斥することもないし、
さらにすべての神々に平等に敬意と畏れを抱くから自然や社会を破壊しない。

日本はいたるところに遍く神々がおわします国である。
そろそろ結論だが・・・
21世紀の宗教の在り方として私はこう思う。
宗教の弊害を歴史的に経験し熟知してきた欧州人のキリスト教離れは、
ある意味、自然保護、人権運動、男女平等・・・などキリスト教に反発する、
或いは、キリスト教の反省から発生した近代の啓蒙運動と捉えることができる。
キリスト教はその歴史的役割の終焉にきている。
私は宗教とは、誤解を恐れずにいえば一種の人生哲学だと思う。
人の生き方や死生観を説き、生きるべき指針を示す人生ガイドである。
だからいろいろな教えや考え方があってもかまわないのだ。
このことはちょうど江戸時代の石田梅岩の石門心学と同じだ。
心学は商売人の心構えを説いたものだが、これも一種の哲学書で、
どんな宗教でもかまわないから一途に心を磨くことが大事だと説く。
宗教など専門家以外の個人はその程度の捉え方で十分である。
これが教団を作り出すと、ロクな事がないのが歴史の教訓である。
それに宗教教団など神や仏とはまったく関係ない俗人の集まりに過ぎないのだから。

石門心学を説いた石田梅岩
人の生き方は現実を見据え合理的に生きるべきと考えるが、
その精神的支えを宗教が行うことには何ら反対しないし、むしろ、
目に見えない何かを畏れる心がないと人間は傲慢になると思う
しかし宗教が団体化すると本来の教えとは真逆な、
金銭欲、権力欲、名声欲、排他性、独善性・・・など、
ドロドロの俗人の世界にまみれることは歴史の事実だ。
宗教によって心が解放され自由になるというのは、
個々人が切磋琢磨して心を磨いた結果そうなるのであって、
宗教団体に入って活動すれば逆に心は拘束されるのである。

日本はいろんな神々のおわします国である。
だから仲良く共存する思想が根底にあるのだ。
宗教団体に所属すれば、献金や不況活動など強制的義務を負わされる。
それも宗教的脅迫(実践しないと罰が下るとか天国に行けないとか)と、
打算(自分は神に選ばれし者、天国の切符貰える♪)で活動するのである。
宗教=信仰とは個人的なものに過ぎない
自分が謙虚に信じ生活すればいいだけである。
他人に勧めるのはいいが強制はいけない。
如何に偉大な宗教でも個々人の心の問題に過ぎないと喝破したのは、
ドイツ観念論のインマニュエル・カントであるが、まさにこれだ。
宗教心は生きるための心の糧になるが、宗教団体は弊害しかない。
宗教団体は崩壊し宗教心だけが残る。

「いかなる偉大な宗教でも私事である。」
・・・by インマヌエル・カント
水瓶座の時代というのをご存じだろうか?
この時代は宗教団体や教会など世俗的権威主義から人間が解放され、
個々人の価値観や自主性を尊重し合うと同時に、自立した個の確立を目指し、
平和共存と人間尊重の時代になるといわれている。
つまり21世紀からは宗教は必要ない時代になるのである。
具体的には宗教的権威や団体の消滅が進むのではないだろうか?
しかし個々人の心の中には超越的真理(神といってもよいが)は存在し続ける。
すべての人々の心は神につながっているのである。
神とは大宇宙の意識というか、目に見えない崇高、荘厳な存在であるが、
それをGodと呼ぶか、ブラーフマン、梵天と呼ぶか、大日如来と呼ぶか、
エホバ、ヤーヴェ、アッラー・・・なんでもいいのだ。
個々人が心の内に「神」を持つという事は自立した人間になるという事である。
外に神を求めるからおかしな宗教に騙され利用され自縄自縛になるのである。
各人が心に神を持つ時代が水瓶座の時代なのである。

アクエリアス【訳詞付】- The Fifth Dimension



Posted by トラネコ at 00:00│Comments(14)
│思想・宗教
この記事へのコメント
パヨクの場合、現行憲法が信仰の対象なんでしょうね。
http://blog.livedoor.jp/nanyade/archives/18168698.html
「日米チイキョウテイガー」と腐しておいて、その一方で日本の軍事的自立は必死で潰そうとする。この矛盾に気付かずに「ウヨはアメポチ」と罵るパヨクカルト信者こそ「究極のアメポチ」ですね。
「鰯の頭も信心から」と言いますが、宗教以外の事物も信仰の対象になり得るのかもしれません。
http://blog.livedoor.jp/nanyade/archives/18168698.html
「日米チイキョウテイガー」と腐しておいて、その一方で日本の軍事的自立は必死で潰そうとする。この矛盾に気付かずに「ウヨはアメポチ」と罵るパヨクカルト信者こそ「究極のアメポチ」ですね。
「鰯の頭も信心から」と言いますが、宗教以外の事物も信仰の対象になり得るのかもしれません。
Posted by KOBA at 2019年05月09日 04:03
KOBA様
地井協定の運用については各国の事情は異なりますが、在欧州米軍と日本の決定的違いは、安保条約の在り方でしょう。欧州は双務的で対等のNATO条約ですが、日本は片務的な保護性のつよい条約。ここに不平等がある以上地位協定にも不平等は生じるでしょう。つまり日本が自主防衛できずアメリカの安保属国にあり主権独立国家として機能していないからです。地位協定が不満なら自主防衛を進め安保の世話にならないようにすべきです。或いは対等な条約にすべきですね。
地井協定の運用については各国の事情は異なりますが、在欧州米軍と日本の決定的違いは、安保条約の在り方でしょう。欧州は双務的で対等のNATO条約ですが、日本は片務的な保護性のつよい条約。ここに不平等がある以上地位協定にも不平等は生じるでしょう。つまり日本が自主防衛できずアメリカの安保属国にあり主権独立国家として機能していないからです。地位協定が不満なら自主防衛を進め安保の世話にならないようにすべきです。或いは対等な条約にすべきですね。
Posted by トラネコ at 2019年05月09日 18:03
at 2019年05月09日 18:03
 at 2019年05月09日 18:03
at 2019年05月09日 18:03しばらく前の欧米など (一神教文化圏)では、あなたの宗教は何か、と訊かれ、日本人が「特にない」と言うと、それじゃ動物と同じだ、と言われたらしいです。
たぶん、欧米人や一神教の人々は(動物のように?)ただ生きる、ということが難しいのかもしれません。この世界が何なのか、自分は何なのか、あるいは世界は何のためにあるのか、自分は何のために生きているのか、それらがわからない、ということが、人間にとっては「不安」であって、その不安を解消する術が宗教だったのかもしれません。
たしかにこれが、近代科学その他の、自然や社会の分析や理解に役立ち、今日の西欧化された学問の元になっているのは事実です(かつてのイスラムも同様の理由で優れた学術をもっていました)。以前述べたように、神が数学で宇宙を運営してると信じたニュートン力学は、一神教の勝利と言って差し支えないでしょう。そうした観点から、唯一神を、自然の唯一の真理である物質とその法則に置き換えたのが唯物論であり、近代科学の基礎となる「唯物」も、まさに一神教の原理です(ちなみにマルクスの唯物史観はこれを歴史や経済に強引に当てはめた頓珍漢なインチキ宗教ですが)。
ただ、彼らのパラダイム、あるいはその根底にある、世界の不明性に対する「不安」という問題意識は、一時的には有用であっても、いささか強引すぎるきらいがあります。なぜなら、これこそカルト宗教がつけ込む、人間心理のスキだからです。
以前のべた、ジョジョの奇妙な冒険という漫画の悪の大ボスのディオ(イタリア語で神の意味)の、人間の目的は安心を得ることだ、わたしに仕えるだけで、すべての安心が簡単に手に入るぞ、という誘惑に、この種の不安を抱いた、自信が哲学者でもない人々は、いともかんたんに飛び付き、ディオに支配されて、ドグマにひれ伏し、司祭が言えば何でもやるように洗脳されてしまうからです。
私は彼ら(欧米人)と話していて、その不安からくるバカげた断定をしばしば耳にしてきたので、それがよくわかります(たとえば、神が人間を作ったのでない以上、進化論が正しいのは明らかなことだ、という、阿保なお笑い議論を糞まじめにしてくるのです)。要するに、彼らは、本質的にわからない、ということを認めたくない、というか、認めると恐怖に襲われるらしいのです。
たぶんこれが、ニーチェの言う、真理至上主義としての一神教の原理だと、私は思います。
一方で、我々日本人のような、多神教はその対極にあるようです。ただ、日本でも、カルト主教が、人々の不安や不満を煽り、上記のディオ様のような言い方をして、金と欲のために大衆を利用していることは、言うまでもありません。
私の個人的断定的な定義では、多神教とは複数の原理を認め、世界や自分に対する不可知性を認めて、それを何とも思わず、謙虚に未知のものも尊重しながら生きていける自由な精神のことです。これは、まったく動物的なことでも不道徳なことでもありません。カルト信者からは、動物的だと思われるのかもしれませんが、それは彼らが不安という病気にかかり、なおかつそれを狂信埋める、安易な人々だからにすぎません。
たぶん、欧米人や一神教の人々は(動物のように?)ただ生きる、ということが難しいのかもしれません。この世界が何なのか、自分は何なのか、あるいは世界は何のためにあるのか、自分は何のために生きているのか、それらがわからない、ということが、人間にとっては「不安」であって、その不安を解消する術が宗教だったのかもしれません。
たしかにこれが、近代科学その他の、自然や社会の分析や理解に役立ち、今日の西欧化された学問の元になっているのは事実です(かつてのイスラムも同様の理由で優れた学術をもっていました)。以前述べたように、神が数学で宇宙を運営してると信じたニュートン力学は、一神教の勝利と言って差し支えないでしょう。そうした観点から、唯一神を、自然の唯一の真理である物質とその法則に置き換えたのが唯物論であり、近代科学の基礎となる「唯物」も、まさに一神教の原理です(ちなみにマルクスの唯物史観はこれを歴史や経済に強引に当てはめた頓珍漢なインチキ宗教ですが)。
ただ、彼らのパラダイム、あるいはその根底にある、世界の不明性に対する「不安」という問題意識は、一時的には有用であっても、いささか強引すぎるきらいがあります。なぜなら、これこそカルト宗教がつけ込む、人間心理のスキだからです。
以前のべた、ジョジョの奇妙な冒険という漫画の悪の大ボスのディオ(イタリア語で神の意味)の、人間の目的は安心を得ることだ、わたしに仕えるだけで、すべての安心が簡単に手に入るぞ、という誘惑に、この種の不安を抱いた、自信が哲学者でもない人々は、いともかんたんに飛び付き、ディオに支配されて、ドグマにひれ伏し、司祭が言えば何でもやるように洗脳されてしまうからです。
私は彼ら(欧米人)と話していて、その不安からくるバカげた断定をしばしば耳にしてきたので、それがよくわかります(たとえば、神が人間を作ったのでない以上、進化論が正しいのは明らかなことだ、という、阿保なお笑い議論を糞まじめにしてくるのです)。要するに、彼らは、本質的にわからない、ということを認めたくない、というか、認めると恐怖に襲われるらしいのです。
たぶんこれが、ニーチェの言う、真理至上主義としての一神教の原理だと、私は思います。
一方で、我々日本人のような、多神教はその対極にあるようです。ただ、日本でも、カルト主教が、人々の不安や不満を煽り、上記のディオ様のような言い方をして、金と欲のために大衆を利用していることは、言うまでもありません。
私の個人的断定的な定義では、多神教とは複数の原理を認め、世界や自分に対する不可知性を認めて、それを何とも思わず、謙虚に未知のものも尊重しながら生きていける自由な精神のことです。これは、まったく動物的なことでも不道徳なことでもありません。カルト信者からは、動物的だと思われるのかもしれませんが、それは彼らが不安という病気にかかり、なおかつそれを狂信埋める、安易な人々だからにすぎません。
Posted by 艮の金さん at 2019年05月09日 21:02
日本人の当たり前な日常生活の中に、有難い、罰当たり、ご先祖さんに顔向け出来ない恥知らずな言動、おてんとうさんがしっかり見てはるんや、ちゃんと生きなアカン!みたいな教えと言うには大袈裟かも知れないですが、そんな人としてして、して良い事悪い事を戒める言葉が日常的な言葉としてあったと思います。 ご飯を食べる時は必ず頂きますと礼をしてから頂きますは、全知全能の神に感謝ではなく、キリスト教での食前の祈りは神にのみの感謝の言葉ですが日本では、有り難うございますは、この食物を与えてくれた自然の恵み育ててくれた人びと、料理してくれた人全てに感謝ですからね。
旧約聖書のモーセがシナイ山で神からの契約を託される十戒の内容は日本人からしたら、えーそれ!普通にしたらアカン!て言われてきた事やんでしたね。
旧約聖書のモーセがシナイ山で神からの契約を託される十戒の内容は日本人からしたら、えーそれ!普通にしたらアカン!て言われてきた事やんでしたね。
Posted by うさこ at 2019年05月10日 01:24
艮の金さん様
とても興味深い論考ですね。
>この世界が何なのか、自分は何なのか、あるいは
世界は何のためにあるのか、自分は何のために生きているのか、
それらがわからない、ということが、人間にとっては「不安」であって、
その不安を解消する術が宗教だったのかもしれません。
恐らくですが・・・
これがギリシャ文明以来の西欧の哲学の発展の基盤になってきたことは間違いないでしょう。この自分や世界とは何ぞや?という問いは、一神教の発生基盤になった広大無辺の砂漠や平原という厳しい大空間に置かれた、ちっぽけな人間存在から発した問いなのかもしれません。大自然と自分との対峙はあまりにも絶対的な優劣観があり、自分の存在意義と同時に何か「偉大な存在」を必要とする欲求が生まれ、それと同時にご指摘の「存在の安心感」が得られるるのでしょう。
一方、仏教やヒンズー教などの自然が豊かな農耕地域は、自然と対峙することなく自然と融合・共存していくことで人間も幸福に暮らせる環境だから、自然崇拝や多神教の発生した風土があるのだと思います。そこには平和共存や助け合いという精神が発展していくでしょう。しかし厳しい自然環境では奪う事、争う事で生きる知恵が得られるので自ずと闘争心が発展します。そしてその荒くれ者を統率するリーダー(カリスマ)が必然的に出てきます。これがモーゼであったりイエスやムハマンドであったのでしょう。
>私の個人的断定的な定義では、多神教とは複数の原理を認め、
世界や自分に対する不可知性を認めて、それを何とも思わず、
謙虚に未知のものも尊重しながら生きていける自由な精神のことです。
まったく同感です。
いずれこのことについてもエントリしてみたいと思います。
貴重なご意見有難うございました。
うさこ様
同意です。
まったく仰る通りですね。
我々日本人はご先祖様の時代から、何の宗教でもなく自然に社会と調和し、人間関係を大切にする知恵(道徳といってもいいかな)を受け継いできました。別に世界を創造した偉大な神に教えてもらわなくても、殺人や泥棒はいけないことだと子供でも知っているのです。まあ基本的に日本人の道徳性は儒教精神から明文化されてはいますが、これを自然に受け入れたのは日本人の精神性にそのような要素が普通にあったからなのです。そしてそれが「神道」という無意識の思想なのだと思います。
とても興味深い論考ですね。
>この世界が何なのか、自分は何なのか、あるいは
世界は何のためにあるのか、自分は何のために生きているのか、
それらがわからない、ということが、人間にとっては「不安」であって、
その不安を解消する術が宗教だったのかもしれません。
恐らくですが・・・
これがギリシャ文明以来の西欧の哲学の発展の基盤になってきたことは間違いないでしょう。この自分や世界とは何ぞや?という問いは、一神教の発生基盤になった広大無辺の砂漠や平原という厳しい大空間に置かれた、ちっぽけな人間存在から発した問いなのかもしれません。大自然と自分との対峙はあまりにも絶対的な優劣観があり、自分の存在意義と同時に何か「偉大な存在」を必要とする欲求が生まれ、それと同時にご指摘の「存在の安心感」が得られるるのでしょう。
一方、仏教やヒンズー教などの自然が豊かな農耕地域は、自然と対峙することなく自然と融合・共存していくことで人間も幸福に暮らせる環境だから、自然崇拝や多神教の発生した風土があるのだと思います。そこには平和共存や助け合いという精神が発展していくでしょう。しかし厳しい自然環境では奪う事、争う事で生きる知恵が得られるので自ずと闘争心が発展します。そしてその荒くれ者を統率するリーダー(カリスマ)が必然的に出てきます。これがモーゼであったりイエスやムハマンドであったのでしょう。
>私の個人的断定的な定義では、多神教とは複数の原理を認め、
世界や自分に対する不可知性を認めて、それを何とも思わず、
謙虚に未知のものも尊重しながら生きていける自由な精神のことです。
まったく同感です。
いずれこのことについてもエントリしてみたいと思います。
貴重なご意見有難うございました。
うさこ様
同意です。
まったく仰る通りですね。
我々日本人はご先祖様の時代から、何の宗教でもなく自然に社会と調和し、人間関係を大切にする知恵(道徳といってもいいかな)を受け継いできました。別に世界を創造した偉大な神に教えてもらわなくても、殺人や泥棒はいけないことだと子供でも知っているのです。まあ基本的に日本人の道徳性は儒教精神から明文化されてはいますが、これを自然に受け入れたのは日本人の精神性にそのような要素が普通にあったからなのです。そしてそれが「神道」という無意識の思想なのだと思います。
Posted by トラネコ at 2019年05月11日 02:58
at 2019年05月11日 02:58
 at 2019年05月11日 02:58
at 2019年05月11日 02:58宗教の政治的社会的考察を行うのであれば、次の点は外せないと考えます。
1.大きな宗教の始まりは、反体制社会運動(革命)だったが、後の人たちによって宗教の形式に整えられた。
釈迦はインドのバラモン教の身分制度であるカーストを否定し「人は皆平等である」と説いた。 これは、カースト制度の「前世の行いによって現世の身分が決まっている」とする根本を否定する社会革命思想にほかならない。 後の弟子たちによる仏教の教義の「今世の行いがその人の価値を決める」という考え方が、身分制度に苦しんでいる多くの下層階級に受け入れられた。
イエスは救世主ではなく、圧政転覆を目指した革命家であった。
http://hon-bako.com/bookbox/bookbox_passion/%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%81%AF%E6%95%91%E4%B8%96%E4%B8%BB%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%80%81%E5%9C%A7%E6%94%BF%E8%BB%A2%E8%A6%86%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%97%E3%81%9F%E9%9D%A9/
2.全ての古代宗教が多神教であったのに対して、一神教は多神教的社会を征服するために利用された。
ユダヤ人・フェニキア人・カルタゴ人は、多神教のローマ帝国を崩壊させるために一神教のキリスト教を普及し、帝国崩壊後はユダヤ人やキリスト教徒がキリスト教の教会を世界支配の道具として利用した。
https://blog.goo.ne.jp/j4goocast/e/f37408d7496147a3ce8c2e9cdd2a0d41
3.ユダヤを理解しなければキリスト教は理解できないし、西洋の歴史も理解できない。 ユダヤ人(シオニスト)は世界を支配すべき神の選民であると信じ、カネと権力で世界を支配しようとしてきた。 ユダヤが始めた共産主義と金融資本主義グローバリズムは、かつての一神教と同じ役割を持っていると理解される。
元ソ連外交官が語る「ロシア-ユダヤ闘争史」の全貌 ← 必読
http://inri.client.jp/hexagon/floorA4F_ha/a4fhb500.html
1.大きな宗教の始まりは、反体制社会運動(革命)だったが、後の人たちによって宗教の形式に整えられた。
釈迦はインドのバラモン教の身分制度であるカーストを否定し「人は皆平等である」と説いた。 これは、カースト制度の「前世の行いによって現世の身分が決まっている」とする根本を否定する社会革命思想にほかならない。 後の弟子たちによる仏教の教義の「今世の行いがその人の価値を決める」という考え方が、身分制度に苦しんでいる多くの下層階級に受け入れられた。
イエスは救世主ではなく、圧政転覆を目指した革命家であった。
http://hon-bako.com/bookbox/bookbox_passion/%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%81%AF%E6%95%91%E4%B8%96%E4%B8%BB%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%80%81%E5%9C%A7%E6%94%BF%E8%BB%A2%E8%A6%86%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%97%E3%81%9F%E9%9D%A9/
2.全ての古代宗教が多神教であったのに対して、一神教は多神教的社会を征服するために利用された。
ユダヤ人・フェニキア人・カルタゴ人は、多神教のローマ帝国を崩壊させるために一神教のキリスト教を普及し、帝国崩壊後はユダヤ人やキリスト教徒がキリスト教の教会を世界支配の道具として利用した。
https://blog.goo.ne.jp/j4goocast/e/f37408d7496147a3ce8c2e9cdd2a0d41
3.ユダヤを理解しなければキリスト教は理解できないし、西洋の歴史も理解できない。 ユダヤ人(シオニスト)は世界を支配すべき神の選民であると信じ、カネと権力で世界を支配しようとしてきた。 ユダヤが始めた共産主義と金融資本主義グローバリズムは、かつての一神教と同じ役割を持っていると理解される。
元ソ連外交官が語る「ロシア-ユダヤ闘争史」の全貌 ← 必読
http://inri.client.jp/hexagon/floorA4F_ha/a4fhb500.html
Posted by Black Joker at 2019年05月11日 13:55
京都の神社仏閣に押し寄せ、拝観料を払って見物している連中は、抑々宗教心・信仰心の持ち合わせは無く、神社仏閣にしても、建物や庭園、宝物の維持管理の為に、「観光名所」に成り下がらざるを得ない事情があります。京都の西芳寺は、拝観を予約制にし、拝観料を大幅に値上げしましたが、読経・写経をしてから拝観させることで、「寺院」と「観光名所」の両立を図りました。私も無宗教な人間ですが、京都でお寺参り、というか襖絵や庭園を拝観する際には、美しいものは心静かに愛でるものと考え、お行儀よくしています。そして、「美しさ」以外の何かに気付いた時、私にも宗教心が芽生えることでしょう。
Posted by NTRC特撮軍団長・ヤラセロウ大元帥 at 2019年05月11日 17:53
Black Joker様
う~ん、宗教も政治思想みたいなものですか・・・
今何ともいえないですが、興味深い資料をご提示いただき、ありがとうございます。これに関しては現在忙しいので後でゆっくり読ませていただきます。また後ほど感想なりを述べさせていただきます。
NTRC特撮軍団長・ヤラセロウ大元帥 様
同意です。
京都の西芳寺(苔寺)の参道沿いに松尾市場がありますが、実は大昔ですが私、この入り口でたこ焼き屋をやっていたことがありました。しかし予約拝観制の導入で客足がばったり途絶え、店をたたみました。でも観光客のマナーの悪さも原因としてあり、コケをむしって持ち帰ったり、境内にゴミをもポイ捨てしたり、維持管理費が余計にかかるという話を当時聞きました。
京都観光の神社仏閣巡りは参拝というより観光ですよね。ただ仰るような雰囲気もあるのは事実です。これは何も仏教、神道だけでなく立派な教会でも同じような厳かな気持ちにさせてくれます。個人的には神社仏閣や教会は宗教演出の舞台だと考えているのですが、あながち外れてはいないでしょう。
う~ん、宗教も政治思想みたいなものですか・・・
今何ともいえないですが、興味深い資料をご提示いただき、ありがとうございます。これに関しては現在忙しいので後でゆっくり読ませていただきます。また後ほど感想なりを述べさせていただきます。
NTRC特撮軍団長・ヤラセロウ大元帥 様
同意です。
京都の西芳寺(苔寺)の参道沿いに松尾市場がありますが、実は大昔ですが私、この入り口でたこ焼き屋をやっていたことがありました。しかし予約拝観制の導入で客足がばったり途絶え、店をたたみました。でも観光客のマナーの悪さも原因としてあり、コケをむしって持ち帰ったり、境内にゴミをもポイ捨てしたり、維持管理費が余計にかかるという話を当時聞きました。
京都観光の神社仏閣巡りは参拝というより観光ですよね。ただ仰るような雰囲気もあるのは事実です。これは何も仏教、神道だけでなく立派な教会でも同じような厳かな気持ちにさせてくれます。個人的には神社仏閣や教会は宗教演出の舞台だと考えているのですが、あながち外れてはいないでしょう。
Posted by トラネコ at 2019年05月12日 02:36
at 2019年05月12日 02:36
 at 2019年05月12日 02:36
at 2019年05月12日 02:36トラネコ 様
世界宗教と呼ばれるキリスト教、仏教、イスラム教には共通する「平等思想」があり、これが多神教社会における「身分制度や家柄、支配部族からの開放」を謳ったことが強い影響力を持った事実を見なければなりません。 日本においても神道には氏子でないと正式には入信できなかった厳然たる身分差別が存在したことを知らなければ、どうして神道が仏教との権力闘争に負けていったのかを理解できません。 神道は非一神教だから寛容とかいうのは社会的政治的には迷信であり、一部であからさまな不寛容が存在していました。 神社の教義を「神道」だとすると、明らかに序列化が行われており、高天原に属さなければ排除され、属しても地位の差が存在した点には不寛容がありました。
神道における「八百万の神々」とは自然崇拝やアニミズムであると説明する文言がよくありますが、信仰対象とするものは自然界の全てではありません。 厳密には、八百万の神々とは、元々高天原の天津神のことです。 神話では物言う草木や石は高天原の神々に鎮められて物言う力を失ったとされています。 日本書紀には開発する大和朝廷に討伐される水神・雷神が登場します。 地上の神格については、かなり限定されたものしか信仰されていません。 動物を「神」と看做す慣習は古代にあったはずですが、あくまで人間の手に負えない生物や自然の存在が神だったのであり、制御しうるものは「神」ではなかった様です。 前近代の時代には、自然そのものを崇拝するには自然が強過ぎたので無理もないことだったでしょう。
「自然に帰れ」と言える様になったのは文明が強大化してからでであり、文明が自然を開発したばかりの頃は、自然は退治して制御する存在でした。 神道=自然崇拝、路傍の石ころにも神が宿るとか言い出したのは、戦後の宣伝だと考えられます。 石に霊威を認めるにしても、何かしら特別な石である必要があったはずです。 路傍の石はただの石であり、信仰の対象となるには何らかの権威付けが必要です。 その意味でも、宗教を政治と切り離して捉えられるようになったのは、一種の平和ボケなのです。 今日の宗教は政治性が失われて純粋思想化していますので、あくまで世俗化した社会では理解が難しいでしょうが、世界宗教は最初は全て社会運動(解放運動)でした。 イスラム原理主義やシオニズム運動を見れば、かつてのキリスト教や仏教もそうであったことが推測出来るでしょうか。
世界宗教と呼ばれるキリスト教、仏教、イスラム教には共通する「平等思想」があり、これが多神教社会における「身分制度や家柄、支配部族からの開放」を謳ったことが強い影響力を持った事実を見なければなりません。 日本においても神道には氏子でないと正式には入信できなかった厳然たる身分差別が存在したことを知らなければ、どうして神道が仏教との権力闘争に負けていったのかを理解できません。 神道は非一神教だから寛容とかいうのは社会的政治的には迷信であり、一部であからさまな不寛容が存在していました。 神社の教義を「神道」だとすると、明らかに序列化が行われており、高天原に属さなければ排除され、属しても地位の差が存在した点には不寛容がありました。
神道における「八百万の神々」とは自然崇拝やアニミズムであると説明する文言がよくありますが、信仰対象とするものは自然界の全てではありません。 厳密には、八百万の神々とは、元々高天原の天津神のことです。 神話では物言う草木や石は高天原の神々に鎮められて物言う力を失ったとされています。 日本書紀には開発する大和朝廷に討伐される水神・雷神が登場します。 地上の神格については、かなり限定されたものしか信仰されていません。 動物を「神」と看做す慣習は古代にあったはずですが、あくまで人間の手に負えない生物や自然の存在が神だったのであり、制御しうるものは「神」ではなかった様です。 前近代の時代には、自然そのものを崇拝するには自然が強過ぎたので無理もないことだったでしょう。
「自然に帰れ」と言える様になったのは文明が強大化してからでであり、文明が自然を開発したばかりの頃は、自然は退治して制御する存在でした。 神道=自然崇拝、路傍の石ころにも神が宿るとか言い出したのは、戦後の宣伝だと考えられます。 石に霊威を認めるにしても、何かしら特別な石である必要があったはずです。 路傍の石はただの石であり、信仰の対象となるには何らかの権威付けが必要です。 その意味でも、宗教を政治と切り離して捉えられるようになったのは、一種の平和ボケなのです。 今日の宗教は政治性が失われて純粋思想化していますので、あくまで世俗化した社会では理解が難しいでしょうが、世界宗教は最初は全て社会運動(解放運動)でした。 イスラム原理主義やシオニズム運動を見れば、かつてのキリスト教や仏教もそうであったことが推測出来るでしょうか。
Posted by Black Joker at 2019年05月13日 16:49
Black Joker様
同意です。
>世界宗教と呼ばれるキリスト教、仏教、イスラム教には共通する
「平等思想」があり、これが多神教社会における「身分制度や家柄、
支配部族からの開放」を謳ったことが強い影響力を持った事実
>神道は非一神教だから寛容とかいうのは社会的政治的には迷信であり、
一部であからさまな不寛容が存在していました
その通りです。
しかし結局はどちらもセクト主義に過ぎないですね。
つまり神の前のでの平等とは、同じ信仰を持つ者の間にのみ存在する概念であり、異教徒には適用されない価値観です。これが一方で「選ばれし者」という選民思想を生んでいます。創価学会はかつて学会会員は「地湧菩薩」と称し非会員を見下していました。また神道の氏子しか祭りに参加できないのも同じで、神社が各地域の地場信仰の中心であり、その地域の住民の守護神であれば当然でしょう。
そういう意味では、人間は何かの所属意識がどうしても不可欠にならざるを得ない存在なのだと思います。宗教はそういう人間の弱さを救済するための、一種の依存心を補助する「思想」ともいえるでしょう。俗な言い方すれば「気休め」とでもいえるかもしれませんが、人間は弱い存在ゆえにイワシの頭さえもすがりたくなのでしょう。
>厳密には、八百万の神々とは、元々高天原の天津神のことです。
>前近代の時代には、自然そのものを崇拝するには
自然が強過ぎたので無理もないことだったでしょう
そうなんですが・・・
原始時代の「神道」における「神々」とは祖霊、自然界の命あるものの精霊、無生物の物霊など、すべての現象に宿る目に見えない存在を指していると思います。日本における「神」の概念は、高天原におわしまする我々の先祖神のみならず、山川草木すべての生命もやはり神として存在します。これがアニミズムとしての側面である「神々」でしょう。 日本人はこういう不可視的な存在を「畏れる」感性をもっていた、というか一神教以外の民族はそういう感性だったのかもしれません。
>「自然に帰れ」と言える様になったのは文明が強大化してからでであり、
文明が自然を開発したばかりの頃は、自然は退治して制御する存在でした。
同意です。
自然崇拝はおそらく今でも一神教の人々の中にもあるような気がします。それは人間は自然を支配など到底できていないのは、世界各地で起こる地震、台風、津波、竜巻・・・様々な自然災害によっても明らかで、自然(災害)を恐れる=神を畏れる(神の怒り)という発想は今でもあると思います。一神教圏の連中が自然保護などを言い出したのも、それに気が付いたというのは言い過ぎでしょうか・・・
>神道=自然崇拝、路傍の石ころにも神が宿るとか言い出したのは、
戦後の宣伝だと考えられます。
ここは微妙に疑問です。
石をご神体にしている神社や依り代にしている神社は多いと思います。また古代人が天皇家の神宝の一つである勾玉も石でできています。もちろんこれはご指摘のような「特別の霊力」をもった石であるには違いないですが、石ころにも「神」が宿るといのは自然界すべてに「神々」が存在するという意味ではないでしょうか?
同意です。
>世界宗教と呼ばれるキリスト教、仏教、イスラム教には共通する
「平等思想」があり、これが多神教社会における「身分制度や家柄、
支配部族からの開放」を謳ったことが強い影響力を持った事実
>神道は非一神教だから寛容とかいうのは社会的政治的には迷信であり、
一部であからさまな不寛容が存在していました
その通りです。
しかし結局はどちらもセクト主義に過ぎないですね。
つまり神の前のでの平等とは、同じ信仰を持つ者の間にのみ存在する概念であり、異教徒には適用されない価値観です。これが一方で「選ばれし者」という選民思想を生んでいます。創価学会はかつて学会会員は「地湧菩薩」と称し非会員を見下していました。また神道の氏子しか祭りに参加できないのも同じで、神社が各地域の地場信仰の中心であり、その地域の住民の守護神であれば当然でしょう。
そういう意味では、人間は何かの所属意識がどうしても不可欠にならざるを得ない存在なのだと思います。宗教はそういう人間の弱さを救済するための、一種の依存心を補助する「思想」ともいえるでしょう。俗な言い方すれば「気休め」とでもいえるかもしれませんが、人間は弱い存在ゆえにイワシの頭さえもすがりたくなのでしょう。
>厳密には、八百万の神々とは、元々高天原の天津神のことです。
>前近代の時代には、自然そのものを崇拝するには
自然が強過ぎたので無理もないことだったでしょう
そうなんですが・・・
原始時代の「神道」における「神々」とは祖霊、自然界の命あるものの精霊、無生物の物霊など、すべての現象に宿る目に見えない存在を指していると思います。日本における「神」の概念は、高天原におわしまする我々の先祖神のみならず、山川草木すべての生命もやはり神として存在します。これがアニミズムとしての側面である「神々」でしょう。 日本人はこういう不可視的な存在を「畏れる」感性をもっていた、というか一神教以外の民族はそういう感性だったのかもしれません。
>「自然に帰れ」と言える様になったのは文明が強大化してからでであり、
文明が自然を開発したばかりの頃は、自然は退治して制御する存在でした。
同意です。
自然崇拝はおそらく今でも一神教の人々の中にもあるような気がします。それは人間は自然を支配など到底できていないのは、世界各地で起こる地震、台風、津波、竜巻・・・様々な自然災害によっても明らかで、自然(災害)を恐れる=神を畏れる(神の怒り)という発想は今でもあると思います。一神教圏の連中が自然保護などを言い出したのも、それに気が付いたというのは言い過ぎでしょうか・・・
>神道=自然崇拝、路傍の石ころにも神が宿るとか言い出したのは、
戦後の宣伝だと考えられます。
ここは微妙に疑問です。
石をご神体にしている神社や依り代にしている神社は多いと思います。また古代人が天皇家の神宝の一つである勾玉も石でできています。もちろんこれはご指摘のような「特別の霊力」をもった石であるには違いないですが、石ころにも「神」が宿るといのは自然界すべてに「神々」が存在するという意味ではないでしょうか?
Posted by トラネコ at 2019年05月13日 19:29
at 2019年05月13日 19:29
 at 2019年05月13日 19:29
at 2019年05月13日 19:29世界中どこでも同じですが、狩猟採集の自然資源、農業地や水源、牧畜地は一様に非常に重要視され、収穫を祈って祀られてきました。 それに関して、自然そのものを神の啓示と見做す世界観と「神道」とは明確に異なります。 神道はむしろ自然を擬人化しており、いわゆる汎神論とは根本的に異なるのです。
神道の神々は、あくまで人と同じような姿や人格を有する記紀神話に見られるような「人格神」であり、現世の人間に恩恵を与える「守護神」として祟る性格も持っています。 祟るからこそ、神は畏れられのであり、神道の神は祟りと密接な関係にあります。
繰り返しますが、縄文人などが持っていただろう自然崇拝的原始宗教と神道とは別物であり、仮説ですが神道は渡来人がオリエント世界から持ってきた(ギリシャ神話のような)多神教的世界観に基づいていると考えられます。
そもそも古事記も日本書紀も外来の影響下で書かれたものであり、神道は日本国家が統一された威厳を示すために新調された宗教と見るべきです。 神道を縄文文化や自然崇拝と結びつけたい気持ちは分かりますが、事実は想像とは異なります。 もっと古い古代には縄文文化や自然崇拝と結びついた神話や宗教儀式が存在したはずですが、宗教書という形では残っていないのです。
神道の神々は、あくまで人と同じような姿や人格を有する記紀神話に見られるような「人格神」であり、現世の人間に恩恵を与える「守護神」として祟る性格も持っています。 祟るからこそ、神は畏れられのであり、神道の神は祟りと密接な関係にあります。
繰り返しますが、縄文人などが持っていただろう自然崇拝的原始宗教と神道とは別物であり、仮説ですが神道は渡来人がオリエント世界から持ってきた(ギリシャ神話のような)多神教的世界観に基づいていると考えられます。
そもそも古事記も日本書紀も外来の影響下で書かれたものであり、神道は日本国家が統一された威厳を示すために新調された宗教と見るべきです。 神道を縄文文化や自然崇拝と結びつけたい気持ちは分かりますが、事実は想像とは異なります。 もっと古い古代には縄文文化や自然崇拝と結びついた神話や宗教儀式が存在したはずですが、宗教書という形では残っていないのです。
Posted by Black Joker at 2019年05月13日 22:16
Black Joker様
同意です。
>神道は日本国家が統一された威厳を示すために新調された宗教と見るべきです。
この点と汎神論とを混同していました。
そうですね、縄文時代の信仰とはいわゆるアニミズムであり、擬人化された神々はいませんでした。神社という形式を信仰の場として成立させた背景は、ご指摘の国家統一(恐らく7世紀頃)の思想的バックボーンの必要性だったと思います。
恐らく祖霊崇拝と皇室崇拝が結びついて擬人化もされてきたのでしょう。この辺がギリシャ神話とは若干異なる点かもしれませんが、自然現象と神々を結びつける発想は同じだと思います。
神道化される以前の神道的信仰は、多分沖縄に今もある御嶽(ウタキ)という形式に近いものだったと思っています。御嶽は森の中の一定の空間や岩や木を依り代とした場所を聖地しています。明治以降は鳥居を立てたところが増えましたが、本来は一切の人工建造物のない自然空間を聖地としていました。私はこれが神社の原初的形態だったと思っています。
同意です。
>神道は日本国家が統一された威厳を示すために新調された宗教と見るべきです。
この点と汎神論とを混同していました。
そうですね、縄文時代の信仰とはいわゆるアニミズムであり、擬人化された神々はいませんでした。神社という形式を信仰の場として成立させた背景は、ご指摘の国家統一(恐らく7世紀頃)の思想的バックボーンの必要性だったと思います。
恐らく祖霊崇拝と皇室崇拝が結びついて擬人化もされてきたのでしょう。この辺がギリシャ神話とは若干異なる点かもしれませんが、自然現象と神々を結びつける発想は同じだと思います。
神道化される以前の神道的信仰は、多分沖縄に今もある御嶽(ウタキ)という形式に近いものだったと思っています。御嶽は森の中の一定の空間や岩や木を依り代とした場所を聖地しています。明治以降は鳥居を立てたところが増えましたが、本来は一切の人工建造物のない自然空間を聖地としていました。私はこれが神社の原初的形態だったと思っています。
Posted by トラネコ at 2019年05月15日 10:25
at 2019年05月15日 10:25
 at 2019年05月15日 10:25
at 2019年05月15日 10:25ほんと、おっしゃる通りです。何教だろうが、それは形であって、自分を超越した存在への畏敬の念があることが大切だと思います。しかし事実として、日本では「目に見えない、神的な存在を信じる心」が薄れていることで色々な問題が人に、そして社会に出てきているように感じます。それが「無宗教」という捉えられ方をされているのでしょう。敗戦により、学校で宗教的な話題を扱ってはいけないとされたことが大きな要因ですね。八百万の神。一番、私はしっくり来るのですが…。
Posted by 猫山 at 2019年06月04日 12:24
猫山様
同意です。
>日本では「目に見えない、神的な存在を信じる心」が薄れていることで
色々な問題が人に、そして社会に出てきているように感じます。
まったく同感ですね。
こういう傾向が無意味な殺人や、児童や動物虐待などを引き起こしている原因の一つかな、と個人的には考えております。やはり信仰心は大切だと思います。
よろしければ、こちらのエントリもご笑読くださいませ。
↓
https://ryotaroneko.ti-da.net/e3701031.html
同意です。
>日本では「目に見えない、神的な存在を信じる心」が薄れていることで
色々な問題が人に、そして社会に出てきているように感じます。
まったく同感ですね。
こういう傾向が無意味な殺人や、児童や動物虐待などを引き起こしている原因の一つかな、と個人的には考えております。やはり信仰心は大切だと思います。
よろしければ、こちらのエントリもご笑読くださいませ。
↓
https://ryotaroneko.ti-da.net/e3701031.html
Posted by トラネコ at 2019年06月04日 19:07
at 2019年06月04日 19:07
 at 2019年06月04日 19:07
at 2019年06月04日 19:07