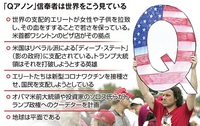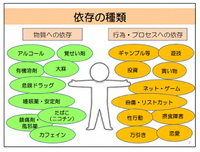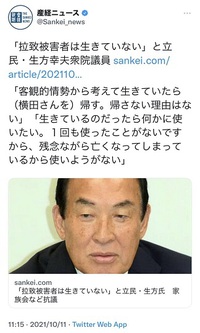聖職者の「性」犯罪と独身制について
2017年09月24日
「独身制」こそ聖職者の性犯罪の元凶 --- 長谷川 良
ローマ・カトリック教会関連施設で聖職者の未成年者への性的虐待が多発しているが、バチカン法王庁は、「聖職者の独身制と性犯罪の増加とは関係がない」という立場を強調してきた。しかし、オーストラリアの2人の学者が、「聖職者の性犯罪とその独身制とは密接な関係がある」と指摘した研究書をこのほど発表し、注目を集めている。
384頁に及ぶ研究書はペーター・ウィルキンソン氏とデスモンド・ケヒル氏の労作だ。2人は元神父だ。教会の組織、内部事情に通じている両氏は、「世界のカトリック教会には、聖職者を性犯罪に走らせる組織的欠陥がある」と考え、個々のケースを調査し、各ケースに共通する背景、状況を検証していったという。
オーストラリア教会の聖職者の性犯罪調査王立委員会は今年初めに暫定報告を公表したが、それによると、オーストラリア教会で1950年から2010年の間、少なくとも7%の聖職者が未成年者への性的虐待で告訴されている。身元が確認された件数だけで1880人の聖職者の名前が挙げられている。
すなわち、100人の神父がいたらそのうち7人が未成年者への性的虐待を犯しているという衝撃的な内容だった(「豪教会聖職者の『性犯罪』の衝撃」(http://agora-web.jp/archives/2024343.html)2017年2月9日参考)。
2人の学者は聖職者による過去の性犯罪を検証し、関連の研究書やレポートを参考に研究を進めていった。ちなみに、ロイヤルメルボルン工科大学=RMIT大学は、「聖職者の性犯罪の背景分析として、文化的、歴史的、組織的、社会的、心理学的、神学的要素を包括的に検証している」と、研究書を高く評価している。
2人の学者は聖職者の性犯罪の主因として2点を挙げている。
(1)聖職者が結婚できる教会では性犯罪は少ない一方、聖職者の独身制を
強いるカトリック教会では性的に未熟な若い神父たちが自分より幼い未成年者に
性的犯行に走るケースが多い。すなわち、聖職者の性犯罪とその独身制には
密接な関連がある。
(2)カトリック教会が経営する孤児院や養護施設などが性犯罪を誘発する
組織的背景となっている。カトリック教会は世界約9800カ所に孤児院、
養護施設などを経営しているが、それらの施設に保護される未成年者は
聖職者の性犯罪の犠牲となる危険性が高い。経営側の教会はその点に
ついて余り自覚していない。
上記の2点は新しい事実ではない。多くのメディアや教会関係者が指摘してきた内容だが、今回は膨大な資料を分析、検証したうえでの結論だけに説得力がある。
例えば、オーストリアのローマ・カトリック教会最高指導者シェーンボルン枢機卿は、「性犯罪はカトリック教会の聖職者だけが犯す犯罪ではない。その件数自体、他の社会層のそれよりも少ない」と弁明したことがある。同枢機卿の見解が教会のこれまでの代表的な立場だった。
なお、前オーストラリア教会最高指導者ジョージ・ペル枢機卿(バチカンの枢機卿会議メンバー)は同国の検察庁から未成年者への性的虐待容疑で起訴され、現在、公判を受ける身だ。
カトリック教会の独身制については、このコラムでも何度も言及してきた。南米教会出身のフランシスコ法王は前法王べネディクト16世と同様、「独身制は神の祝福だ」と強調する一方、「聖職者の独身制は信仰(教義)問題ではない」と認めている。換言すれば、独身制は聖書に基づくものではなく、あくまでも教会が決めた規約に過ぎないわけだ。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2017年9月18日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』(http://blog.livedoor.jp/wien2006/)をご覧ください。
アゴラ 9/19(火)
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170919-00010003-agora-int&pos=1

カトリック教会の性的虐待事件

ドイツのカトリック教会の聖歌隊にも「性的虐待」事件が・・・
https://www.telesurtv.net/news/Abusos-contra-menores-de-un-coro-de-la-iglesia-catolica-alemana-20160114-0030.html
今日は宗教界の「性」に関する考察をしてみる。
とはいっても、そんな生々しい話はしないのでご安心をw
あくまで宗教における人間論の一つの観方としての雑感である。
冗談にも聖職者が「性」職者になってもらってはいけないが、
現実的には宗教者の「性」犯罪は結構多いようだから、
宗教者を聖職者と見ることを疑う事から考えるべきである。
日本の仏教界などは既に聖職者などほぼ皆無に近いだろう。
僧籍が一職業に堕しているくらいで風俗通いの僧侶など珍しくもないし、
それがあっても誰も驚かないくらい日本仏教界は世俗化している。
・・・あ、いやこれは訂正しよう。
今も高野山奥の院や永平寺などでは真剣に修行に励む僧侶はいる。
実際に今でも少数ではあるが人生の真理を求め修行の道を歩む人はいる。
私のような俗人にはない崇高な求道心をもった人である。少ないけどねw

高野山奥の院
今は交通機関も整備され誰でも簡単に行く事ができるが、
昔は簡単に行けないし、行けば戻ってくるのも大変な所だ。
しかしそんな人でも俗界に戻って寺の住職にでもなれば大抵堕落する。
まあこれは僧侶に限らず、常習的犯罪者にも同じことがいえる。
刑務所に入り規則正しい生活や反省や学習を強制されればマトモになる。
しかし出所し娑婆の生活に戻れば、昔の悪友と交わりまた元に戻るのだ。
ダイエットでもRIZAPみたいに集中的な個人管理下でトレーニングして、
短期間に結果を出したとしても、元の暮らしに戻り自己管理できなければ、
たちまちリバウンドしてしまうのと同じである。
そういう意味で、昔から修行を中心に行う寺は人里離れた山間部などにあった。
俗界と隔絶し閉鎖的空間で修行しないと世俗の誘惑が多いからであろう。
自分の意思の強さもそうだが、いかに環境が大事かという事だな。
もっとも・・・
悟りを開いた昔の禅の高僧などは完全な不動心を確立しているらしく、、
三条大橋の欄干の傍でも座禅を組めた(賑やかな場所でも瞑想ができる)、
というが、今はそこまで悟りを開いた僧侶はいないだろうな・・・
人間って弱い生き物なんだよな・・・

松村邦洋クンもスッキリした体形になったが、
問題は今後これを彼が維持できるかどうか。
>「聖職者の性犯罪とその独身制とは密接な関係がある」
そりゃあ、大有りだろう!
生命力にあふれる若い時代に性欲を抑えるなどは至難の業である。
俗に売春業が人類最古の職業といわれるのも、特に女性よりも、
男性の性欲の処理が人類史の始まりから社会の課題だったのだ。
いくら修行に励み俗界と縁を切った宗教者といえど生身の人間である。
現在はどうか知らないが昔の修道士は自慰も禁止されていたというから、
若い僧侶や修道士など、性欲の抑圧は拷問に等しかっただろうと思う。
そりゃあね、人間の性欲は食欲と並び個の生存と種の繁栄の基本である。
これは生物の生存本能として備わっている以上、抑止する方に無理がある。
だから特に精神修養を課題とする宗教者には禁欲が要求されるのはわかるが・・・
カトリック教会でも、若い修道士が性犯罪起こしても、
まあ驚かんわ、これは生理現象だし抑圧し続ければ、
こういう犯罪に走ることもわかるしな・・・

いくら強い志をもって神への道、仏の道、悟りの道・・・を歩もうと決心しても、
人間の生存本能に逆らう事の方がどんな厳しい修行より苦痛ではないだろうか?
性衝動は快楽を伴うから禁欲するほど抑止は難しいだろう。
そして人間は大なり小なり、安楽、快楽に流れやすいものだ。
それを忍耐し修行することが僧侶や修道士の人生目標だろうが、
自然に備わった本能を抑止する、逆らうのってキッツイだろうと思う。
だがしかし・・・
カトリックに小児性愛者が多いのは個人的には理解し難いものがある。
日本でも昔は寺の子坊主を「稚児」と言って性の対象にしていたらしい。
しかしこれは昔の俗世間と隔離された山寺の話だ。
俗世間と関わる教会の神父にロリ コンが多いのには驚く。それも男の子の・・・
まあ相手が子供なら騙しやすいし、言いなりにしやすいって事なんだろうが、
子供に「性欲」を感じる精神構造というか、感性が私はわからんなあ・・・
私ならその子のカーちゃんに手をだすが・・・(失礼)

ウリスト教の牧師は100%小児「性」職者www
昔は宗教者には独身制を採用する宗教教団が多かった。
もちろん一般信者ではなく指導者に当たる者である。
現在でもカトリック、ラマ教、東南アジアの上座部仏教・・・などは皆独身制だ。
一方・・・
キリスト教でもプロテスタント系の牧師は妻帯し家庭をもっている。
イスラム教の指導者(ウラマー)も妻帯し普通に家庭をもっている。
そしてユダヤ教のラビもである。
まあこの方が人間として自然ではあると個人的には思う。
日本では親鸞以前は仏教界すべて独身制だったのだが、
現在は仏教界すべてが妻帯し子供をもうけて俗化している。
一部の僧侶は独身を通し修行に生涯を捧げている人もいるようだ。
なぜ宗教者には独身制がとられてきたのか?
それは恐らく快楽に溺れない為の戒めだたのだろうと思う。
しかし快楽に溺れない程度に快楽を享受することはいいのではないか?

こういう修行僧はプロ中のプロ、世俗にはいない。
個人的に思うのだが、人間は肉体を持った状態で「悟り」は不可能だという事だ。
ただ快楽を極めつくした「性の達人」になれば性欲もコントロールできるかもしれない。
或いは性を極め尽くし一定の年齢に達すれ性欲も抑制できるとは思う。
要は若いころは遊びまくってある程度「性」を理解して後ならば、
宗教界に入って修行する事も可能だろうと思うが、これを実践したのが、
浄土真宗の親鸞である。彼も修行僧時代は飲む・打つ・買うやってたそうだ。
↓
<参考エントリ>
浄土真宗の不思議
http://ryotaroneko.ti-da.net/e2132946.html

悪人正機説の親鸞
そもそも・・・
仏教の開祖釈迦(ゴーダマ・シッタルダ)がそうだったじゃないか。
彼は元々王子だから何不自由なく暮らし酒池肉林の暮らしだった。
今の北朝鮮のカリアゲ豚みたいな生活してたんじゃないだろうか。
それだけ快楽も知り尽くしたからこそ、カピラバースト城の四つの門から、
世俗人の暮らしを見て人生の虚しさを感じたのではなかったのだろうか。
そこで人生とは四苦(生老病死)を悟り、出家し苦行生活に入ったのだろう。
ちなみに、釈迦みたいな偉い人が家を出れば「出家」というが、
我々凡人が家を出て行方知れずになってももただの「家出」としかいわれない。
やっぱり偉大な人はちがうなあ・・・(溜息)

我々凡人が家を出てもこんな事は悟れない
信者には叱られるかもしれないが、キリスト教の開祖イエスだって・・・
イエスも30歳前くらいに洗礼を受け荒野に出て修行したというらしいが、
それまでは女遊びや酒飲んで喧嘩した経験も大いにあったのではないだろうか?
意外にもイエスは母マリアを泣かせた悪ガキだったかも知れないぞ。
実際にイエスの生涯で30歳前後まではまったく記述がないのである。
これはあえて聖書編集者が記述したくなかったのではないだろうか?
つまりイエスも神の子になる前に人の子だったという事である。
神童とか言われて年端もいかないガキがエラソーに大人に説法など、
馬鹿バカしくて信じる気もしないね。マリアの処女懐妊、水をワインに変えた、
パンと魚に魔法をかけ5千人分に増やす、磔刑後三日で肉体を持ったまま昇天した・・・
こんなのは後世の教会あたりが勝ってに神格化し伝説化した作り話だと私は思う。

しかし彼らの快楽三昧の暮らしは、その後の厳しい修行と、
悪魔との闘いに打ち勝つためのこれまた修行だったのだ。
ここが快楽三昧で堕落していく凡人とは大きく異なる点である。
釈迦もイエスも断食修行している間、「魔」(悪魔)の誘惑を執拗に受けたが、
これに打ち勝てたのも「欲望」を知り尽くしていたからではなかったか。
つまりしっかりした「欲への免疫」を身につけていたのである。
やっぱり偉大な人物は地獄も天国も生前に経験させられ、
人生の酸いも甘いも理解できる人生の達人であったのだ。
生身の肉体を持って生きている以上、清濁併せ呑む生き方しか出来ないな。

苦行中の釈迦
釈迦に悟りを開かれて困る「魔」が脅し、誘惑など、
様々な手段を使って悟りを開かせまいと攻撃した。

荒野で40日間断食したイエスも
悪魔の執拗な誘惑を受けた。
昔話題になった「親分はイエス様」という実話を基にした映画があった。
暴力、強盗、恐喝、麻薬・・・殺人以外の悪事をすべて行ったヤクザが、
あるきっかけでキリスト教に出会い、悪事の人生を反省、改心した後に、
自らが牧師になって同じ境遇の人びとを救済する話である。
私はこういう人は本物だと思う。
悪のどん底に身を落とし「地獄」を見てきた境遇から這い上がり、
宗教者としての生き方を実践し迷える人々を救う生き方は凄いと思う。
ヤクザが宗教者として生まれ変わる方が、凡人として生きるよりも難しいと思う。
元々道徳的な生き方してきた人には、ヤクザの生き方は理解できないし説得力もない。
こういう牧師に説得されればヤクザも改心して真人間になるのではないか。

元ヤクザの鈴木啓之牧師

一方、同じ不道徳な生活をしまくった人物で、
出家はしたものの、全く対照的な俗人もいる・・・
若いころ不道徳しまくって出家しても全く悟りとは縁遠い暮らしで、
TVや週刊誌には出まくって愚論を述べ俗世間と縁がきれない俗物もいる。
マスゴミはこういう袈裟を纏った俗物には実に好意的である(笑)
↓

若いころにエロ事三昧で出家して、
90歳越えてもいまだ悟れないBBA
いい加減に逝けよ、老醜エロBBA!
>独身制は聖書に基づくものではなく、
あくまでも教会が決めた規約に過ぎないわけだ。
宗教教義ってすべてそうじゃないのか?
私はキリスト教も仏教も特に信仰していないが興味・関心から、
聖書や仏典はよく読んでいた。そこで常に疑問を抱いていた事は、
神学論争とか仏教哲学とか何故にこうも難解なのか? という事だった。
恐らくだが、イエスや仏陀の生きていた時代には民衆は無学文盲であり、
学問など一部の王族や貴族、宗教者くらいにしか学べなかったはずである。
偉大な救世主が民衆を救うのにこんな難しい事言ってわかるはずがない。
イエスや仏陀の教えとはもっと単純明快だったはずだ。
仏教の開祖・釈迦はすべての人間が出家しろなどと言ってないし、
僧侶という職業すら念頭にはなかったのではないかと私は思う。
そんな事したら社会が成り立たないしwww
釈迦が言いたかった事は、凡人は普通に生業を持ち家庭をもって、
快楽も抑圧するのではなく適度に行い、何事にも極端に流れず、
「足る事を知った暮らし」をせよと言うだけだったのではないか?
多分イエスだって似たような事を言っていたと思うぞ。

それが弟子たちの主観や解釈の違いなど時代を重ねるごとに、
後継者たちの解釈により複雑化し、それぞれが教団を出て
分派独立していったのだろう。だから宗派というのができるのだ。
カトリックは一つだがプロテスタントなど30000以上の分派の教会があるという。
だから宗教者の戒律なども、そうやって徐々に意味もなく増えて行ったのだろう。
いや意味はあったのだろうが、時代を経るうちに形式化していったといえるだろう。
カトリックもその時代の教皇の考え方でいろいろ解釈も生まれるものだし、
所詮人間は人間、神にはなれないのだから妻帯するのは自然ではないか。
ここいら辺でカトリックも妻帯を認めてみてはいかがなものだろうか?
<参考エントリ>
聖書は神の言葉か?
http://ryotaroneko.ti-da.net/e2784494.html

ま、私は宗教心は誰しも必要だと思うし、どの宗派でも良いと思う。
信仰は個人的なものと考えているからだ。それが教団を作り、
階級や活動ノルマができれば確実に堕落すると言っておこう。
また信仰心が大事なのは、共産主義みたいに人間万能論に陥れば、
人間の傲慢さが増長され、時に残酷にもなれるからである。
もっとも一部の原理主義みたいに狂信的になっても同じだが。
何事もほどほどに、適当に、偏らない中道の生き方がよい、
とお釈迦様も言ってます。イエスも似たような事言ってないだろうか?
とにかく・・・
笑顔と謙虚さを忘れずに、
いつも感謝して生きよう!

<お知らせ>
読者の皆様、一時帰国しますので数日休みます。
ではまた、よろしくお願いいたします。
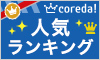

ローマ・カトリック教会関連施設で聖職者の未成年者への性的虐待が多発しているが、バチカン法王庁は、「聖職者の独身制と性犯罪の増加とは関係がない」という立場を強調してきた。しかし、オーストラリアの2人の学者が、「聖職者の性犯罪とその独身制とは密接な関係がある」と指摘した研究書をこのほど発表し、注目を集めている。
384頁に及ぶ研究書はペーター・ウィルキンソン氏とデスモンド・ケヒル氏の労作だ。2人は元神父だ。教会の組織、内部事情に通じている両氏は、「世界のカトリック教会には、聖職者を性犯罪に走らせる組織的欠陥がある」と考え、個々のケースを調査し、各ケースに共通する背景、状況を検証していったという。
オーストラリア教会の聖職者の性犯罪調査王立委員会は今年初めに暫定報告を公表したが、それによると、オーストラリア教会で1950年から2010年の間、少なくとも7%の聖職者が未成年者への性的虐待で告訴されている。身元が確認された件数だけで1880人の聖職者の名前が挙げられている。
すなわち、100人の神父がいたらそのうち7人が未成年者への性的虐待を犯しているという衝撃的な内容だった(「豪教会聖職者の『性犯罪』の衝撃」(http://agora-web.jp/archives/2024343.html)2017年2月9日参考)。
2人の学者は聖職者による過去の性犯罪を検証し、関連の研究書やレポートを参考に研究を進めていった。ちなみに、ロイヤルメルボルン工科大学=RMIT大学は、「聖職者の性犯罪の背景分析として、文化的、歴史的、組織的、社会的、心理学的、神学的要素を包括的に検証している」と、研究書を高く評価している。
2人の学者は聖職者の性犯罪の主因として2点を挙げている。
(1)聖職者が結婚できる教会では性犯罪は少ない一方、聖職者の独身制を
強いるカトリック教会では性的に未熟な若い神父たちが自分より幼い未成年者に
性的犯行に走るケースが多い。すなわち、聖職者の性犯罪とその独身制には
密接な関連がある。
(2)カトリック教会が経営する孤児院や養護施設などが性犯罪を誘発する
組織的背景となっている。カトリック教会は世界約9800カ所に孤児院、
養護施設などを経営しているが、それらの施設に保護される未成年者は
聖職者の性犯罪の犠牲となる危険性が高い。経営側の教会はその点に
ついて余り自覚していない。
上記の2点は新しい事実ではない。多くのメディアや教会関係者が指摘してきた内容だが、今回は膨大な資料を分析、検証したうえでの結論だけに説得力がある。
例えば、オーストリアのローマ・カトリック教会最高指導者シェーンボルン枢機卿は、「性犯罪はカトリック教会の聖職者だけが犯す犯罪ではない。その件数自体、他の社会層のそれよりも少ない」と弁明したことがある。同枢機卿の見解が教会のこれまでの代表的な立場だった。
なお、前オーストラリア教会最高指導者ジョージ・ペル枢機卿(バチカンの枢機卿会議メンバー)は同国の検察庁から未成年者への性的虐待容疑で起訴され、現在、公判を受ける身だ。
カトリック教会の独身制については、このコラムでも何度も言及してきた。南米教会出身のフランシスコ法王は前法王べネディクト16世と同様、「独身制は神の祝福だ」と強調する一方、「聖職者の独身制は信仰(教義)問題ではない」と認めている。換言すれば、独身制は聖書に基づくものではなく、あくまでも教会が決めた規約に過ぎないわけだ。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2017年9月18日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』(http://blog.livedoor.jp/wien2006/)をご覧ください。
アゴラ 9/19(火)
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170919-00010003-agora-int&pos=1

カトリック教会の性的虐待事件

ドイツのカトリック教会の聖歌隊にも「性的虐待」事件が・・・
https://www.telesurtv.net/news/Abusos-contra-menores-de-un-coro-de-la-iglesia-catolica-alemana-20160114-0030.html
今日は宗教界の「性」に関する考察をしてみる。
とはいっても、そんな生々しい話はしないのでご安心をw
あくまで宗教における人間論の一つの観方としての雑感である。
冗談にも聖職者が「性」職者になってもらってはいけないが、
現実的には宗教者の「性」犯罪は結構多いようだから、
宗教者を聖職者と見ることを疑う事から考えるべきである。
日本の仏教界などは既に聖職者などほぼ皆無に近いだろう。
僧籍が一職業に堕しているくらいで風俗通いの僧侶など珍しくもないし、
それがあっても誰も驚かないくらい日本仏教界は世俗化している。
・・・あ、いやこれは訂正しよう。
今も高野山奥の院や永平寺などでは真剣に修行に励む僧侶はいる。
実際に今でも少数ではあるが人生の真理を求め修行の道を歩む人はいる。
私のような俗人にはない崇高な求道心をもった人である。少ないけどねw

高野山奥の院
今は交通機関も整備され誰でも簡単に行く事ができるが、
昔は簡単に行けないし、行けば戻ってくるのも大変な所だ。
しかしそんな人でも俗界に戻って寺の住職にでもなれば大抵堕落する。
まあこれは僧侶に限らず、常習的犯罪者にも同じことがいえる。
刑務所に入り規則正しい生活や反省や学習を強制されればマトモになる。
しかし出所し娑婆の生活に戻れば、昔の悪友と交わりまた元に戻るのだ。
ダイエットでもRIZAPみたいに集中的な個人管理下でトレーニングして、
短期間に結果を出したとしても、元の暮らしに戻り自己管理できなければ、
たちまちリバウンドしてしまうのと同じである。
そういう意味で、昔から修行を中心に行う寺は人里離れた山間部などにあった。
俗界と隔絶し閉鎖的空間で修行しないと世俗の誘惑が多いからであろう。
自分の意思の強さもそうだが、いかに環境が大事かという事だな。
もっとも・・・
悟りを開いた昔の禅の高僧などは完全な不動心を確立しているらしく、、
三条大橋の欄干の傍でも座禅を組めた(賑やかな場所でも瞑想ができる)、
というが、今はそこまで悟りを開いた僧侶はいないだろうな・・・
人間って弱い生き物なんだよな・・・

松村邦洋クンもスッキリした体形になったが、
問題は今後これを彼が維持できるかどうか。
>「聖職者の性犯罪とその独身制とは密接な関係がある」
そりゃあ、大有りだろう!
生命力にあふれる若い時代に性欲を抑えるなどは至難の業である。
俗に売春業が人類最古の職業といわれるのも、特に女性よりも、
男性の性欲の処理が人類史の始まりから社会の課題だったのだ。
いくら修行に励み俗界と縁を切った宗教者といえど生身の人間である。
現在はどうか知らないが昔の修道士は自慰も禁止されていたというから、
若い僧侶や修道士など、性欲の抑圧は拷問に等しかっただろうと思う。
そりゃあね、人間の性欲は食欲と並び個の生存と種の繁栄の基本である。
これは生物の生存本能として備わっている以上、抑止する方に無理がある。
だから特に精神修養を課題とする宗教者には禁欲が要求されるのはわかるが・・・
カトリック教会でも、若い修道士が性犯罪起こしても、
まあ驚かんわ、これは生理現象だし抑圧し続ければ、
こういう犯罪に走ることもわかるしな・・・

いくら強い志をもって神への道、仏の道、悟りの道・・・を歩もうと決心しても、
人間の生存本能に逆らう事の方がどんな厳しい修行より苦痛ではないだろうか?
性衝動は快楽を伴うから禁欲するほど抑止は難しいだろう。
そして人間は大なり小なり、安楽、快楽に流れやすいものだ。
それを忍耐し修行することが僧侶や修道士の人生目標だろうが、
自然に備わった本能を抑止する、逆らうのってキッツイだろうと思う。
だがしかし・・・
カトリックに小児性愛者が多いのは個人的には理解し難いものがある。
日本でも昔は寺の子坊主を「稚児」と言って性の対象にしていたらしい。
しかしこれは昔の俗世間と隔離された山寺の話だ。
俗世間と関わる教会の神父にロリ コンが多いのには驚く。それも男の子の・・・
まあ相手が子供なら騙しやすいし、言いなりにしやすいって事なんだろうが、
子供に「性欲」を感じる精神構造というか、感性が私はわからんなあ・・・
私ならその子のカーちゃんに手をだすが・・・(失礼)

ウリスト教の牧師は100%小児「性」職者www
昔は宗教者には独身制を採用する宗教教団が多かった。
もちろん一般信者ではなく指導者に当たる者である。
現在でもカトリック、ラマ教、東南アジアの上座部仏教・・・などは皆独身制だ。
一方・・・
キリスト教でもプロテスタント系の牧師は妻帯し家庭をもっている。
イスラム教の指導者(ウラマー)も妻帯し普通に家庭をもっている。
そしてユダヤ教のラビもである。
まあこの方が人間として自然ではあると個人的には思う。
日本では親鸞以前は仏教界すべて独身制だったのだが、
現在は仏教界すべてが妻帯し子供をもうけて俗化している。
一部の僧侶は独身を通し修行に生涯を捧げている人もいるようだ。
なぜ宗教者には独身制がとられてきたのか?
それは恐らく快楽に溺れない為の戒めだたのだろうと思う。
しかし快楽に溺れない程度に快楽を享受することはいいのではないか?

こういう修行僧はプロ中のプロ、世俗にはいない。
個人的に思うのだが、人間は肉体を持った状態で「悟り」は不可能だという事だ。
ただ快楽を極めつくした「性の達人」になれば性欲もコントロールできるかもしれない。
或いは性を極め尽くし一定の年齢に達すれ性欲も抑制できるとは思う。
要は若いころは遊びまくってある程度「性」を理解して後ならば、
宗教界に入って修行する事も可能だろうと思うが、これを実践したのが、
浄土真宗の親鸞である。彼も修行僧時代は飲む・打つ・買うやってたそうだ。
↓
<参考エントリ>
浄土真宗の不思議
http://ryotaroneko.ti-da.net/e2132946.html

悪人正機説の親鸞
そもそも・・・
仏教の開祖釈迦(ゴーダマ・シッタルダ)がそうだったじゃないか。
彼は元々王子だから何不自由なく暮らし酒池肉林の暮らしだった。
今の北朝鮮のカリアゲ豚みたいな生活してたんじゃないだろうか。
それだけ快楽も知り尽くしたからこそ、カピラバースト城の四つの門から、
世俗人の暮らしを見て人生の虚しさを感じたのではなかったのだろうか。
そこで人生とは四苦(生老病死)を悟り、出家し苦行生活に入ったのだろう。
ちなみに、釈迦みたいな偉い人が家を出れば「出家」というが、
我々凡人が家を出て行方知れずになってももただの「家出」としかいわれない。
やっぱり偉大な人はちがうなあ・・・(溜息)

我々凡人が家を出てもこんな事は悟れない
信者には叱られるかもしれないが、キリスト教の開祖イエスだって・・・
イエスも30歳前くらいに洗礼を受け荒野に出て修行したというらしいが、
それまでは女遊びや酒飲んで喧嘩した経験も大いにあったのではないだろうか?
意外にもイエスは母マリアを泣かせた悪ガキだったかも知れないぞ。
実際にイエスの生涯で30歳前後まではまったく記述がないのである。
これはあえて聖書編集者が記述したくなかったのではないだろうか?
つまりイエスも神の子になる前に人の子だったという事である。
神童とか言われて年端もいかないガキがエラソーに大人に説法など、
馬鹿バカしくて信じる気もしないね。マリアの処女懐妊、水をワインに変えた、
パンと魚に魔法をかけ5千人分に増やす、磔刑後三日で肉体を持ったまま昇天した・・・
こんなのは後世の教会あたりが勝ってに神格化し伝説化した作り話だと私は思う。

しかし彼らの快楽三昧の暮らしは、その後の厳しい修行と、
悪魔との闘いに打ち勝つためのこれまた修行だったのだ。
ここが快楽三昧で堕落していく凡人とは大きく異なる点である。
釈迦もイエスも断食修行している間、「魔」(悪魔)の誘惑を執拗に受けたが、
これに打ち勝てたのも「欲望」を知り尽くしていたからではなかったか。
つまりしっかりした「欲への免疫」を身につけていたのである。
やっぱり偉大な人物は地獄も天国も生前に経験させられ、
人生の酸いも甘いも理解できる人生の達人であったのだ。
生身の肉体を持って生きている以上、清濁併せ呑む生き方しか出来ないな。

苦行中の釈迦
釈迦に悟りを開かれて困る「魔」が脅し、誘惑など、
様々な手段を使って悟りを開かせまいと攻撃した。

荒野で40日間断食したイエスも
悪魔の執拗な誘惑を受けた。
昔話題になった「親分はイエス様」という実話を基にした映画があった。
暴力、強盗、恐喝、麻薬・・・殺人以外の悪事をすべて行ったヤクザが、
あるきっかけでキリスト教に出会い、悪事の人生を反省、改心した後に、
自らが牧師になって同じ境遇の人びとを救済する話である。
私はこういう人は本物だと思う。
悪のどん底に身を落とし「地獄」を見てきた境遇から這い上がり、
宗教者としての生き方を実践し迷える人々を救う生き方は凄いと思う。
ヤクザが宗教者として生まれ変わる方が、凡人として生きるよりも難しいと思う。
元々道徳的な生き方してきた人には、ヤクザの生き方は理解できないし説得力もない。
こういう牧師に説得されればヤクザも改心して真人間になるのではないか。

元ヤクザの鈴木啓之牧師

一方、同じ不道徳な生活をしまくった人物で、
出家はしたものの、全く対照的な俗人もいる・・・
若いころ不道徳しまくって出家しても全く悟りとは縁遠い暮らしで、
TVや週刊誌には出まくって愚論を述べ俗世間と縁がきれない俗物もいる。
マスゴミはこういう袈裟を纏った俗物には実に好意的である(笑)
↓

若いころにエロ事三昧で出家して、
90歳越えてもいまだ悟れないBBA
いい加減に逝けよ、老醜エロBBA!
>独身制は聖書に基づくものではなく、
あくまでも教会が決めた規約に過ぎないわけだ。
宗教教義ってすべてそうじゃないのか?
私はキリスト教も仏教も特に信仰していないが興味・関心から、
聖書や仏典はよく読んでいた。そこで常に疑問を抱いていた事は、
神学論争とか仏教哲学とか何故にこうも難解なのか? という事だった。
恐らくだが、イエスや仏陀の生きていた時代には民衆は無学文盲であり、
学問など一部の王族や貴族、宗教者くらいにしか学べなかったはずである。
偉大な救世主が民衆を救うのにこんな難しい事言ってわかるはずがない。
イエスや仏陀の教えとはもっと単純明快だったはずだ。
仏教の開祖・釈迦はすべての人間が出家しろなどと言ってないし、
僧侶という職業すら念頭にはなかったのではないかと私は思う。
そんな事したら社会が成り立たないしwww
釈迦が言いたかった事は、凡人は普通に生業を持ち家庭をもって、
快楽も抑圧するのではなく適度に行い、何事にも極端に流れず、
「足る事を知った暮らし」をせよと言うだけだったのではないか?
多分イエスだって似たような事を言っていたと思うぞ。

それが弟子たちの主観や解釈の違いなど時代を重ねるごとに、
後継者たちの解釈により複雑化し、それぞれが教団を出て
分派独立していったのだろう。だから宗派というのができるのだ。
カトリックは一つだがプロテスタントなど30000以上の分派の教会があるという。
だから宗教者の戒律なども、そうやって徐々に意味もなく増えて行ったのだろう。
いや意味はあったのだろうが、時代を経るうちに形式化していったといえるだろう。
カトリックもその時代の教皇の考え方でいろいろ解釈も生まれるものだし、
所詮人間は人間、神にはなれないのだから妻帯するのは自然ではないか。
ここいら辺でカトリックも妻帯を認めてみてはいかがなものだろうか?
<参考エントリ>
聖書は神の言葉か?
http://ryotaroneko.ti-da.net/e2784494.html

ま、私は宗教心は誰しも必要だと思うし、どの宗派でも良いと思う。
信仰は個人的なものと考えているからだ。それが教団を作り、
階級や活動ノルマができれば確実に堕落すると言っておこう。
また信仰心が大事なのは、共産主義みたいに人間万能論に陥れば、
人間の傲慢さが増長され、時に残酷にもなれるからである。
もっとも一部の原理主義みたいに狂信的になっても同じだが。
何事もほどほどに、適当に、偏らない中道の生き方がよい、
とお釈迦様も言ってます。イエスも似たような事言ってないだろうか?
とにかく・・・
笑顔と謙虚さを忘れずに、
いつも感謝して生きよう!

<お知らせ>
読者の皆様、一時帰国しますので数日休みます。
ではまた、よろしくお願いいたします。
Posted by トラネコ at 10:00│Comments(11)
│思想・宗教
この記事へのコメント
私は仏教はそれほど好みませんが、お釈迦様の言われたことで、中庸の徳というのは、正しいと思います。
極端な禁欲と、欲求欲望の暴走は、実は同じ心性の両面なのでしょう。
文明とそれによる病とは、フロイトの述べた言葉だったでしょうか。
聖職者に限らず、我々文明人は、動物ではありませんから、
生物学的欲求の命ずるがままに行動することを、必ずしも良しとはしません。
食、性、排泄その他の欲求は、ある程度抑えられなければならないのは、当然のことでしょう。
しかしそれが過度になると、本来大海に流れ入るはずの川の流れがせき止められ、ダムのように圧力の高まった状態で出口を失ったエネルギーが、とんでもないところから暴発流出し、異常な倒錯や、心的執念となり、本末転倒の事態を引き起こすようです。
特にこれが起こりやすいのが、過度に理想化された世界、宗教に支配された世界なのかもしれません。
中世のヨーロッパでの、魔女狩りや異端審問の、異常な残虐拷問、特に女性に対するそれなどは、当時の極端な禁欲生活と無関係ではないように思われます。
日本でも、ご存じかもしれませんが、稚児灌頂(ちごかんじょう)という、仏教由来の儀式がありました。
これは一説にすぎませんが、かのスーパー僧侶の空海が、シナから身の回りを世話する?少年達を連れてきたのが、日本におけるこの手の文化の発祥とうことです(ということは、シナではすでに行われていた?)。
これが近代以前まで、ある程度の規模で、仏僧に認められていたというのですから・・・
そう言えば、かの「雨月物語」の一篇「青頭巾」に出てくるのは、この少年愛が進展した、恐ろしい性倒錯の僧侶の化け物でした。いったい、なんのために、煩悩を抑えたのか、これではかえって、本末転倒ではないか、と思えるような事態が、作り話ではなく、現実に、昔からあったのかもしれません。
しかし、人間とは、そのようなものをも受け入れ、文化や芸術にまでしているのですから、難しいものですね。
極端な禁欲と、欲求欲望の暴走は、実は同じ心性の両面なのでしょう。
文明とそれによる病とは、フロイトの述べた言葉だったでしょうか。
聖職者に限らず、我々文明人は、動物ではありませんから、
生物学的欲求の命ずるがままに行動することを、必ずしも良しとはしません。
食、性、排泄その他の欲求は、ある程度抑えられなければならないのは、当然のことでしょう。
しかしそれが過度になると、本来大海に流れ入るはずの川の流れがせき止められ、ダムのように圧力の高まった状態で出口を失ったエネルギーが、とんでもないところから暴発流出し、異常な倒錯や、心的執念となり、本末転倒の事態を引き起こすようです。
特にこれが起こりやすいのが、過度に理想化された世界、宗教に支配された世界なのかもしれません。
中世のヨーロッパでの、魔女狩りや異端審問の、異常な残虐拷問、特に女性に対するそれなどは、当時の極端な禁欲生活と無関係ではないように思われます。
日本でも、ご存じかもしれませんが、稚児灌頂(ちごかんじょう)という、仏教由来の儀式がありました。
これは一説にすぎませんが、かのスーパー僧侶の空海が、シナから身の回りを世話する?少年達を連れてきたのが、日本におけるこの手の文化の発祥とうことです(ということは、シナではすでに行われていた?)。
これが近代以前まで、ある程度の規模で、仏僧に認められていたというのですから・・・
そう言えば、かの「雨月物語」の一篇「青頭巾」に出てくるのは、この少年愛が進展した、恐ろしい性倒錯の僧侶の化け物でした。いったい、なんのために、煩悩を抑えたのか、これではかえって、本末転倒ではないか、と思えるような事態が、作り話ではなく、現実に、昔からあったのかもしれません。
しかし、人間とは、そのようなものをも受け入れ、文化や芸術にまでしているのですから、難しいものですね。
Posted by 丑寅の金さん at 2017年09月24日 12:03
>「独身制」こそ聖職者の性犯罪の元凶
半島ケダモノにこの法則が当てはまらないのは言うまでもありませんね。
性犯罪そのものが「国技」になってるのですから。
そのケダモノに媚を売るあまり性癖まで似てきたパヨクが仏門に入ると「破戒僧」ならぬ「破戒イロキチガイ尼ババア」になるのでしょうな。
半島ケダモノにこの法則が当てはまらないのは言うまでもありませんね。
性犯罪そのものが「国技」になってるのですから。
そのケダモノに媚を売るあまり性癖まで似てきたパヨクが仏門に入ると「破戒僧」ならぬ「破戒イロキチガイ尼ババア」になるのでしょうな。
Posted by KOBA at 2017年09月24日 22:20
丑寅の金さん様
同意です。
そうですね、動物と人間の境界線は理性機能の有無でしょうね。
人間が動物から進化したものだとすれば、当然人間にも獣性があり、またそれを基盤に進化してきたのですから獣性を分離することは不可能でしょう。しかし動物と異なるのは、その獣性(本能と言ってもいいでしょう)をいかにコントロールし抑制機能が働くかというところですね。本能のままに感情むき出しに生きている、今だ獣のような人間型の生物がほぼ全国民の国が近隣諸国でしょう。こういう連中は理性もないし言葉も通じないのですから真面目に対応する方がバカなのです。
>中世のヨーロッパでの、魔女狩りや・・・当時の極端な禁欲生活と無関係ではないように思われます
そうですね。
まさに物理の作用反作用の法則で、過剰な我慢はその反動もすごいでしょう。空海の稚児灌頂の話は知りませんでしたが、空海は「十住心論」の中で人間の精神的発達段階を、ラズローの欲求説をさらに詳細に仏教的にのべています。また空海は性欲を否定しておらず、すべての存在を肯定する立場で「理趣経」という経典を研究していました。まあこれの貸し借りで最澄と絶交したという逸話もありました。
KOBA様
同意です。
朝鮮土人は人間未満ですから、独身であれ妻帯であれ、性犯罪を犯します。
それが彼らの文化であり遺伝子的な特性ですからね。瀬戸内某は一種の性的人格破綻者だと思いますね。
同意です。
そうですね、動物と人間の境界線は理性機能の有無でしょうね。
人間が動物から進化したものだとすれば、当然人間にも獣性があり、またそれを基盤に進化してきたのですから獣性を分離することは不可能でしょう。しかし動物と異なるのは、その獣性(本能と言ってもいいでしょう)をいかにコントロールし抑制機能が働くかというところですね。本能のままに感情むき出しに生きている、今だ獣のような人間型の生物がほぼ全国民の国が近隣諸国でしょう。こういう連中は理性もないし言葉も通じないのですから真面目に対応する方がバカなのです。
>中世のヨーロッパでの、魔女狩りや・・・当時の極端な禁欲生活と無関係ではないように思われます
そうですね。
まさに物理の作用反作用の法則で、過剰な我慢はその反動もすごいでしょう。空海の稚児灌頂の話は知りませんでしたが、空海は「十住心論」の中で人間の精神的発達段階を、ラズローの欲求説をさらに詳細に仏教的にのべています。また空海は性欲を否定しておらず、すべての存在を肯定する立場で「理趣経」という経典を研究していました。まあこれの貸し借りで最澄と絶交したという逸話もありました。
KOBA様
同意です。
朝鮮土人は人間未満ですから、独身であれ妻帯であれ、性犯罪を犯します。
それが彼らの文化であり遺伝子的な特性ですからね。瀬戸内某は一種の性的人格破綻者だと思いますね。
Posted by トラネコ at 2017年09月25日 01:09
at 2017年09月25日 01:09
 at 2017年09月25日 01:09
at 2017年09月25日 01:09イスラムのムハンマドも、若い頃は
「男一匹何でもお任せ。一声掛けりゃ、子分が●●人集まる」
一寸した街の顔役だったそうで、最初の妻は15歳年上の金持ちの
未亡人だそうでして、まあ、モテたんでしょう。
まあ、いずれにせよ「無欲=欲三昧の生活から脱却≒欲に飽きた」
じゃないでしょうか。
それと、
>また信仰心が大事なのは、共産主義みたいに人間万能論に陥れば、
>人間の傲慢さが増長され、時に残酷にもなれるからである。
仰せの通り、「あとは神のみぞ知る」という部分を持たねば、傲慢になって
自身を神格化する基地概が出てきます。毛沢東とかポルポトとか。
「男一匹何でもお任せ。一声掛けりゃ、子分が●●人集まる」
一寸した街の顔役だったそうで、最初の妻は15歳年上の金持ちの
未亡人だそうでして、まあ、モテたんでしょう。
まあ、いずれにせよ「無欲=欲三昧の生活から脱却≒欲に飽きた」
じゃないでしょうか。
それと、
>また信仰心が大事なのは、共産主義みたいに人間万能論に陥れば、
>人間の傲慢さが増長され、時に残酷にもなれるからである。
仰せの通り、「あとは神のみぞ知る」という部分を持たねば、傲慢になって
自身を神格化する基地概が出てきます。毛沢東とかポルポトとか。
Posted by 猫宮とらお at 2017年09月25日 09:40
>トラネコ様
「聖書は神言葉か?」と言う題のスレを読ませていただきましたが、ご指摘は何れも正鵠を得て居ると思います。
先ず、①書いたものは必ず、改竄を受ける。 ②言語の壁があって、訳出すればニュアンスが大幅に変わるが、それを検証できる能力を持った人も機関もなしに、永い間放置された。 ③元々その宗教の教えを説いたものの意図は神の教えを伝えたかったのではなく、その当時、世に蔓延って混乱して居た宗教を改革し、マトモなものにしようとしたダケだったから、①②の経験から、書いたものを遺さなかったのに、後世の弟子や教徒が勝手に創り上げた、作者不明の言葉としか言いようがない。 ダカラ「神の声」で、あったり、「宇宙の真理」である可能性は殆ど無かろう。
キリスト教に在っては、異宗派の士師だったパウロが、4人の使徒から聞き取った話を新約聖書に纏め、「神の声」と偽っているし、彼自身の知見であるユダヤ教的な成分も、可成り盛り込まれている。 仏教に在っては、全て、如是我聞(私はこの様に聞いた)と、経の先頭にあるように、全て伝聞である上、仏教自体が、「解釈自由」との原則だったから、似非仏教も似非経典も存在するが、当然、当事者たちは、釈迦の教えである事を主張する。
要は譬えイエスや釈尊が、神の言葉や宇宙の真理を説いても、其れを信仰するものが現れた時に、教えや心理は「絶対的なモノ」に変質しているのである。
BC4世紀に生きた釈迦と紀元前後に生きたイエスとでは、約400年の隔たりが有るにも拘らず、その説いている本質は「愛」である。
発生が古い仏教の方が、より踏み込んだ「利他愛」を説いているのはマルクス史観でいえば、オカシイのですが、背後にある社会のレベルに拠ったものと考えられば、納得できます。 亦、そも両者の文明には、詳密な交流はなかったと思います。
然しオソラク、イエスも同じ事を説いていたと思われるのに、それが伝わって居ないのは、イエスの教えを伝えた社会のレベルが、イエスの愛についての水準=無償の愛を理解できなかったと思われます。
トラネコさんが福音派の女性と宗教についての議論を為されたとの事ですが、私は、キリスト教は、世界宗教としては欠陥宗教だと思って居ます。 何故なら、かなり早い時期に、異教の排他性を主張しているからだし、性差別も咋に肯定して居ます。
先ず異教や異教徒の排他を認めれば、如何なる異教も全て「悪魔の教え」となるわけで、異民族の大虐殺を何回も繰り返す原因になって居ます。例を挙げれば、十字軍の派遣、スペイン人に拠る新大陸の原住民の大量虐殺、文化破壊。 中世の同じキリスト教徒同士の戦争、アメリカ移民の原住民(インディアン)の殺りく・・ト枚挙にいとまがない程です。
次に、性差別ですがパウロはイエスを磔刑に懸けたユダヤ教ファリサイ派の士師として、長く禁女性の身であったと思われ、完全にその主観に立って「女性は男を惑わす悪魔の存在である」と決め付けて居ます。
それが元で、未だにキリスト教圏では、女性は差別の対象です。 中世に欧州で流行した「黒死病=ペスト」の原因が、細菌である事を発見できていなかった欧州では、「魔女」と言う妄想の産物を現実化させ、無実の女性を火焙りなどの残酷な刑で多数殺害して居ます。 此の迷信が、300年以上も続いたのですが、キリスト教は何もこの蛮行を止める要素にはなり得なかった。
日本に来た欧州人が、「日本人には、クリスチャニティが伝わって居ない筈なのに、人々は、庶民層に至るまで理性的で、何より正直で、親切だ」と例外なく感嘆の声を挙げて居るのです。
更にあの黒船のペリーは、「東洋の3国の社会を観て来たが、日本は他の2国とは全く水準の違う国だ、女性は家庭内でその地位を認められており、経済的な切り盛りをやって居る点では、欧州以上である」と、述懐して居ます。
是は、キリスト教しか知らないモノにとっては驚嘆なのであるかもしれないが、現在の様に双方の民族の歴史を知れば、当たり前なのですがね。
キリスト教の聖職者の身の下問題ですが、日本では親鸞の時代、平安時代(800~1100)位には、僧の妻帯が認められていたのです。 日本で仏教が堕落したのは、江戸期の初めに起こった天草の乱で、その宗教の怖さをたっぷり味あわされ、昔日の一向一揆の例示から、松平伊豆守が提唱して行った「宗門改め」により、各家の宗派が固定して終ったのです。
つまり宗教の原動力となる布教が出来なくなって終ったので、結局、托鉢に回る事も無くなり、葬式と結婚式位しか、僧侶の出番はくなって終い、更に、葬式を出すのに坊主が経を読む事を有料にしたのが、仏教を職業にした事で、限りなく堕落させたと思います。
キリスト教も仏教も、今は公然と批判されていますが、ダカラと言って、宗教改革などする気もないのが、正直なところでしょう。
「聖書は神言葉か?」と言う題のスレを読ませていただきましたが、ご指摘は何れも正鵠を得て居ると思います。
先ず、①書いたものは必ず、改竄を受ける。 ②言語の壁があって、訳出すればニュアンスが大幅に変わるが、それを検証できる能力を持った人も機関もなしに、永い間放置された。 ③元々その宗教の教えを説いたものの意図は神の教えを伝えたかったのではなく、その当時、世に蔓延って混乱して居た宗教を改革し、マトモなものにしようとしたダケだったから、①②の経験から、書いたものを遺さなかったのに、後世の弟子や教徒が勝手に創り上げた、作者不明の言葉としか言いようがない。 ダカラ「神の声」で、あったり、「宇宙の真理」である可能性は殆ど無かろう。
キリスト教に在っては、異宗派の士師だったパウロが、4人の使徒から聞き取った話を新約聖書に纏め、「神の声」と偽っているし、彼自身の知見であるユダヤ教的な成分も、可成り盛り込まれている。 仏教に在っては、全て、如是我聞(私はこの様に聞いた)と、経の先頭にあるように、全て伝聞である上、仏教自体が、「解釈自由」との原則だったから、似非仏教も似非経典も存在するが、当然、当事者たちは、釈迦の教えである事を主張する。
要は譬えイエスや釈尊が、神の言葉や宇宙の真理を説いても、其れを信仰するものが現れた時に、教えや心理は「絶対的なモノ」に変質しているのである。
BC4世紀に生きた釈迦と紀元前後に生きたイエスとでは、約400年の隔たりが有るにも拘らず、その説いている本質は「愛」である。
発生が古い仏教の方が、より踏み込んだ「利他愛」を説いているのはマルクス史観でいえば、オカシイのですが、背後にある社会のレベルに拠ったものと考えられば、納得できます。 亦、そも両者の文明には、詳密な交流はなかったと思います。
然しオソラク、イエスも同じ事を説いていたと思われるのに、それが伝わって居ないのは、イエスの教えを伝えた社会のレベルが、イエスの愛についての水準=無償の愛を理解できなかったと思われます。
トラネコさんが福音派の女性と宗教についての議論を為されたとの事ですが、私は、キリスト教は、世界宗教としては欠陥宗教だと思って居ます。 何故なら、かなり早い時期に、異教の排他性を主張しているからだし、性差別も咋に肯定して居ます。
先ず異教や異教徒の排他を認めれば、如何なる異教も全て「悪魔の教え」となるわけで、異民族の大虐殺を何回も繰り返す原因になって居ます。例を挙げれば、十字軍の派遣、スペイン人に拠る新大陸の原住民の大量虐殺、文化破壊。 中世の同じキリスト教徒同士の戦争、アメリカ移民の原住民(インディアン)の殺りく・・ト枚挙にいとまがない程です。
次に、性差別ですがパウロはイエスを磔刑に懸けたユダヤ教ファリサイ派の士師として、長く禁女性の身であったと思われ、完全にその主観に立って「女性は男を惑わす悪魔の存在である」と決め付けて居ます。
それが元で、未だにキリスト教圏では、女性は差別の対象です。 中世に欧州で流行した「黒死病=ペスト」の原因が、細菌である事を発見できていなかった欧州では、「魔女」と言う妄想の産物を現実化させ、無実の女性を火焙りなどの残酷な刑で多数殺害して居ます。 此の迷信が、300年以上も続いたのですが、キリスト教は何もこの蛮行を止める要素にはなり得なかった。
日本に来た欧州人が、「日本人には、クリスチャニティが伝わって居ない筈なのに、人々は、庶民層に至るまで理性的で、何より正直で、親切だ」と例外なく感嘆の声を挙げて居るのです。
更にあの黒船のペリーは、「東洋の3国の社会を観て来たが、日本は他の2国とは全く水準の違う国だ、女性は家庭内でその地位を認められており、経済的な切り盛りをやって居る点では、欧州以上である」と、述懐して居ます。
是は、キリスト教しか知らないモノにとっては驚嘆なのであるかもしれないが、現在の様に双方の民族の歴史を知れば、当たり前なのですがね。
キリスト教の聖職者の身の下問題ですが、日本では親鸞の時代、平安時代(800~1100)位には、僧の妻帯が認められていたのです。 日本で仏教が堕落したのは、江戸期の初めに起こった天草の乱で、その宗教の怖さをたっぷり味あわされ、昔日の一向一揆の例示から、松平伊豆守が提唱して行った「宗門改め」により、各家の宗派が固定して終ったのです。
つまり宗教の原動力となる布教が出来なくなって終ったので、結局、托鉢に回る事も無くなり、葬式と結婚式位しか、僧侶の出番はくなって終い、更に、葬式を出すのに坊主が経を読む事を有料にしたのが、仏教を職業にした事で、限りなく堕落させたと思います。
キリスト教も仏教も、今は公然と批判されていますが、ダカラと言って、宗教改革などする気もないのが、正直なところでしょう。
Posted by ナポレオン・ソロ at 2017年09月25日 16:50
そもそも、性犯罪とか何とかっていうのは、日本において、延暦寺はじめとして肉食妻帯なんて当たり前だったり、中世の権力者が寺社に対して火をかけたり攻め上ったのも、生臭坊主が蔓延っていて、政治というナマグサに触れまくって為政者の怒りに触れた歴史があるので、講釈の内容がどうであれ、うさん臭いとしか取れません
そもそも延暦寺がここまでになったのは、最澄が組織づくりをキッチリやったのであって、しかも組織づくりをしっかりやらざるを得なかった理由として、かの有名な「泰範事件」という、最澄が、風信帖っていう手紙貰って、弟子で、最澄のお気に入りの泰範を空海のもとへ一年間修業に行くはずが美男子で、空海にも気に入られて帰らなくなって、最澄は「久隔帖」という泰範帰ってきてくれーっていうラブレター書いて結局戻らなかった顛末から、最澄が反省して組織を作ったわけで、しかもナマグサが元ですから、どうしょうもないですし、そもそも人間の理に叶ってないから、山門の連中は変な事するし、キリスト教が公認されたのだって、経済的な理由からっていう観点もあるくらいです。英国国教会なんて、ヘンリー8世が離婚したいって喚いて、エリザベス1世の母親のアン・ブーリンを処刑したりメチャクチャやってたわけです。
それに、江戸時代までの寺社は、ただの893に過ぎないですから、あんなの持ち上げすぎてるわけです。
メチャクチャな禁欲が崇高だと言ってしまってるからおかしくなるわけですから、セーフティーガードもロクすっぽ機能させられないから聖職者の性犯罪なんてのがネタに上がるわけですし、それに比べたら、真宗立川流なんて、逆におおっぴろげにしてるので大したもんだし、後醍醐天皇だって立川流の文観と昵懇になって、倒幕の密議をおねーちゃん侍らせて、いかがわしいことしながらやってたわけですし、一休宗純だって、写真に上がってる瀬戸内晴美の師である今東光だって現代から見たらいかがわしさ満点。ですが逆にその方が健全だと思います。
かといって左翼のような事を言うつもりは一切なくて、共有物として女をみなすような共産党とは相いれないです。
そもそも延暦寺がここまでになったのは、最澄が組織づくりをキッチリやったのであって、しかも組織づくりをしっかりやらざるを得なかった理由として、かの有名な「泰範事件」という、最澄が、風信帖っていう手紙貰って、弟子で、最澄のお気に入りの泰範を空海のもとへ一年間修業に行くはずが美男子で、空海にも気に入られて帰らなくなって、最澄は「久隔帖」という泰範帰ってきてくれーっていうラブレター書いて結局戻らなかった顛末から、最澄が反省して組織を作ったわけで、しかもナマグサが元ですから、どうしょうもないですし、そもそも人間の理に叶ってないから、山門の連中は変な事するし、キリスト教が公認されたのだって、経済的な理由からっていう観点もあるくらいです。英国国教会なんて、ヘンリー8世が離婚したいって喚いて、エリザベス1世の母親のアン・ブーリンを処刑したりメチャクチャやってたわけです。
それに、江戸時代までの寺社は、ただの893に過ぎないですから、あんなの持ち上げすぎてるわけです。
メチャクチャな禁欲が崇高だと言ってしまってるからおかしくなるわけですから、セーフティーガードもロクすっぽ機能させられないから聖職者の性犯罪なんてのがネタに上がるわけですし、それに比べたら、真宗立川流なんて、逆におおっぴろげにしてるので大したもんだし、後醍醐天皇だって立川流の文観と昵懇になって、倒幕の密議をおねーちゃん侍らせて、いかがわしいことしながらやってたわけですし、一休宗純だって、写真に上がってる瀬戸内晴美の師である今東光だって現代から見たらいかがわしさ満点。ですが逆にその方が健全だと思います。
かといって左翼のような事を言うつもりは一切なくて、共有物として女をみなすような共産党とは相いれないです。
Posted by やま at 2017年09月25日 22:33
猫宮とらお様
へえ~ムハマンドも中々のプレイボーイじゃないですか。
釈迦も王子として酒池肉林三昧でしたから、絶対イエスも相当な遊び人だったと思いますね。だから30歳くらい前までの具体的な生活の記述がないのです。でもまあそうなら、私はこの三人の開祖がさすがだと感心し納得もしますね。生まれたときから聖人君子など嘘っぱちもいいところです。また共産主義は宗教も神も認めませんから、指導者の神格化がおこなわれるのは旧ソ連もシナも日本共産党も皆同じです。所詮共産主義も宗教みたいなものですわwww
>平安時代(800~1100)位には、僧の妻帯が認められていたのです。
これは知りませんでした。
平安時代は空海最澄の密教が興った頃ですが、この頃は南都六宗が相当勢力があり、聖武天皇は彼らの政治介入が鬱陶しくて平安京遷都したと言います。この頃に既に僧侶の妻帯ですか、何か資料があれば教えて下さい。
ナポレオン・ソロ様
同意です。
信長の比叡山焼き討ち、一向一揆の弾圧、これらは宗教が政治に口出ししてきたからに他なりません。信長が結構宗教に関心があって、バテレンの宣教師を城に招待し西洋事情と同時にキリスト教(耶蘇教)の講義を受けていたと言いますし、日蓮宗の僧侶と論争させて宗教の優劣を競わせてみたりしたそうです。信長は結構寛大な心で様々な観点から宗教を見ていたみたいですね。しかし宗教が政治に介入することは絶対に許さない非情に毅然とした態度を示したのが比叡山や一向宗への徹底的な弾圧でした。こういう白黒けじめをハッキリした人だったんですね。
やま様
私も空海が結構すきでして、若いころは空海伝や密教関連の本は結構読んでいましたが、ご指摘の「泰範事件」、一説にはこれが原因で空海と最澄の仲が破綻したといわれ、なにやら男色の色恋沙汰みたいな雰囲気もあります。一方この泰範を通じて最澄が借りたかった理趣経の経典を空海は断固断った事が原因だとし、その後泰範は最澄の元を離れ、空海に就いたことが原因ともいわれています。まあこれだけエライ人らですから、あまり世俗の問題ではないでしょう。
最澄は当時は学問僧としてかなりの秀才だったようで、空海はこれが気に入らなかった、というか頭だけの理論で悟ろうとする最澄の修行者としての在り方に批判だったといいます。とくに理趣経はインドのタントリズムが原点のように、ご指摘のように文寛が、日本最大の邪教真言密教立川流を編み出した如く、あの聡明な後醍醐天皇を麻薬とセックス三昧でボロボロに堕落させ、下手するとセックス宗教に堕落する危険性があったからですね。まあ何事もほどほどにということがここでも言えます。やはり仏陀やエライわ!
へえ~ムハマンドも中々のプレイボーイじゃないですか。
釈迦も王子として酒池肉林三昧でしたから、絶対イエスも相当な遊び人だったと思いますね。だから30歳くらい前までの具体的な生活の記述がないのです。でもまあそうなら、私はこの三人の開祖がさすがだと感心し納得もしますね。生まれたときから聖人君子など嘘っぱちもいいところです。また共産主義は宗教も神も認めませんから、指導者の神格化がおこなわれるのは旧ソ連もシナも日本共産党も皆同じです。所詮共産主義も宗教みたいなものですわwww
>平安時代(800~1100)位には、僧の妻帯が認められていたのです。
これは知りませんでした。
平安時代は空海最澄の密教が興った頃ですが、この頃は南都六宗が相当勢力があり、聖武天皇は彼らの政治介入が鬱陶しくて平安京遷都したと言います。この頃に既に僧侶の妻帯ですか、何か資料があれば教えて下さい。
ナポレオン・ソロ様
同意です。
信長の比叡山焼き討ち、一向一揆の弾圧、これらは宗教が政治に口出ししてきたからに他なりません。信長が結構宗教に関心があって、バテレンの宣教師を城に招待し西洋事情と同時にキリスト教(耶蘇教)の講義を受けていたと言いますし、日蓮宗の僧侶と論争させて宗教の優劣を競わせてみたりしたそうです。信長は結構寛大な心で様々な観点から宗教を見ていたみたいですね。しかし宗教が政治に介入することは絶対に許さない非情に毅然とした態度を示したのが比叡山や一向宗への徹底的な弾圧でした。こういう白黒けじめをハッキリした人だったんですね。
やま様
私も空海が結構すきでして、若いころは空海伝や密教関連の本は結構読んでいましたが、ご指摘の「泰範事件」、一説にはこれが原因で空海と最澄の仲が破綻したといわれ、なにやら男色の色恋沙汰みたいな雰囲気もあります。一方この泰範を通じて最澄が借りたかった理趣経の経典を空海は断固断った事が原因だとし、その後泰範は最澄の元を離れ、空海に就いたことが原因ともいわれています。まあこれだけエライ人らですから、あまり世俗の問題ではないでしょう。
最澄は当時は学問僧としてかなりの秀才だったようで、空海はこれが気に入らなかった、というか頭だけの理論で悟ろうとする最澄の修行者としての在り方に批判だったといいます。とくに理趣経はインドのタントリズムが原点のように、ご指摘のように文寛が、日本最大の邪教真言密教立川流を編み出した如く、あの聡明な後醍醐天皇を麻薬とセックス三昧でボロボロに堕落させ、下手するとセックス宗教に堕落する危険性があったからですね。まあ何事もほどほどにということがここでも言えます。やはり仏陀やエライわ!
Posted by トラネコ at 2017年09月26日 16:29
at 2017年09月26日 16:29
 at 2017年09月26日 16:29
at 2017年09月26日 16:29>トラネコ様
平安時代(800-1200)と言うのは、私が書いたものですし、是は所謂、消し忘れです。済みません。
最初、親鸞が平安~鎌倉時代の境目の時代の人だと言う認識はあったのですが、書いて居る裡に空海や最澄に話が拡大、然し、彼らは平安時代でも初期の人達であった事を思い出して文章を大幅に直したのですが、消し忘れて終い、実際は、平安末期の人である親鸞が始めた妻帯が、丸で、平安初期から妻帯が認めてられて居たかのような話になりました。 注意が足りませんでした。 御免なさい。
平安時代(800-1200)と言うのは、私が書いたものですし、是は所謂、消し忘れです。済みません。
最初、親鸞が平安~鎌倉時代の境目の時代の人だと言う認識はあったのですが、書いて居る裡に空海や最澄に話が拡大、然し、彼らは平安時代でも初期の人達であった事を思い出して文章を大幅に直したのですが、消し忘れて終い、実際は、平安末期の人である親鸞が始めた妻帯が、丸で、平安初期から妻帯が認めてられて居たかのような話になりました。 注意が足りませんでした。 御免なさい。
Posted by ナポレオン・ソロ at 2017年09月27日 13:34
ナポレオン・ソロ様
了解しました!
了解しました!
Posted by トラネコ at 2017年09月27日 22:52
at 2017年09月27日 22:52
 at 2017年09月27日 22:52
at 2017年09月27日 22:52「坊主と性欲」というのは、庶民にとって格好の笑いのネタだったようで、偉いお坊さんが自分の跡取りを決めようと、寺の若い坊さんの○○○○に糸で鈴を括りつけ、目の前で遊女にセクシーポーズをさせたところ、忽ち鈴が鳴り響く中、1人だけ平然と座禅を組む坊さんがおり、「この者こそ跡継ぎに相応しい」と○○○○を改めたところ、糸はちぎれていた・・・、という艶笑小噺があります。本願寺の坊さんも、首に白粉を付けて祇園から朝帰りしてましたが、賢明な京都人は見て見ぬふりをしてました。「坊主も生身の人間」ということを、庶民はよく理解しており、お伊勢参宮の後には、古市遊郭で「精進落とし」と称し、女郎を買ってます。「本音」と「建て前」のバランスを取ることは、人間の生活の知恵ですが、地位や権力を笠に着て、歪んだ劣情を満たすことは許されません。
Posted by NTRC特撮軍団長・ヤラセロウ大元帥 at 2017年09月30日 23:14
NTRC特撮軍団長・ヤラセロウ大元帥様
同意です。
ま、坊さんも人の子ですからね。
親鸞が妻帯、その後の徳川政権の寺受け制度、檀家制度が定着してから、日本仏教界の堕落が始まったといえるでしょう。現在でも幼稚園経営や駐車場経営の寺はいいとして、中には風俗を経営する寺とか、タレントで稼いでお縄頂戴した織田無道みたいな俗物も結構いますしねw。まそんなこのですw
同意です。
ま、坊さんも人の子ですからね。
親鸞が妻帯、その後の徳川政権の寺受け制度、檀家制度が定着してから、日本仏教界の堕落が始まったといえるでしょう。現在でも幼稚園経営や駐車場経営の寺はいいとして、中には風俗を経営する寺とか、タレントで稼いでお縄頂戴した織田無道みたいな俗物も結構いますしねw。まそんなこのですw
Posted by トラネコ at 2017年10月01日 16:05
at 2017年10月01日 16:05
 at 2017年10月01日 16:05
at 2017年10月01日 16:05