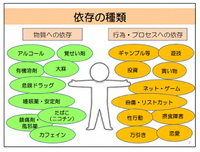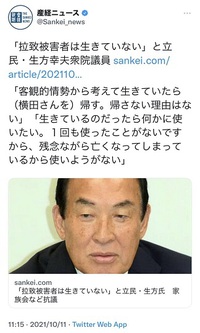絵画修復はプロの仕事、「餅は餅屋」は世界共通
2020年06月28日
素人が絵画を修復しようとして大失敗する事態がまたもや発生、
専門家が素人によるアート修復の規制を訴える
絵画や彫刻などの芸術作品は時間が経つにつれて劣化してしまうため、貴重な作品を後世に残すために定期的な修復作業を行う必要があります。しかし、時には修復作業が専門の知識と技術を持った人ではなく、単なる素人に任されてしまうケースもあります。そんな素人による芸術作品の修復事例が相次いでいるスペインで、またもや「素人による修復作業で芸術作品が台無しになってしまった」という事例が報告されました。
スペインでは2012年、教会にあったエリアス・ガルシア・マルティネスのフレスコ画「この人を見よ」の修復作業を素人である80歳のセシリア・ヒメネスさんが行い、「まるで血色の悪いサルのようなキリスト」が誕生してしまいました。世界的に有名となったこの修復後の絵画には多くの賛否が寄せられ、皮肉にも話題となった絵画を見るために観光客が殺到し、ワインのラベルやマグカップといったグッズまで作成されています。
また、2018年には16世紀に作られた木彫りの聖ジョージ像の清掃を美術教師に任せたところ、美術教師が誤った塗料を使って修復作業を行い、彫刻を台無しにしてしまうという事態も発生。結果的に彫刻は専門の機関に修復が依頼され、木像はほぼ元どおりにされました。
このように素人による芸術作品の修復失敗が多数報告されているスペインで、新たな悲劇が発生したとのこと。スペインのバレンシアに住むある美術収集家は、バロック期の画家であるバルトロメ・エステバン・ムリーリョの作品「The Immaculate Conception of Los Venerables」の複製画を修復するため、家具修復業者に1200ユーロ(約14万5000円)を支払いました。
ところが、修復された絵画に描かれていた聖母マリアは、明らかに元の絵画とは似ても似つかないものとなっており、持ち主は憤慨して元通りに復元するように命じました。しかし、再度の修復でもやはり失敗し、もはや聖母マリアには見えないただのおばさんのような顔になってしまったとのこと。以下の画像の左が元々描かれていた聖母マリアで、右上が1回目の修復、右下が2回目の修復で描かれた聖母マリア。だんだん悪化している様子がわかります。
ガリシア文化遺産保護修復学校のフェルナンド・カレラ教授は、こうした芸術作品の修復失敗事例は適切な訓練を受けた修復者のみが作業を行う必要性を強調していると指摘。「私はこの男、または彼らが『修復者』と呼ばれるべきではないと考えています。正直に言いましょう。彼らはヘタクソで芸術作品を台無しにします」と、カレラ教授はコメントしています。
<後略>
Gigazine 2020年06月23日
https://gigazine.net/news/20200623-spain-botched-art-restoration/

バルトロメ・エステバン・ムリーリョの作品
「The Immaculate Conception of Los Venerables」の複製画

エリアス・ガルシア・マルティネスのフレスコ画「この人を見よ」

16世紀に作られた木彫りの聖ジョージ像

>ガリシア文化遺産保護修復学校のフェルナンド・カレラ教授は、
こうした芸術作品の修復失敗事例は適切な訓練を受けた修復者のみが
作業を行う必要性を強調していると指摘。「私はこの男、または彼らが
『修復者』と呼ばれるべきではないと考えています。正直に言いましょう。
彼らはヘタクソで芸術作品を台無しにします」と、カレラ教授はコメントしています。
全くその通り!
「専門家が素人によるアート修復の規制を訴える」
それ以前のきわめて基本的な問題だと思うが・・・
>このように素人による芸術作品の修復失敗が多数報告されているスペイン
これな・・・
まず読者諸氏も思ったと思うが、私が不思議に思う事は、
何故このような歴史的にも文化的にも貴重な作品の修復を
ズブの素人に任せてしまうのだろうか?ということである。
この「修復」と称する仕事を見る限り、修復の専門家以前の
まったく絵すら描いたこともないド素人の「仕事」だということだ。
なぜ絵の所有者はそのことがわからないのだろうか?
さらに、請負者は自分が絵も描けないのに何故この仕事を請け負ったのか?
例えば、大工の基礎知識も技術もない者が、誰かに家を建ててほしいと依頼され、
「わかりました!」と二つ返事で仕事を請け負うか? ということである。
スペインもバロック絵画など古い壁画が多く残る国だから、
絵画の伝統的な修復技術は高度なものがあると思うのだが、
なぜこれらの絵画の修復に専門家を依頼しなかったのだろうか?
つまり・・・
依頼者も受注者も、
何にも考えていない、
バカだということだ(笑)

私も以前メキシコの個人の別荘に設置されてある
礼拝堂のマリア像の修復を依頼されたことがあった。
塗料がはげ落ち色が経年劣化していたものだ。
絵の具はアクリル塗料だったので思ったより簡単にできたが、
それでも土日二日×8時間を使って6日かかったのを覚えている。
やはり聖像だけに気軽にはできない、ある種の緊張感があった。
修復過程でマリア像の肌の色で所有者と意見の相違をみた。
メキシコのマリアはグアダルーペの聖母と呼ばれた先住民の女性である。
褐色のマリアと呼ばれている事から、肌は白くはないので故事に従ったが、
所有者は白人の肌にするよう要求してきたので、塗り直した事があった。
マリア像の所有者は私の絵画技術を知った上で依頼してきた。
私が素人ではなく、絵画の専門家という事を確認した上での依頼で、
普通このような内容の仕事を依頼するなら当然の確認事項である。

写真を収めたPCとデジカメを盗難で失ったので、
別の写真を使うが、こんな感じのマリア像である。
ヨーロッパでは中世以来、教会などに宗教画が多く描かれており、
これは当時のほとんどの信者が文盲なのでキリスト教の教えや、
イエス・キリストの物語を学習する為に絵画で表現したのである。
そういう意味では、西欧絵画は宗教画から発展したと言ってよいだろう。
その絵画の修復は昔の伝統的な技術や顔料や材料に精通した、
大学などで専門教育を受けたプロフェッショナルの仕事である。
特にルネサンス期の壁画においては、フレスコ画やテンペラ画が中心であったが、
この当時発明された油絵の具を使ったものもあったり、フレスコとテンペラと、
油彩の混合したものもあったりで、修復作業には絵の具の分析が重要なのだ。
例えば・・・
レオナルド・ダ・ヴィンチの名作「最後の晩餐」には、
フレスコ画の上から性質の違うテンペラ技法を重ねており、
材質の違いなどから剥離が激しく修復が何度も繰り返された。

ダ・ヴィンチ「最後の晩餐」修復前

修復後
閑話休題。
今から12年前の話だが・・・
南朝鮮のソウルにある歴史的建造物・南大門が放火によって焼失した。
その修復作業が行われたが、その中にある壁画の修復作業も同時に行われた。
ところが完成後たったの5か月で塗料が剥脱して問題になった。
そこでいつもの通りだが、
チョンいわく・・・
「日本製の膠を使った所為ニダ!」
<参考記事>
韓国の国宝の復元作業で、日本製の接着剤が使用され問題に
サーチナ 2012年6月14日
https://news.livedoor.com/article/detail/6657696/

事実は胡粉の使い方の基本中の基本を完全無視した、
南鮮の「人間国宝」サマのお仕事が原因だということである。
日本では日本画専攻の学生すら犯さない初歩的ミスである。
これは日本画の素人の私でさえ写真からすぐにわかった。
恐らく朝鮮半島の社会では古代から続く膠をメディウムに使用した、
伝統絵画の技術がきちんと踏襲されていないのではないかと思う。
古いものはすべて破壊する軽薄な文化を持つ事大主義民族ならではである。
<参考エントリ>
やはり伝統技術などない国・韓国(笑)
https://ryotaroneko.ti-da.net/e5426440.html

修復して半年もしない内に剥離した絵画
また木のひび割れは原木伐採後十分に、
乾燥させていないからではないだろうか?
ということで・・・
昔から「餅は餅屋」という諺が語る通り、
ヘタに素人が付け焼刃的な技術を行使すればロクな事はない。
何事もプロ(専門家)の仕事が一番適確で安心なのだ。
あいちトリエンナーレ展に出品された芸術以前の稚拙な「作品」、
あれらもプロの造形専門家ではなく、まったくのド素人の作品である。
私なら展示される方が恥ずかしいと思うがな・・・
またそう考えてみると、今の日本の政治にも政治のプロが実に少ない。
売国サヨク系の野党など、売国奴はいても政治家そのものがいない。
自民党にも金と名声目当ての政治屋が殆どだから何をかいわんやである。
日本にはどの分野にも専門家が、
減少しているのかもしれないな・・・

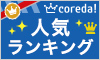

専門家が素人によるアート修復の規制を訴える
絵画や彫刻などの芸術作品は時間が経つにつれて劣化してしまうため、貴重な作品を後世に残すために定期的な修復作業を行う必要があります。しかし、時には修復作業が専門の知識と技術を持った人ではなく、単なる素人に任されてしまうケースもあります。そんな素人による芸術作品の修復事例が相次いでいるスペインで、またもや「素人による修復作業で芸術作品が台無しになってしまった」という事例が報告されました。
スペインでは2012年、教会にあったエリアス・ガルシア・マルティネスのフレスコ画「この人を見よ」の修復作業を素人である80歳のセシリア・ヒメネスさんが行い、「まるで血色の悪いサルのようなキリスト」が誕生してしまいました。世界的に有名となったこの修復後の絵画には多くの賛否が寄せられ、皮肉にも話題となった絵画を見るために観光客が殺到し、ワインのラベルやマグカップといったグッズまで作成されています。
また、2018年には16世紀に作られた木彫りの聖ジョージ像の清掃を美術教師に任せたところ、美術教師が誤った塗料を使って修復作業を行い、彫刻を台無しにしてしまうという事態も発生。結果的に彫刻は専門の機関に修復が依頼され、木像はほぼ元どおりにされました。
このように素人による芸術作品の修復失敗が多数報告されているスペインで、新たな悲劇が発生したとのこと。スペインのバレンシアに住むある美術収集家は、バロック期の画家であるバルトロメ・エステバン・ムリーリョの作品「The Immaculate Conception of Los Venerables」の複製画を修復するため、家具修復業者に1200ユーロ(約14万5000円)を支払いました。
ところが、修復された絵画に描かれていた聖母マリアは、明らかに元の絵画とは似ても似つかないものとなっており、持ち主は憤慨して元通りに復元するように命じました。しかし、再度の修復でもやはり失敗し、もはや聖母マリアには見えないただのおばさんのような顔になってしまったとのこと。以下の画像の左が元々描かれていた聖母マリアで、右上が1回目の修復、右下が2回目の修復で描かれた聖母マリア。だんだん悪化している様子がわかります。
ガリシア文化遺産保護修復学校のフェルナンド・カレラ教授は、こうした芸術作品の修復失敗事例は適切な訓練を受けた修復者のみが作業を行う必要性を強調していると指摘。「私はこの男、または彼らが『修復者』と呼ばれるべきではないと考えています。正直に言いましょう。彼らはヘタクソで芸術作品を台無しにします」と、カレラ教授はコメントしています。
<後略>
Gigazine 2020年06月23日
https://gigazine.net/news/20200623-spain-botched-art-restoration/

バルトロメ・エステバン・ムリーリョの作品
「The Immaculate Conception of Los Venerables」の複製画

エリアス・ガルシア・マルティネスのフレスコ画「この人を見よ」

16世紀に作られた木彫りの聖ジョージ像

>ガリシア文化遺産保護修復学校のフェルナンド・カレラ教授は、
こうした芸術作品の修復失敗事例は適切な訓練を受けた修復者のみが
作業を行う必要性を強調していると指摘。「私はこの男、または彼らが
『修復者』と呼ばれるべきではないと考えています。正直に言いましょう。
彼らはヘタクソで芸術作品を台無しにします」と、カレラ教授はコメントしています。
全くその通り!
「専門家が素人によるアート修復の規制を訴える」
それ以前のきわめて基本的な問題だと思うが・・・
>このように素人による芸術作品の修復失敗が多数報告されているスペイン
これな・・・
まず読者諸氏も思ったと思うが、私が不思議に思う事は、
何故このような歴史的にも文化的にも貴重な作品の修復を
ズブの素人に任せてしまうのだろうか?ということである。
この「修復」と称する仕事を見る限り、修復の専門家以前の
まったく絵すら描いたこともないド素人の「仕事」だということだ。
なぜ絵の所有者はそのことがわからないのだろうか?
さらに、請負者は自分が絵も描けないのに何故この仕事を請け負ったのか?
例えば、大工の基礎知識も技術もない者が、誰かに家を建ててほしいと依頼され、
「わかりました!」と二つ返事で仕事を請け負うか? ということである。
スペインもバロック絵画など古い壁画が多く残る国だから、
絵画の伝統的な修復技術は高度なものがあると思うのだが、
なぜこれらの絵画の修復に専門家を依頼しなかったのだろうか?
つまり・・・
依頼者も受注者も、
何にも考えていない、
バカだということだ(笑)

私も以前メキシコの個人の別荘に設置されてある
礼拝堂のマリア像の修復を依頼されたことがあった。
塗料がはげ落ち色が経年劣化していたものだ。
絵の具はアクリル塗料だったので思ったより簡単にできたが、
それでも土日二日×8時間を使って6日かかったのを覚えている。
やはり聖像だけに気軽にはできない、ある種の緊張感があった。
修復過程でマリア像の肌の色で所有者と意見の相違をみた。
メキシコのマリアはグアダルーペの聖母と呼ばれた先住民の女性である。
褐色のマリアと呼ばれている事から、肌は白くはないので故事に従ったが、
所有者は白人の肌にするよう要求してきたので、塗り直した事があった。
マリア像の所有者は私の絵画技術を知った上で依頼してきた。
私が素人ではなく、絵画の専門家という事を確認した上での依頼で、
普通このような内容の仕事を依頼するなら当然の確認事項である。

写真を収めたPCとデジカメを盗難で失ったので、
別の写真を使うが、こんな感じのマリア像である。
ヨーロッパでは中世以来、教会などに宗教画が多く描かれており、
これは当時のほとんどの信者が文盲なのでキリスト教の教えや、
イエス・キリストの物語を学習する為に絵画で表現したのである。
そういう意味では、西欧絵画は宗教画から発展したと言ってよいだろう。
その絵画の修復は昔の伝統的な技術や顔料や材料に精通した、
大学などで専門教育を受けたプロフェッショナルの仕事である。
特にルネサンス期の壁画においては、フレスコ画やテンペラ画が中心であったが、
この当時発明された油絵の具を使ったものもあったり、フレスコとテンペラと、
油彩の混合したものもあったりで、修復作業には絵の具の分析が重要なのだ。
例えば・・・
レオナルド・ダ・ヴィンチの名作「最後の晩餐」には、
フレスコ画の上から性質の違うテンペラ技法を重ねており、
材質の違いなどから剥離が激しく修復が何度も繰り返された。

ダ・ヴィンチ「最後の晩餐」修復前

修復後
閑話休題。
今から12年前の話だが・・・
南朝鮮のソウルにある歴史的建造物・南大門が放火によって焼失した。
その修復作業が行われたが、その中にある壁画の修復作業も同時に行われた。
ところが完成後たったの5か月で塗料が剥脱して問題になった。
そこでいつもの通りだが、
チョンいわく・・・
「日本製の膠を使った所為ニダ!」
<参考記事>
韓国の国宝の復元作業で、日本製の接着剤が使用され問題に
サーチナ 2012年6月14日
https://news.livedoor.com/article/detail/6657696/

事実は胡粉の使い方の基本中の基本を完全無視した、
南鮮の「人間国宝」サマのお仕事が原因だということである。
日本では日本画専攻の学生すら犯さない初歩的ミスである。
これは日本画の素人の私でさえ写真からすぐにわかった。
恐らく朝鮮半島の社会では古代から続く膠をメディウムに使用した、
伝統絵画の技術がきちんと踏襲されていないのではないかと思う。
古いものはすべて破壊する軽薄な文化を持つ事大主義民族ならではである。
<参考エントリ>
やはり伝統技術などない国・韓国(笑)
https://ryotaroneko.ti-da.net/e5426440.html

修復して半年もしない内に剥離した絵画
また木のひび割れは原木伐採後十分に、
乾燥させていないからではないだろうか?
ということで・・・
昔から「餅は餅屋」という諺が語る通り、
ヘタに素人が付け焼刃的な技術を行使すればロクな事はない。
何事もプロ(専門家)の仕事が一番適確で安心なのだ。
あいちトリエンナーレ展に出品された芸術以前の稚拙な「作品」、
あれらもプロの造形専門家ではなく、まったくのド素人の作品である。
私なら展示される方が恥ずかしいと思うがな・・・
またそう考えてみると、今の日本の政治にも政治のプロが実に少ない。
売国サヨク系の野党など、売国奴はいても政治家そのものがいない。
自民党にも金と名声目当ての政治屋が殆どだから何をかいわんやである。
日本にはどの分野にも専門家が、
減少しているのかもしれないな・・・

Posted by トラネコ at 00:00│Comments(10)
│美術
この記事へのコメント
昔、坂本繁二郎という日本の近代洋画家が、自作を所蔵する美術館からその修復を依頼され、修復するというより、今の自分の考えで描き直してしまったことがありました。それ以来、日本では「モチはモチ屋」というのは、修復は画家ではなく、修復家に任せるべきだ、という意味にも使われています。
それでも、法隆寺の壁画の焼失の修復、というか描き直しにあたって、近代日本画家たちがこぞって取り組んだのは、有名な話ですが、現在の日本画家たちに、同様のことができるかどうかは、相当疑わしいと思われます。
私が日本画に転向して、一番びっくりしたのは、現代日本画家たちは、前近代の技法をほとんど学ばず、古画の模写もほとんどしない、ということでした。あるいは、たとえ模写をするにしても、前近代の基礎技術なくしては、いわゆる表面模写になってしまい、これでは本来の技能や技法は身に付きません。要するに、そんなことは、修復科に進んだ連中に任せておけ、といった姿勢で、芸大や多摩美の大学院を卒業された方でも、原則古い技法ができないので、古画の修復は厳しいと思われます。
要するに、日本画というものが引き継いでいるのは、絵画の絵の部分、色やマチエルの部分であって、基礎技術や骨組みとしての画の部分ではありません。彼らのほとんどは、書はおろか、東洋画の基礎である18手の線描による白描を、まったくやったこともないようで、その代わりに、石膏デッサンなどの近代洋画の基礎をやって美大に入るのですから、現状の教育からすれば、無理からぬことなのです。
それでも、胡粉をすり潰して、膠を一寸づつ垂らしながら、子供のころやった泥団子遊びと同じ要領で、団子を作って百叩きをして、粘土の蛇のように伸ばしてトグロを巻かせ、それでひび割れなければOKで、あとはお湯をかけてあく抜きしてから使う、などの基礎のマチエルくらいは伝授されているようです。詳細は知りませんが、韓国の方は、これをしなかったのでしょうか?
しかし、岩絵の具の練り方や、箔の張り方などの、マチエルがいくらできても、肝心の筆の扱いによる、昔ながらの線描技法ができなければ、古画を描き直すのは難しいでしょう。線を使わない、いわゆる没骨法も、無骨法ではなく、あくまで線描が基礎になっているので、今の人がやると、昔のようにはいかないのです。
日本というのは実に奇妙な国で、西洋画の古典技法は、明治時代に慌てて近代洋画を仕入れ、その基礎の古典技法を仕入れなかった反省からか、ここ半世紀くらいのあいだに、かなりの日本人が欧州で学んできて、日本でも技術程度の差や欧州地方の違いはあれど、そこそこの古典技法が学べるところは、ちらほらと見かけます。
これに対して、日本画以前の前近代日本美術の技法を学べるところは、大学の修復科以外に、ほとんど見当たらず、現在の日本画家ができるのは、膠で描いた近代西洋画としての日本画を教えることくらいです。
従って、こうした環境下では、いかに日本といえども、古画の修復の専門家を、良質な形で育てて、技法を継承していくのが、かなり難しくなっているようです。
それでも、法隆寺の壁画の焼失の修復、というか描き直しにあたって、近代日本画家たちがこぞって取り組んだのは、有名な話ですが、現在の日本画家たちに、同様のことができるかどうかは、相当疑わしいと思われます。
私が日本画に転向して、一番びっくりしたのは、現代日本画家たちは、前近代の技法をほとんど学ばず、古画の模写もほとんどしない、ということでした。あるいは、たとえ模写をするにしても、前近代の基礎技術なくしては、いわゆる表面模写になってしまい、これでは本来の技能や技法は身に付きません。要するに、そんなことは、修復科に進んだ連中に任せておけ、といった姿勢で、芸大や多摩美の大学院を卒業された方でも、原則古い技法ができないので、古画の修復は厳しいと思われます。
要するに、日本画というものが引き継いでいるのは、絵画の絵の部分、色やマチエルの部分であって、基礎技術や骨組みとしての画の部分ではありません。彼らのほとんどは、書はおろか、東洋画の基礎である18手の線描による白描を、まったくやったこともないようで、その代わりに、石膏デッサンなどの近代洋画の基礎をやって美大に入るのですから、現状の教育からすれば、無理からぬことなのです。
それでも、胡粉をすり潰して、膠を一寸づつ垂らしながら、子供のころやった泥団子遊びと同じ要領で、団子を作って百叩きをして、粘土の蛇のように伸ばしてトグロを巻かせ、それでひび割れなければOKで、あとはお湯をかけてあく抜きしてから使う、などの基礎のマチエルくらいは伝授されているようです。詳細は知りませんが、韓国の方は、これをしなかったのでしょうか?
しかし、岩絵の具の練り方や、箔の張り方などの、マチエルがいくらできても、肝心の筆の扱いによる、昔ながらの線描技法ができなければ、古画を描き直すのは難しいでしょう。線を使わない、いわゆる没骨法も、無骨法ではなく、あくまで線描が基礎になっているので、今の人がやると、昔のようにはいかないのです。
日本というのは実に奇妙な国で、西洋画の古典技法は、明治時代に慌てて近代洋画を仕入れ、その基礎の古典技法を仕入れなかった反省からか、ここ半世紀くらいのあいだに、かなりの日本人が欧州で学んできて、日本でも技術程度の差や欧州地方の違いはあれど、そこそこの古典技法が学べるところは、ちらほらと見かけます。
これに対して、日本画以前の前近代日本美術の技法を学べるところは、大学の修復科以外に、ほとんど見当たらず、現在の日本画家ができるのは、膠で描いた近代西洋画としての日本画を教えることくらいです。
従って、こうした環境下では、いかに日本といえども、古画の修復の専門家を、良質な形で育てて、技法を継承していくのが、かなり難しくなっているようです。
Posted by キジトラ at 2020年06月28日 13:26
at 2020年06月28日 13:26
 at 2020年06月28日 13:26
at 2020年06月28日 13:26失礼しました。別エントリーで韓国の剥落の原因が、胡粉の厚塗りと指摘されていますね。ただ、厚塗りも可能な胡粉もあり、それを腐れ胡粉と言います。
膠を足し団子の状態にした胡粉を容器に入れて、土中(胡粉塚)に埋め膠を腐らせた胡粉の事。 普通の胡粉に比べて接着力が上がり、盛り上げし易くひび割れなくなる。
しかし、これは部分厚塗りの特殊技法に使われているようであって、全面的な厚塗りではないと思われます。古典の西洋画で、人体の明部が厚塗りになっているのと、原理は同じだと思いますが、東洋画のものの見方に応じて使われるのでしょう。
盛り上げ胡粉について
http://blog.livedoor.jp/fjok/archives/28781582.html
厚塗りで盛り上げた胡粉は、頂上がへこむ傾向がありますが、それを防ぐためにも、特殊な処理をした胡粉を使うことがあるようです。
膠にせよ、卵にせよ、カゼインにせよ、水性のメジュームを厚塗りにすれば、期間の差はあれど、一般には剥落していきます。西洋画のテンペラ(卵やカゼイン)でも、現存する古典作品は、きわめて薄塗りで、厚塗りのものははげ落ちてしまっています。
上記の特別な処置をした胡粉を除き、東洋画でもこの原則は変わらないと思われます。
ですので、はっきり言えば、戦後の厚塗りの日本画のほとんどは、長持ちしないでしょう。ただ、半年もしないうちに剥落という韓国の例は、それでも極端と思われますが。
膠を足し団子の状態にした胡粉を容器に入れて、土中(胡粉塚)に埋め膠を腐らせた胡粉の事。 普通の胡粉に比べて接着力が上がり、盛り上げし易くひび割れなくなる。
しかし、これは部分厚塗りの特殊技法に使われているようであって、全面的な厚塗りではないと思われます。古典の西洋画で、人体の明部が厚塗りになっているのと、原理は同じだと思いますが、東洋画のものの見方に応じて使われるのでしょう。
盛り上げ胡粉について
http://blog.livedoor.jp/fjok/archives/28781582.html
厚塗りで盛り上げた胡粉は、頂上がへこむ傾向がありますが、それを防ぐためにも、特殊な処理をした胡粉を使うことがあるようです。
膠にせよ、卵にせよ、カゼインにせよ、水性のメジュームを厚塗りにすれば、期間の差はあれど、一般には剥落していきます。西洋画のテンペラ(卵やカゼイン)でも、現存する古典作品は、きわめて薄塗りで、厚塗りのものははげ落ちてしまっています。
上記の特別な処置をした胡粉を除き、東洋画でもこの原則は変わらないと思われます。
ですので、はっきり言えば、戦後の厚塗りの日本画のほとんどは、長持ちしないでしょう。ただ、半年もしないうちに剥落という韓国の例は、それでも極端と思われますが。
Posted by キジトラ at 2020年06月28日 13:51
at 2020年06月28日 13:51
 at 2020年06月28日 13:51
at 2020年06月28日 13:51キジトラ様
同意です。
坂本繁二郎は高校時代に好きな画家でした。馬をよく描いていた作家で確か熊本の方で一生そこからでなかったとか。私は特に淡い色使いに魅了されました。
ところで最近の日本画というのも伝統的な技法を踏襲するよりも、絵の具の材料を膠や岩絵の具を使うというだけの意味での日本画みたいですね。基本的には油絵もアクリル画も水彩画も関係ないような風潮になっています。横山大観などは画学生の頃は二年間は線引きの練習を徹底的にやらされたとかいいます。日本画の線描はそれほど重要だったのです。
以前平山郁夫のシルクロードスケッチ展を見に行きましたが、彼は線描が下手なのがわかります。言葉で説明しにくいのですが、線が一定間隔で点につながれているのです。つまり彼は対象を見ながら一気に線を引くのではなく、5センチ間隔くらいで筆が止まるのです。その止まった場所が点になっているのです。これは線描をしっかり勉強した人ではないのがわかります。
私は京都の染色工房で線描の運筆練習を、毎日古新聞を使ってやらされました。着物に直描きするので失敗は許されないので線描は非常に重要な技術です。お陰様でその後水墨画を始めたときも比較的楽に輪郭線を描くことができました。あの頃の運筆技術は現在アクリルや、その他の顔料を使った絵の場合でも結構役に立っています。
菱田春草の朦朧体は一切線を排した新しいコンセプトの日本画かもしれませんが、それも基礎基本が前提にあってこそといえるでしょう。また基礎基本を学んだことにより、別の分野の技法を取り入れる事も可能になるのです。
まあ伝統技術もそれを踏襲する人とそうでない人の立場によって、技術の習得の考え方も変わってきますよね。伝統的な日本画というのは誤解を恐れずに言えば、工芸的な仕事といえるでしょうか。まずは技術の習得が重要な印象があります。
恐らく朝鮮には伝統的な絵画技術を学ぶ文化的風土はないと思います。何せ職人や技術を軽蔑する信じられない文化ですから、そういう技術に敬意を払う精神性など皆無でしょう。だから出来合いの技術をパクってインスタントに製造するしか産業を発展させる方法がないのでしょう。これではいつまでたってもオリジナルや独自の発展はできないはずです。
同意です。
坂本繁二郎は高校時代に好きな画家でした。馬をよく描いていた作家で確か熊本の方で一生そこからでなかったとか。私は特に淡い色使いに魅了されました。
ところで最近の日本画というのも伝統的な技法を踏襲するよりも、絵の具の材料を膠や岩絵の具を使うというだけの意味での日本画みたいですね。基本的には油絵もアクリル画も水彩画も関係ないような風潮になっています。横山大観などは画学生の頃は二年間は線引きの練習を徹底的にやらされたとかいいます。日本画の線描はそれほど重要だったのです。
以前平山郁夫のシルクロードスケッチ展を見に行きましたが、彼は線描が下手なのがわかります。言葉で説明しにくいのですが、線が一定間隔で点につながれているのです。つまり彼は対象を見ながら一気に線を引くのではなく、5センチ間隔くらいで筆が止まるのです。その止まった場所が点になっているのです。これは線描をしっかり勉強した人ではないのがわかります。
私は京都の染色工房で線描の運筆練習を、毎日古新聞を使ってやらされました。着物に直描きするので失敗は許されないので線描は非常に重要な技術です。お陰様でその後水墨画を始めたときも比較的楽に輪郭線を描くことができました。あの頃の運筆技術は現在アクリルや、その他の顔料を使った絵の場合でも結構役に立っています。
菱田春草の朦朧体は一切線を排した新しいコンセプトの日本画かもしれませんが、それも基礎基本が前提にあってこそといえるでしょう。また基礎基本を学んだことにより、別の分野の技法を取り入れる事も可能になるのです。
まあ伝統技術もそれを踏襲する人とそうでない人の立場によって、技術の習得の考え方も変わってきますよね。伝統的な日本画というのは誤解を恐れずに言えば、工芸的な仕事といえるでしょうか。まずは技術の習得が重要な印象があります。
恐らく朝鮮には伝統的な絵画技術を学ぶ文化的風土はないと思います。何せ職人や技術を軽蔑する信じられない文化ですから、そういう技術に敬意を払う精神性など皆無でしょう。だから出来合いの技術をパクってインスタントに製造するしか産業を発展させる方法がないのでしょう。これではいつまでたってもオリジナルや独自の発展はできないはずです。
Posted by トラネコ at 2020年06月28日 14:42
at 2020年06月28日 14:42
 at 2020年06月28日 14:42
at 2020年06月28日 14:42トラネコ様の主張される「絵画修復には、絵画の元と同じように見えるように修復する高い専門技術が必要」というのはその通りでしょう。 複製が元の絵と変わってしまっては話になりません。
ただ、私には別の意見があります。 バルトロメ・エステバン・ムリーリョの作品「The Immaculate Conception of Los Venerables」の修復画、エリアス・ガルシア・マルティネスのフレスコ画「この人を見よ」の修復画、16世紀に作られた木彫りの聖ジョージ像の修復像が【 近代現代の絵画スタイルをそのまま踏襲している 】ことです。 勿論、修復(複製)としては完全に失敗ですが、作品そのものは私の目には『それほど悪くない』ように写ります。
私には、意図的に近代現代の絵画スタイルに変更されたのか、あるいは修復師の技術が劣悪で単に失敗したのかは完全には断定できません。 つまり、悪意あるいは意図をもって、修復ではなく「創造」が行われた可能性があるということです。
ここからが私の本題です。 18世紀までは、絵画は現在の写真の役割も担っていました。 当時の人たちに、現代の写実を廃したポープアートや漫画を芸術絵画として見せたらどうなるのか? 彼らは下手クソというに決まってますね。 私は 村上隆の作品は嫌いなのですが、彼の主張する『スーパーフラット理論』は正しいと考えます。 スーパーフラット理論とは、今日の日本のマンガやアニメにおける平面性は日本の美術における平面表現の延長にあり、スーパーフラットは戦後日本の無階級社会や一様で均質的なポップカルチャーを現すものでもあるという主張です。
このスーパーフラット理論は、村上作品における芸術理論の核であり、彼が深く探求する中心的概念だそうです。 スーパーフラット展が、2001年7から10月に Walker Art Center(ミネアポリス)、11月から2002年3月に Henry Art Gallery(シアトル)で巡回電磁が行われ、これらの展示で、あまり知られていない日本の文化を海外に紹介することに貢献しました。 リトル・ボーイ展では、2005年にニューヨークのジャパン・ソサエティで開催された村上隆が企画するグループ展で、10人の日本人アーティストの展覧会でした。 リトル・ボーイの名前の由来は、広島に落とされた原子爆弾のニックネームからきています。 原爆の影響によって日本人は幼児的で特殊な奇形的文化を形成、さらにこのような文化を生み出したきっかけはアメリカにもある、というのが村上の主張です。
欧州の芸術絵画はキリスト教の教会中心に発展してきました。 バルトロメ・エステバン・ムリーリョの作品、エリアス・ガルシア・マルティネスのフレスコ画、16世紀に作られた木彫りの聖ジョージ像は全てキリスト教美術です。 言ってみれば、階級社会の象徴のようなものです。 無政府主義者や共産主義者の修復師が権力に歯向かって、修復作業で意図的に近代現代の絵画スタイルをそのまま踏襲したとした可能性がある、というのは考えすぎでしょうか。 さらに、現在の時代に描くのだから(平等社会を反映する)現代のスタイルで描くのが本筋であるという主張も一理あります。
ただ、私には別の意見があります。 バルトロメ・エステバン・ムリーリョの作品「The Immaculate Conception of Los Venerables」の修復画、エリアス・ガルシア・マルティネスのフレスコ画「この人を見よ」の修復画、16世紀に作られた木彫りの聖ジョージ像の修復像が【 近代現代の絵画スタイルをそのまま踏襲している 】ことです。 勿論、修復(複製)としては完全に失敗ですが、作品そのものは私の目には『それほど悪くない』ように写ります。
私には、意図的に近代現代の絵画スタイルに変更されたのか、あるいは修復師の技術が劣悪で単に失敗したのかは完全には断定できません。 つまり、悪意あるいは意図をもって、修復ではなく「創造」が行われた可能性があるということです。
ここからが私の本題です。 18世紀までは、絵画は現在の写真の役割も担っていました。 当時の人たちに、現代の写実を廃したポープアートや漫画を芸術絵画として見せたらどうなるのか? 彼らは下手クソというに決まってますね。 私は 村上隆の作品は嫌いなのですが、彼の主張する『スーパーフラット理論』は正しいと考えます。 スーパーフラット理論とは、今日の日本のマンガやアニメにおける平面性は日本の美術における平面表現の延長にあり、スーパーフラットは戦後日本の無階級社会や一様で均質的なポップカルチャーを現すものでもあるという主張です。
このスーパーフラット理論は、村上作品における芸術理論の核であり、彼が深く探求する中心的概念だそうです。 スーパーフラット展が、2001年7から10月に Walker Art Center(ミネアポリス)、11月から2002年3月に Henry Art Gallery(シアトル)で巡回電磁が行われ、これらの展示で、あまり知られていない日本の文化を海外に紹介することに貢献しました。 リトル・ボーイ展では、2005年にニューヨークのジャパン・ソサエティで開催された村上隆が企画するグループ展で、10人の日本人アーティストの展覧会でした。 リトル・ボーイの名前の由来は、広島に落とされた原子爆弾のニックネームからきています。 原爆の影響によって日本人は幼児的で特殊な奇形的文化を形成、さらにこのような文化を生み出したきっかけはアメリカにもある、というのが村上の主張です。
欧州の芸術絵画はキリスト教の教会中心に発展してきました。 バルトロメ・エステバン・ムリーリョの作品、エリアス・ガルシア・マルティネスのフレスコ画、16世紀に作られた木彫りの聖ジョージ像は全てキリスト教美術です。 言ってみれば、階級社会の象徴のようなものです。 無政府主義者や共産主義者の修復師が権力に歯向かって、修復作業で意図的に近代現代の絵画スタイルをそのまま踏襲したとした可能性がある、というのは考えすぎでしょうか。 さらに、現在の時代に描くのだから(平等社会を反映する)現代のスタイルで描くのが本筋であるという主張も一理あります。
Posted by もののけ at 2020年06月28日 16:23
もののけ様
同意です。
テーセウスのパラドックスというのがあります。
オリジナルに改修や部品追加を重ねていくうちに、元の姿と似てはいても実態が完全に入れ替わるのはオリジナルと言えるか?というものです。 古美術品はかなりの割合で修復がなされています。「最後の晩餐」も過去5~6回は修復作業が入ったそうですが、絵の具の特性の違いがわからず20世紀後半の科学分析による修復作業までは、完全には果たせなかったそうです。
村上隆の作風は何ら斬新でも新しいコンセプトでもありませんよね。
昔からある漫画やアニメの作風にポップ風のテイストを加味しただけのものですが、日本のサブカル人気の西欧では結構評価が高いというだけでしょう。
スーパーフラット理論というのを知らなかったのでググってウィキの解説を読んでみたのですが、正直浅学な私にはわかりませんでしたw 昔からある日本画的な空間概念が漫画やアニメにもみられるのは一般常識としてわかるとしても、「オタクを構成している基本的な願望と、第二次世界大戦敗戦後の日本文化全体の構造」なんてのは私には理解できません。
>原爆の影響によって日本人は幼児的で特殊な奇形的文化を形成、
さらにこのような文化を生み出したきっかけはアメリカにもある
これもまったく意味不明です。
>無政府主義者や共産主義者の修復師が権力に歯向かって、
修復作業で意図的に近代現代の絵画スタイルをそのまま踏襲した
とした可能性がある
そうは思いません。
ジョルジョ像の塗りは単純に素人に毛の生えた人の、稚拙故の技術的結果だと思います。もし無政府主義とか共産主義者なら、元来宗教を否定する人ですから作業を断るでしょう。というか破壊するんじゃないかな・・・
同意です。
テーセウスのパラドックスというのがあります。
オリジナルに改修や部品追加を重ねていくうちに、元の姿と似てはいても実態が完全に入れ替わるのはオリジナルと言えるか?というものです。 古美術品はかなりの割合で修復がなされています。「最後の晩餐」も過去5~6回は修復作業が入ったそうですが、絵の具の特性の違いがわからず20世紀後半の科学分析による修復作業までは、完全には果たせなかったそうです。
村上隆の作風は何ら斬新でも新しいコンセプトでもありませんよね。
昔からある漫画やアニメの作風にポップ風のテイストを加味しただけのものですが、日本のサブカル人気の西欧では結構評価が高いというだけでしょう。
スーパーフラット理論というのを知らなかったのでググってウィキの解説を読んでみたのですが、正直浅学な私にはわかりませんでしたw 昔からある日本画的な空間概念が漫画やアニメにもみられるのは一般常識としてわかるとしても、「オタクを構成している基本的な願望と、第二次世界大戦敗戦後の日本文化全体の構造」なんてのは私には理解できません。
>原爆の影響によって日本人は幼児的で特殊な奇形的文化を形成、
さらにこのような文化を生み出したきっかけはアメリカにもある
これもまったく意味不明です。
>無政府主義者や共産主義者の修復師が権力に歯向かって、
修復作業で意図的に近代現代の絵画スタイルをそのまま踏襲した
とした可能性がある
そうは思いません。
ジョルジョ像の塗りは単純に素人に毛の生えた人の、稚拙故の技術的結果だと思います。もし無政府主義とか共産主義者なら、元来宗教を否定する人ですから作業を断るでしょう。というか破壊するんじゃないかな・・・
Posted by トラネコ at 2020年06月28日 16:53
at 2020年06月28日 16:53
 at 2020年06月28日 16:53
at 2020年06月28日 16:53トラネコ さま
素人に毛の生えた程度の人に修復作業をさせる事自体が、私には理解不能です。 正直言って、技術がなくて描けないよりも、修復作業で意図的に現代スタイルで描く方が、遥かにましだと思います。 もしスペインが、技能育成が出来ないほど美術教育が腐っているとすれば、深刻な状況です。
というのは、時代の流れとして現代美術の主流のスタイルが曖昧になっており、結果的に抽象画とポップ・アートしか残らないように見えるからです。 実写技能が軽んじられた末には、芸術絵画自体が存在しない状態になりかねない。 そうなると、修復の技術が廃れてしまっても仕方ないです。
私が村上隆の作品が嫌いなのは「日本人の漫画やアニメは幼児的で特殊な奇形的文化」とこけ下ろしておきながら、それを商売の種にして大きな利益を得ているからです。 すべてが遊びであり金儲けの手段に過ぎないという末期状態を感じます。
素人に毛の生えた程度の人に修復作業をさせる事自体が、私には理解不能です。 正直言って、技術がなくて描けないよりも、修復作業で意図的に現代スタイルで描く方が、遥かにましだと思います。 もしスペインが、技能育成が出来ないほど美術教育が腐っているとすれば、深刻な状況です。
というのは、時代の流れとして現代美術の主流のスタイルが曖昧になっており、結果的に抽象画とポップ・アートしか残らないように見えるからです。 実写技能が軽んじられた末には、芸術絵画自体が存在しない状態になりかねない。 そうなると、修復の技術が廃れてしまっても仕方ないです。
私が村上隆の作品が嫌いなのは「日本人の漫画やアニメは幼児的で特殊な奇形的文化」とこけ下ろしておきながら、それを商売の種にして大きな利益を得ているからです。 すべてが遊びであり金儲けの手段に過ぎないという末期状態を感じます。
Posted by もののけ at 2020年06月28日 21:06
私もスーパーフラット理論は、それほど厳密に検討した訳ではありませんが、日本美術を誤解した軽薄な理論に思えてなりません。そもそも、東洋美術=平面などという決めつけ自体が、ラカンの亜流の構造主義者の西洋中心主義から生まれた、浅学なものの見方の産物だと思います。おそらくこれが、スーパーフラット理論の基礎をなしているのでしょう。東洋画にも空間や立体の認識はありますが、それが西洋とは全く別の認知や、絵画構造をなしているということであり、簡単に言えば、構造主義者の礼賛するベラスケスのラス・メニーナスで、西洋人がやったことを、東洋人(日本人)は当たり前のようにやってきたとうことです。一般の西洋画では、日本の前近代美術のような、自分が画面の中に入って、登場人物になるような、いまでいう「なりきり」のような真似はできません。これは空間認知の違いから来るのであって、東洋画の平面性というのは誤解なのです。
レイヤー空間
http://raq-hiphop.com/post-2112/
さらに言えば、東洋画の基礎デッサンの18手の線描は、西洋画の明暗法のような質量描写ではなく、様々な線の組み合わせで、構造と質感を同時に表現するところにミソがあります。これが、レイヤー空間に適合するのです。おそらく書ですら、奥行きのある空間意識の上に成立しているのだと思います。ただ、それは西洋の質量を持つ物質により形成された、自他を分離した客観的世界としての空間認知とは異なるのです。
ここからは、個人の偏見に満ちた考えですが、西洋の近代医美術というのは、上記の西洋流の空間認知が、写真や映画によって、俗的な世界では、そのお株を奪われてしまったために、それ以外の方法で生き残ろうとした、チンドン屋的な作業なのです。そのために、日本の浮世絵やアフリカ美術や、もろもろの異なる要素を取り入れ、つぎはぎしたものを作りましたが、その背後にあるのは、近代独特の進歩主義の思想だと思います。しかし、どう見ても、美術や音楽や文学といった芸術が、近代において進歩したとは思えません。そして、この進歩主義自体が、君主制を打破し、古い権威を足蹴にする、アナーキズムや共産主義とも結びついていくのでしょう。そうした意味では、素人修復による古典美術の近代化や凌辱のような行為が、思想的に歓迎されているのかもしれませんが。
とにかく近代は終了しました。そして進歩主義も古いものになったのです。進化論ですら、下等から高等生物への進化という概念ではなく、たんなる環境に対する適応的変化の考えに代わっている、ということです。
レイヤー空間
http://raq-hiphop.com/post-2112/
さらに言えば、東洋画の基礎デッサンの18手の線描は、西洋画の明暗法のような質量描写ではなく、様々な線の組み合わせで、構造と質感を同時に表現するところにミソがあります。これが、レイヤー空間に適合するのです。おそらく書ですら、奥行きのある空間意識の上に成立しているのだと思います。ただ、それは西洋の質量を持つ物質により形成された、自他を分離した客観的世界としての空間認知とは異なるのです。
ここからは、個人の偏見に満ちた考えですが、西洋の近代医美術というのは、上記の西洋流の空間認知が、写真や映画によって、俗的な世界では、そのお株を奪われてしまったために、それ以外の方法で生き残ろうとした、チンドン屋的な作業なのです。そのために、日本の浮世絵やアフリカ美術や、もろもろの異なる要素を取り入れ、つぎはぎしたものを作りましたが、その背後にあるのは、近代独特の進歩主義の思想だと思います。しかし、どう見ても、美術や音楽や文学といった芸術が、近代において進歩したとは思えません。そして、この進歩主義自体が、君主制を打破し、古い権威を足蹴にする、アナーキズムや共産主義とも結びついていくのでしょう。そうした意味では、素人修復による古典美術の近代化や凌辱のような行為が、思想的に歓迎されているのかもしれませんが。
とにかく近代は終了しました。そして進歩主義も古いものになったのです。進化論ですら、下等から高等生物への進化という概念ではなく、たんなる環境に対する適応的変化の考えに代わっている、ということです。
Posted by キジトラ at 2020年06月28日 21:34
at 2020年06月28日 21:34
 at 2020年06月28日 21:34
at 2020年06月28日 21:34もののけ様
現代美術は70年代で終わったと私は見ています。
80年代以降はレーザーアートやCGなど機械を使ったテクノロジー系のものしか生まれていないように思います。コンセプチュアル・アートが出た時点で既に終焉したのではないでしょうか? それはいみじくもA.ウォーホールが述べたように「生活そのもの、生きている事自体がアートである!」という言葉に表れていますが、人間の生命活動=行為それ自体が芸術ならば、従来の造形芸術は何なんだ?とおもうのですが、これこそがコンテンポラリーアートの究極の表現形態だったといえるのかもしれません。 しかし近年美術館で開催されているいくつかのコンクール展を見ると、再び絵画という表現形式、それも写実的な具象絵画に回帰している傾向があり、やはり「描く造形表現」という原則としての認識が戻ってきているように感じます。まあ絵は絵でいいんじゃないですか?
キジトラ様
西洋絵画の空間認識は三次元の有限空間の二次元表現という意味で写実に徹する、まあカメラの代替的な表現から出発していると思います。ところが日本画は一種の哲学的な無限空間を表しており、余白がそれを表していると思います。余白は西洋絵画では未完成な「部分」としてしか見ないでしょう。なぜなら限定された三次元空間ですから何もない空間は存在せず、例えばターナーなどの光や大気の存在を表現するという手法もあるのです。
しかし日本画では例えば掛け軸に柿が一個だけ描かれていても完成であり、余白が一個の柿の実在を高める演出をしていると考えられます。だから日本画の余白は「描かない」演出効果という表現があると思います。円山応挙の「氷図」を一度ご覧になってください。そこには湖面に張った氷のヒビだけが明快な線によって表現され、その他は何も描かれていませんが、冬の寒さがそれだけで緊張感を醸し出しています。余計なものを描かず余白が演出する空間なのです。
西洋と東洋の絵画における空間表現そのものの概念が異なるということでしょうね。それで私はそのスーパーフラット(超平面?)がわかりませんw
現代美術は70年代で終わったと私は見ています。
80年代以降はレーザーアートやCGなど機械を使ったテクノロジー系のものしか生まれていないように思います。コンセプチュアル・アートが出た時点で既に終焉したのではないでしょうか? それはいみじくもA.ウォーホールが述べたように「生活そのもの、生きている事自体がアートである!」という言葉に表れていますが、人間の生命活動=行為それ自体が芸術ならば、従来の造形芸術は何なんだ?とおもうのですが、これこそがコンテンポラリーアートの究極の表現形態だったといえるのかもしれません。 しかし近年美術館で開催されているいくつかのコンクール展を見ると、再び絵画という表現形式、それも写実的な具象絵画に回帰している傾向があり、やはり「描く造形表現」という原則としての認識が戻ってきているように感じます。まあ絵は絵でいいんじゃないですか?
キジトラ様
西洋絵画の空間認識は三次元の有限空間の二次元表現という意味で写実に徹する、まあカメラの代替的な表現から出発していると思います。ところが日本画は一種の哲学的な無限空間を表しており、余白がそれを表していると思います。余白は西洋絵画では未完成な「部分」としてしか見ないでしょう。なぜなら限定された三次元空間ですから何もない空間は存在せず、例えばターナーなどの光や大気の存在を表現するという手法もあるのです。
しかし日本画では例えば掛け軸に柿が一個だけ描かれていても完成であり、余白が一個の柿の実在を高める演出をしていると考えられます。だから日本画の余白は「描かない」演出効果という表現があると思います。円山応挙の「氷図」を一度ご覧になってください。そこには湖面に張った氷のヒビだけが明快な線によって表現され、その他は何も描かれていませんが、冬の寒さがそれだけで緊張感を醸し出しています。余計なものを描かず余白が演出する空間なのです。
西洋と東洋の絵画における空間表現そのものの概念が異なるということでしょうね。それで私はそのスーパーフラット(超平面?)がわかりませんw
Posted by トラネコ at 2020年06月29日 11:54
at 2020年06月29日 11:54
 at 2020年06月29日 11:54
at 2020年06月29日 11:54キジトラ さま
>> スーパーフラット理論は… ラカンの亜流の構造主義者の西洋中心主義から生まれた、浅学なものの見方の産物
村上隆がそういう時代の背景を意識していたのは明らかでしょう。 ポスト構造主義とは酷い言い方をするなら「理想主義など幻想」というものの見方であり、近代(歴史・思想・芸術は進歩するという信仰、理想主義)は終わったというのも、同じ時代思考です。 私の考えですが、人間はその時代その時代に最善と考えられる理想を追い求めるべきであり、たとえ進化はなくとも理想は存在します。
レイヤー空間という話は初めて聞きました。 私個人は、日本画は目に見える実写よりも、人がどう見るかどう感じるかに重きを置いた結果であり、それによって、現実には存在しない輪郭や遠近法を無視した遠近認識があると理解していました。 絵画修復の問題の背景には、写実芸術の流行の衰退があると想像します。 昔だったら、修復が以前と同じように見えなければ決して許されなかったはずです。
村上隆の作品は、たちの悪い概念の芸術(Conceptual Art)であり、ポストモダンの(近代は終わった)概念と日本のサブカルチャーである漫画を融合した「第2の浮世絵的な、西洋にない目新しさ」を意図的に演出したものです。 彼らの作品がビジネスとして成り立っているのは、美術作品が投資やマネーロンダリングの対象となっているマネー経済があるからです。
>> スーパーフラット理論は… ラカンの亜流の構造主義者の西洋中心主義から生まれた、浅学なものの見方の産物
村上隆がそういう時代の背景を意識していたのは明らかでしょう。 ポスト構造主義とは酷い言い方をするなら「理想主義など幻想」というものの見方であり、近代(歴史・思想・芸術は進歩するという信仰、理想主義)は終わったというのも、同じ時代思考です。 私の考えですが、人間はその時代その時代に最善と考えられる理想を追い求めるべきであり、たとえ進化はなくとも理想は存在します。
レイヤー空間という話は初めて聞きました。 私個人は、日本画は目に見える実写よりも、人がどう見るかどう感じるかに重きを置いた結果であり、それによって、現実には存在しない輪郭や遠近法を無視した遠近認識があると理解していました。 絵画修復の問題の背景には、写実芸術の流行の衰退があると想像します。 昔だったら、修復が以前と同じように見えなければ決して許されなかったはずです。
村上隆の作品は、たちの悪い概念の芸術(Conceptual Art)であり、ポストモダンの(近代は終わった)概念と日本のサブカルチャーである漫画を融合した「第2の浮世絵的な、西洋にない目新しさ」を意図的に演出したものです。 彼らの作品がビジネスとして成り立っているのは、美術作品が投資やマネーロンダリングの対象となっているマネー経済があるからです。
Posted by もののけ at 2020年06月29日 12:26
もののけ様
>近代(歴史・思想・芸術は進歩するという信仰、理想主義)は終わったというのも、同じ時代思考です。
それはそうでしょう。どんなものであれ、時代思考でない思考なんてありません。
>人間はその時代その時代に最善と考えられる理想を追い求めるべきであり、たとえ進化はなくとも理想は存在します。
たしかに存在しますが、今日の悪はかつての善、というニーチェの言葉のように、これもくるくる変わります。たとえば、ナチスのような徹底した人種差別主義は、当時としては、まさに理想主義の権化であって、悪いことでも何でもなかった。コーカソイド(正当なノアの子孫の人間様)という言葉からも理解できるように、人だか何だかわからない、ネグロイドやモンゴロイドを、コーカソイドが支配して当然だったのです。それを、アーリアンという伝説でさらに厳格化したナチスは、まさに理想主義の権化でした。
では、今日の理想と何なのでしょう?人類みな兄弟、地球環境を守り、世界をあらゆる民族で平等に共有しましょう、という、グローバリズムの雑民主義でしょうか?それとも、いまだに止まぬ、共産主義というキリスト教の亜種でしょうか?
いずれにせよ、理想の全てが悪いとはいいませんが、そんなものは相対的なものにすぎないというのが、私の実感です。自由平等博愛だって、ほどほどならいいんです。でも、それが宗教化してしまうと、いつのまにか、不自由不平等残酷になっていくのです。
美術に話を戻せば、西洋のモダニズムという乱痴気騒ぎが、西洋芸術の終焉と言っていいような気がします。ジャッドのミニマルアートの金属の箱とか、カラーフィールドペインティングという巨大一色の板のような絵画?とか、美術館に便器を置いて美の麻薬中毒患者を笑うダダイストデュシャンの悪戯とか、そのあたりで西洋美術は終わったと見ています。
その後の廃墟と化した西洋美術の中で漂う、たよりない亡霊のような、コンセプチュアルアートは、芸術とは概念であって、それを伝えれば作品なんてあってもなくてもいい、というもので、おおむね今日の美術は、作品があってもこの概念過剰の毒素に当てられているという点では、コンセプチュアルアートの類型と見ることも可能です。
トラネコ様
応挙の実験絵画は様々なものを見ています。現代美術家など及びもつかない、優れた技巧と実験精神を合わせ持った作家だったと思います。
>限定された三次元空間ですから何もない空間は存在せず、例えばターナーなどの光や大気の存在を表現するという手法もあるのです。
余白には様々な定義があるようですが、仰るように、ターナーの白い地の残っているところは、厳密には余白ではなく、大気や光の表現の一部、物理空間の描写の一部分です。これは近代以後の春草などの作品も同様かもしれません。ただ彼の空間は特殊な、グリーンバーグがオプッティカルイリュージョン(錯覚的幻覚?)とでも称したような、疑似空間とでもいうべきもので、ちょうど平面と空間の中間のような状態であり、そこにおいて、本来相容れないはずの、琳派風の線描と、西洋風の立体質感描写が共存しているのです。わかりにくいことを言っているのかもしれませんが、例えば落葉のシリーズを実物でよく見ていただくと、ご理解いただけるのではないかと思います。
私は二本画を始めた頃、皆があまりに余白が日本のお家芸のように言うので、それに反発した考えを持っていました。
だって、西洋絵画のように、余白のない絵のほうが、珍しいのではないでしょうか。
子供の描く絵、暴走族の落書き、原始時代の洞窟壁画、中世のヨーロッパ美術、・・・・みな余白だらけです。
私の師匠は、余白を多用し、見えない風景や風情を描いている、みたいなことを言いますが、正直懐疑的でした。余白とは、ひとつの解釈として、よけいなものを捨てて、描きたいもの、見せたいもの、に集中する、ということであれば、子供の絵でも同様です。でも、それでもいいと考えています。要はいかにそれを上手く用いるか、ということで、ある意味書のセンスにも通じるものがあると思います。
>近代(歴史・思想・芸術は進歩するという信仰、理想主義)は終わったというのも、同じ時代思考です。
それはそうでしょう。どんなものであれ、時代思考でない思考なんてありません。
>人間はその時代その時代に最善と考えられる理想を追い求めるべきであり、たとえ進化はなくとも理想は存在します。
たしかに存在しますが、今日の悪はかつての善、というニーチェの言葉のように、これもくるくる変わります。たとえば、ナチスのような徹底した人種差別主義は、当時としては、まさに理想主義の権化であって、悪いことでも何でもなかった。コーカソイド(正当なノアの子孫の人間様)という言葉からも理解できるように、人だか何だかわからない、ネグロイドやモンゴロイドを、コーカソイドが支配して当然だったのです。それを、アーリアンという伝説でさらに厳格化したナチスは、まさに理想主義の権化でした。
では、今日の理想と何なのでしょう?人類みな兄弟、地球環境を守り、世界をあらゆる民族で平等に共有しましょう、という、グローバリズムの雑民主義でしょうか?それとも、いまだに止まぬ、共産主義というキリスト教の亜種でしょうか?
いずれにせよ、理想の全てが悪いとはいいませんが、そんなものは相対的なものにすぎないというのが、私の実感です。自由平等博愛だって、ほどほどならいいんです。でも、それが宗教化してしまうと、いつのまにか、不自由不平等残酷になっていくのです。
美術に話を戻せば、西洋のモダニズムという乱痴気騒ぎが、西洋芸術の終焉と言っていいような気がします。ジャッドのミニマルアートの金属の箱とか、カラーフィールドペインティングという巨大一色の板のような絵画?とか、美術館に便器を置いて美の麻薬中毒患者を笑うダダイストデュシャンの悪戯とか、そのあたりで西洋美術は終わったと見ています。
その後の廃墟と化した西洋美術の中で漂う、たよりない亡霊のような、コンセプチュアルアートは、芸術とは概念であって、それを伝えれば作品なんてあってもなくてもいい、というもので、おおむね今日の美術は、作品があってもこの概念過剰の毒素に当てられているという点では、コンセプチュアルアートの類型と見ることも可能です。
トラネコ様
応挙の実験絵画は様々なものを見ています。現代美術家など及びもつかない、優れた技巧と実験精神を合わせ持った作家だったと思います。
>限定された三次元空間ですから何もない空間は存在せず、例えばターナーなどの光や大気の存在を表現するという手法もあるのです。
余白には様々な定義があるようですが、仰るように、ターナーの白い地の残っているところは、厳密には余白ではなく、大気や光の表現の一部、物理空間の描写の一部分です。これは近代以後の春草などの作品も同様かもしれません。ただ彼の空間は特殊な、グリーンバーグがオプッティカルイリュージョン(錯覚的幻覚?)とでも称したような、疑似空間とでもいうべきもので、ちょうど平面と空間の中間のような状態であり、そこにおいて、本来相容れないはずの、琳派風の線描と、西洋風の立体質感描写が共存しているのです。わかりにくいことを言っているのかもしれませんが、例えば落葉のシリーズを実物でよく見ていただくと、ご理解いただけるのではないかと思います。
私は二本画を始めた頃、皆があまりに余白が日本のお家芸のように言うので、それに反発した考えを持っていました。
だって、西洋絵画のように、余白のない絵のほうが、珍しいのではないでしょうか。
子供の描く絵、暴走族の落書き、原始時代の洞窟壁画、中世のヨーロッパ美術、・・・・みな余白だらけです。
私の師匠は、余白を多用し、見えない風景や風情を描いている、みたいなことを言いますが、正直懐疑的でした。余白とは、ひとつの解釈として、よけいなものを捨てて、描きたいもの、見せたいもの、に集中する、ということであれば、子供の絵でも同様です。でも、それでもいいと考えています。要はいかにそれを上手く用いるか、ということで、ある意味書のセンスにも通じるものがあると思います。
Posted by キジトラ at 2020年06月29日 18:51
at 2020年06月29日 18:51
 at 2020年06月29日 18:51
at 2020年06月29日 18:51